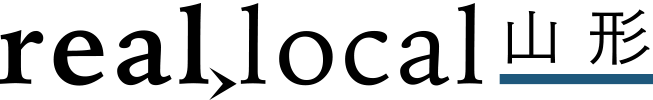わたしの山形日記/異国の地での「だし」
連載
やまがたにUターンして暮らす筆者が、なにげない日々のなかで見つけたこの街の魅力について綴る連載日記です。
今年の夏、お天道様がカンカン照りのある日、冷房のあまり効かない台所で「だし」を作っておりました。じんわりと汗をかきながら黙々と野菜を刻んでいると、「そういえば」と、かつて異国の地でだし作りに挑戦したときのことを思い出しました。
「だし」をご存じですか。山形で食される夏の郷土料理のひとつです。きゅうりと茄子を基本の材料とし、みょうがや大葉、ししとうなどの夏野菜を加え、それらをすべて刻んで、しょうゆやめんつゆで味付けします。ご飯にのせたり冷奴にかけたり、そうめんの薬味にしたりと使い方は万能です。
使う野菜は地域や家庭によってさまざま。どんな材料でも刻んでしまえば、すべて「だし」と呼ばれます。ちょうど、夏野菜の地物が収穫されだす6月頃から食卓に上り始めます。暑さで食欲が落ちたり、農作業で忙しかったりするこの季節、さっと作れてさっぱりと食べられる「だし」は、山形の夏を乗り切るために昔から重宝されてきました。

わたしは以前、南半球にあるフィジーという国で暮らしていました。食事はほぼ自炊だったこともあり、新鮮で安価な野菜を求めて市場へよく足を運んでおりました。市場の中も外も色とりどりの野菜や果物たちがずらっと並んでいて、いつも地元の人で大賑わい。温かい気候のせいか、トマトやきゅうりや茄子など、日本でいわゆる夏野菜と呼ばれるものが通年売られていました。


外国にいても「日本食が恋しい」とはあまり思わないタチなのですが、あるときふと「だしを作ってみようかな」と思いつきました。材料はきゅうりと茄子と、粘りを出すためのオクラを少々。味付けに必要なしょうゆは簡単に買えましたし、お土産でいただいためんつゆもありました。
皮が硬いきゅうりと茄子は、彩りも考えてしましまにむいて刻みました。きゅうりは種も取りました。オクラは硬く筋っぽいため、茹でてから細かくたたきました。刻んだ野菜に、しょうゆとほんの少しのめんつゆを加えます。ひとくち食べてみると、記憶の味と多少違うものの、異国で作ったにしては「おお!『だし』だ!」と思わずテンションが上がる仕上がりになりました。白ご飯と一緒に食べると、より慣れ親しんだ故郷の味に近づきます。「日本から7000km離れた南国で、『だし』を食べている」、それはとても不思議な感覚でした。もしかしたら無意識に故郷を求めていたのかもしれません。
だしの季節になるとどうしても思い出すことが、もうひとつあります。あれは京都でひとり暮らしを始めたばかりのころのこと。夏の少し手前の季節に、母親からパンパンの段ボール箱が届きました。開けてみると、最初に目に飛び込んできたのは「なっとう昆布」のパッケージ。「なっとう昆布」というのは、だし作り用に売られている「がごめ昆布」のことで、水分を加えると強い粘りが出るのが特徴です。我が家のだしには欠かせない重要なアイテムです。
なっとう昆布と一緒に、だしの材料であるきゅうりと茄子も入っていました。「届いたらすぐ作れるように」という母親のやさしさだったと思います。「きゅうりと茄子くらい自分で買えるのに…」とつよがりつつ、本音はうれしくて。あれもこれもと送ってくれた材料を目の前にして、「これは作るしかない」とキッチンに立ちました。

当時「だしは一度にたくさん作るもの」とだけ覚えていたわたしは、分量など特に考えず、届いたきゅうりと茄子をすべて刻みました。途中、「あれ?これ多すぎるかも?」と思いつつ、「中途半端に残すのもな…切っちゃえ」と刻みきりました。てんこ盛りの野菜を見て、なっとう昆布も「これじゃ足りないかも…もう少し入れよう」と3回くらい継ぎ足し、最終的に超ボリューミーで超ネバネバのだしが鍋いっぱいにできあがってしまいました。
小さなひとくちコンロがあるだけの狭小キッチンに、「だし」でいっぱいの大きな鍋。見事に対照的でシュールなその光景が、いまも鮮やかに脳裏に浮かぶのです。
野菜の大きさは不揃いで、異常にネバネバで、ビジュアル的には理想通りとはいきませんでした。でもひとさじ食べた瞬間、シャキシャキとした野菜の歯ごたえと、それを包むなっとう昆布の粘り、噛むたびに鼻に抜ける夏野菜の香り…。「これこれ!」と、わたしの中の『山形』が反応しました。

その場所にいると当たり前すぎてなんでもないと思うようなものが、外に出たときに実は特別なものだったとわかる、ということはよくあります。郷土の料理はその最たるものでしょう。その風土と一緒に味わってこそ、魅力を最大限に感じられるのかもしれません。しかし一方で、まったく環境のちがう、遠く離れた場所で食べるからこそ、普段は意識しない自分の奥底にある「その場所=郷土」を強烈に感じる、ということもある気がします。フィジーや京都での体験はまさにそれでした。
家庭ごとにレシピがあるといわれる山形の「だし」。多少材料や味わいに違いがあっても、すべて引っくるめて「だし」と呼ばれてきました。このおおらかな文化背景が、異国の地で少しくらい違う種類の食材を使っても、「これは『だし』だ!」と思わせてくれるのかもしれません。