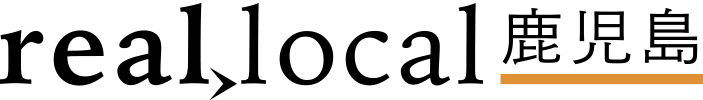【鹿児島県さつま町】足元を見つめ、まちに小さなうねりを生み出す / 堀之内酒店 堀之内力三さん
インタビュー

今置かれている状況を、どう打破していくか
高校時代、レスリングに青春を捧げた力三さん。
入学した高校が強豪校だったため、練習にもついていけず、最初は辛い日々だったといいます。
「僕は他のチームメイトに比べて体力が劣っていたからか、基礎トレーニングすらついていけず、そのたびにやり直しになって…。最初は泣きながら練習していました。」
「チームメイトの一人と親しくなり、朝練の前から二人で自主練をしていました。次第に、力がついてきて、何と1年生の終わりには二人ともレギュラーになれることができたんです。」
「レスリングって、強い選手だと早ければ10秒以内で試合を終わらせられます。けれど、僕は持久戦ばかりで10分間フルに戦う試合ばかりでした。どうやったら対戦相手に勝つことができるか。それを常に意識していました。」
「自分の能力や今置かれている状況で、現状をどう打破していくか。その思考は今でも繋がっていると思います。さつま町で仕事や活動をするにあたっても同じです。」

高校卒業後、社会人経験を経て家業の『堀之内酒店』を継業することになります。
当時、焼酎ブームといわれ、世の中の焼酎人気が上昇していました。
しかし、継業したばかりの力三さんはお酒の知識や商売の仕方もわからないことだらけだったそうです。
「パソコンを購入し、当時のトレンドを調べました。フューチャーされているお酒の専門店は卸屋から仕入れているのではなく、直接現地へ出向き、造り手と信頼関係を築いた上で仕入れていることを知りました。」
「ある時、ずっと気になっていた酒屋さんに出向いて、色々お話を聞かせてもらうことがあったんです。その時のことが今でも忘れられません。」
「店主さんから「さつま町にも良いモノは揃っているじゃないか」「それを君らしく、焼酎と結びつけることができれば、どこにもないお店ができるはずだ」「まずは自分の足元を見つめなおしなさい」と力強い言葉をいただきました。」
そこから、さつま町を舞台に力三さんのアクションが始まるのです。



ラベルの向こう側に、語りたくなる味がある
継業当時、『堀之内酒店』では焼酎をほとんど販売していませんでした。
そこで焼酎の販売を蔵元に申し出るも取引に至れなかったそうです。
「そんな時、手を差し伸べてくれたのが『小牧醸造株式会社』の皆さんでした。」
「焼酎の勉強をしたいとお願いしたところ、2週間程入らせてもらいました。勉強といっても、知識を叩き込むのではなく、現場の農家さんや造り手さんと一緒に汗を流し、夜は宴会をしてコミュニケーションをとる時間でした。」
「次第に気づいたんです。お酒づくりの背景には色々な人や想いがあって、たくさん苦労しているんだと。」
「蔵元で造り手の皆さんと飲むお酒は本当に美味しいと感じました。お酒の背景を伝える仕事なら酒屋でもできるし、そこからスタートしてみよう。それが今の『堀之内酒店』としてのスタイルの始まりでした。」
「焼酎はお客さんの日常生活における様々なシーンへと旅立っていきます。「美味しい」と言いながら喜怒哀楽を分かちあう。そんなことを考えると酒屋って素敵な仕事だなと思うんです。」
「“ラベルの向こう側”というのを意識するようにもなり、それがお店のコンセプトの元にもなりました。」

その後、薩摩心酔会という蔵元・酒屋・飲食店・消費者の4者が集まる会が立ち上がり、そこから19歳の焼酎プロジェクトへ発展していきました。
そのプロジェクトとは
年が明け、新成人を迎える19歳の人たちと故郷の文化である芋焼酎づくりを一緒に体験し、成人式当日に造った焼酎で祝杯をあげる企画です。
今年で9年目の取り組みになります。
「行政や地元の企業のサポートもあり、継続できています。回を重ねていくごとに、私の同世代の親の子たちが成人になってきて、理解してくださる方も増えてきました。」
「企画に参加してくれた子たちとは今でも付き合いがあります。例えば、お客さんとして酒屋へ買い物に来てくれたり。」
「印象的だったのが、あるお父さんから伺った話でした。このプロジェクトがきっかけで「お父さん、地元の焼酎を飲んでよ」「このお酒は〜〜〜でね」と親子の会話が増えたと嬉しそうに語っていました。」
「成人式の後、5月に芋の苗を植えるところまでがプロジェクトになります。次の成人になる子たちへのバトンになるように、それぞれが想いを込めて植えています。」




垣根を越えて、手を取り合う
19歳の焼酎プロジェクト等がきっかけで、さつま町の商工会青年部へ入った力三さん。
数年経ったある時、ふとしたことがきっかけで商工会主催の弁論大会へ出場することになったそうです。
「弁論大会の出場者を決める会に参加できず、そのまま欠席裁判のような流れで僕に決まってしまったんです。実は、その時期は幽霊部員だったので、それも理由にあると思いますが(笑)。」
「正直、最初は嫌々でした(笑)。でも、次第に僕らの活動を多くの人に知ってもらういい機会だなと思うようになりまして。」
「予想を上回り、県大会、九州大会、そして、まさかの全国大会へと勝ち進みました。」
「当時、さつま町として合併したて時期だったこともあり、商工会として連帯感が足りないなと思っていました。でも、弁論大会がきっかけで一体感が生まれ、温度感も上がっていくのを肌で感じました。」
「その後、商工会としてイベント企画をたくさん行っていき、次第に、まちに対して何かできないかという気持ちが強くなっていきました。」
そんな時、『薩摩のさつま』という言葉が力三さんの耳に入ってきたのです

『薩摩のさつま』はJAが独自ブランドとして立ち上げたものでした。
「これ以上、さつま町を表現する言葉として他にないのではないか?農協や行政、民間の垣根を越えて、統一すればもっとできることがあるのに…。」
ブランド名を知って以降、力三さんの中で悶々とした想いがあり、仲間と会うことがあれば、その話をしたといいます。
「気がつけば次第に話が大きくなって、農協の上の方や商工会、観光特産品会、行政が集まった場で想いをプレゼンする機会をいただいたんです。ありったけの想いを伝えました。」
「話を聞いてくださったみなさんは「若い方が熱い想いをもって動こうとしているんだから、その後押しをしたい」「組織の垣根を越えて、一緒に手をとっていきましょう」とおっしゃってくださいました。」
「その後、まちの仲間同士で時間をかけて今後のビジョンや理念について話し合いました。頼もしい行政職員や北さつま農業協同組合、商工会もサポートしてくださり、何とか昨年3月に『薩摩のさつま』としてスタートを切ることができました。」


小さなうねりが生み出していくもの
『薩摩のさつま』は行政、北さつま農業協同組合、商工会、観光特産品協会が組織の垣根を越えて1つになり、子どもたちの支援を見据えた地域ブランドです。
独自の認証基準を通過した商品は認証品として登録され、ブランド品として県内外で販売されています。
さらに、商品を届けるだけではなく、その商品が生まれた背景にあたる人、風土、歴史といった土地が持つ豊かさをnoteにて発信されているところです。
「『薩摩のさつま』の理念は「褒め合い、支え合い、地域愛」です。例えば、僕がお茶屋さんを紹介して、そのお茶屋さんが農家さんを紹介して、さらに、その農家さんが飲み屋さんを紹介したりといった流れも、その理念から生まれた動きだと思います。」
「皆がそんな風に褒め合って、支え合っていくことで、地域愛に溢れた優しさの連鎖が広がり、まちの魅力が広がるきっかけにもなっていってほしい。そんな想いを込めた理念になります。」
昨年7月からは“地域プロジェクトディレクター”として東京からの移住者を迎え入れ、活動の幅を広げていきます。



ブランドとして立ち上げ、もうすぐ1年が経とうとしています。
その中での手応えや今後の展望について伺いました。
「現状として「さつま町って何がありますか?」と聞かれても、しっかり胸を張って答えられる人は少ないと思います。」
「『薩摩のさつま』を通して、町外への魅力発信だけではなく、住んでいる町内の皆さんが魅力を感じ、誇りを持っていただけたら嬉しいです。」
「noteを読んでくださったある民間会社から「自社の企画で認証商品を取り扱いたい」と要望があったり、取り組みを知ったさつま町出身の県外在住者の方から支援の申し出があったりと、少しずつ認知してもらえていると感じています。」
「noteのメインタイトルを“HAIKEI”(拝啓)としています。届いた手紙を読んでいる時のように、私たちの発信を通して、さつま町の事業者さんの想いや温度感を届け続けたいと思います。」
「さつま町は人と人との距離感が程よい町なので、想いを口にすれば良い意味で伝染しやすいし、それが循環していく仕組みをつくりやすいです。」
「今は小さなうねりかもしれません。でも、その小さなものを絶やさないことで、大きなムーブメントを起こせると信じて、しっかりと足元のあるモノと向き合い続けていきたいです。」