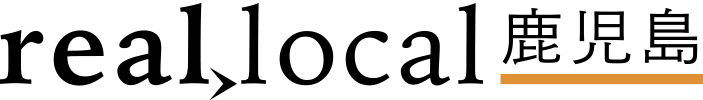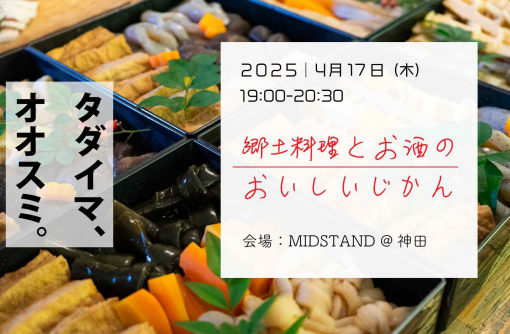【鹿児島県薩摩川内市】「循環経済社会へ向けた、リビングラボプロジェクト活動報告会」開催レポート【後編】
イベントレポート
※本記事は、【後編】です。
【鹿児島県薩摩川内市】「循環経済社会へ向けた、リビングラボプロジェクト活動報告会」開催レポート【前編】からご覧ください。
報告②〈食〉土のデザインプロジェクト「ポスト人間中心のデザインを目指して」

2人目のプロジェクト発表者は、九州大学大学院芸術工学研究院ストラテジックデザイン部門助教の稲村徳州先生。
人間都合のデザインではなく、自然や生態系に目を向けた「ポスト人間中心のデザイン」視点から循環のデザインを考える研究をされています。
土のデザインプロジェクト参加者は、市民10名と学生2名、運営スタッフの十数名。参加者の所有する畑の一部を「SOIL STUDIO」と名付け、プロジェクトの活動拠点とし、参加者は円形の畝(うね)で思い思いの植物や苗を植え、豊かな土づくりを行ったことを報告しました。
瞑想で自分自身と、地球上の生命と向き合う

円形の畝は、薩摩川内市の地域資源・竹を活かし、「竹炭」を含んだ土壌づくり。
プロジェクトで重要視した点については、「重要な概念として、瞑想の時間を設けました。これまで研究してきましたが、このような活動で応用するのは初めてでした。目的は、畑からどのような植生や多様生物が生まれるのか、どのように土が豊かになっていくのかということを参加者の皆さんに考えてもらうためです」と語り、
クリエイティブに土の豊かさを考えることができる瞑想の時間は、参加者の想像力を掻き立て、思い思いの畑づくりに繋がると話しました。
YUTAKASA(豊かさ)は生物と人の多様性から生まれる

稲村先生は、土の豊かさ“YUTAKA”という言葉の意味を「自然、社会、経済の軸が整った状態」とし、「もったいないの概念として広げていきたい」と話し、
「生物の多様性と人の多様性の2つの価値観を含む、POLYCULTURAL CREATIVITY(ポリカルチャークリエイティビティ)というコンセプトを基に、混生や混作などの生物的な多様性(BIODIVERSITY)と、参加者の多様な背景やニーズ、世界観などの人の多様性(DIVERSITY OF PEOPLE)の価値観が調和することで、ポスト人間中心の思考ではなく、新たな価値を生み出すことができるのでは」と話しました。
川内港久見崎みらいゾーンの開発に向けた実践的な取り組みに

また、本プロジェクトをきっかけに、すでに参加者同士でクリエイティブな活動や交流が始まっていることに触れ、「薩摩川内市から世界へ発信し、市民発でイノベーションを起こし、市民の皆さんに興味を持ってもらうことが重要」と強調し、国際学会へ論文を発表する旨を伝えました。
終盤では、稲村先生が構想段階から参加されている、「川内港久見崎みらいゾーン」の開発事業(薩摩フューチャーコモンズ)の3つの方向性「循環素材ライブラリー機能」、「循環素材・バイオ素材を活用した先端研究機能」、「市民発イノベーションラボ機能」との関わり方について、以下のように話しました。
多様な生物や人が交わる「バイオマテリアルライブラリ」

まず、「循環素材ライブラリー機能」の面では、「今後SOIL STUDIOの活動が広まり、人々が畑に植物が増えることで、様々な生き物や竹炭をはじめとした生物多様性のバイオマテリアルライブラリ(生体材料の集まり)が充実し、今後の活用が期待できる」と話しました。
※薩摩川内市の循環経済における「循環素材ライブラリー機能」とは、「素材リサイクル」や「再利用」、「クローズドループ・リサイクル」を実装すること。産業廃棄物等の新たな使途をデザインし、資金調達のためのアイディアソン等のイベントを常態的かつ継続的に実施する。(クローズドループ・リサイクル:材料の持つ本来の性質を保ったまま同じ材料製品の原料とするリサイクル。)(アイディアソン:同じテーマについて皆で集中的にアイディアを出し合うことにより、新たな発想を創出しようとする取組。アイディアマラソンの略。)(参考:川内港久見崎みらいゾーン産業立地ビジョン)
土の豊かさは食だけでなく、生活の土台へ


続いて、「循環素材・バイオ素材を活用した先端研究機能」の面では、「あらゆる命を支え生活の基盤となる、食をはじめとした“YUTAKASA”(豊かさ)を生み出す素材として、食だけでなく、染め物など思いもよらない活用方法が期待でき、生活とデザインの重要な土台となるのでは」と話し期待を寄せました。
※薩摩川内市の循環経済における「循環素材・バイオ素材を活用した先端研究機能」とは、九州大学大学院芸術工学研究院を中心に、市民生活に直接関連する衣食住や廃棄物量の多い産業基盤分野について、生活とデザインを基軸とした研究・開発のこと。(参考:川内港久見崎みらいゾーン産業立地ビジョン)
SOIL STUDIOからはじまる市民発のイノベーション

最後に、「市民発イノベーションラボ機能」の面では、「生物だけでなく人の多様性を呼び込み、SOIL STUDIOで思い思いの畑をカタチにし、土を豊かにしていくという全体のプロセスが、市民発イノベーションへの一歩になるでは」と締めくくりました。
※薩摩川内市の循環経済における「循環素材・バイオ素材を活用した先端研究機能」とは、市民・地域企業・新興企業・国内外の研究機関等の各主体が有機的に連携しながら、各主体のニーズや技術、アイデアなどを出し合い、ビジネス化を模索する活動のこと。(参考:川内港久見崎みらいゾーン産業立地ビジョン)

報告③〈住〉竹建築プロジェクト「竹林面積日本一の鹿児島県で日本初の常設竹建築を実現したい」
3人目のプロジェクト発表者は、九州大学大学院芸術工学研究院助教の岩元真明先生。
建築家として建築設計やインテリアデザインなどの実務を踏まえながら日々建築について研究されています。
冒頭では、岩元先生が長年ベトナムの会社で竹建築に携わっていた経験から、「日本での竹建築の可能性を工学的・技術的に開発していきたい」というメッセージを伝え、今回の竹建築プロジェクトの目的である、「サーキュラーデザインを踏まえた竹建築の実装」に向け、取り組んできた約3年間の活動を報告しました。
建築基準法の壁を越え、実装できるように

まず、広大な竹林を持つ鹿児島・薩摩川内市が抱える課題「放置竹林」について、「豊かな資源として捉え、活用していくことでサーキュラーエコノミー実現に向けた鹿児島らしい取組になるのでは」と話し、長年ベトナムで竹建築に携わった経験と世界の実例を基に、「自然素材で温かみがある」などの竹建築ならではの良さや今後の活用に期待があることを述べられました。
一方、日本で竹建築が広まらない理由として「建築基準法の壁」を挙げ、材料の強度、接合部の強度、品質の確保、防腐・防虫処理など、耐久性や耐火などを研究する必要性を訴え、竹建築プロジェクトの目標は、「竹林面積日本一の鹿児島県で日本初の常設竹建築を実現!」。
株式会社リ・パブリックがプロデュースを行い、九州大学大学院の岩元先生や学生、関西学院大学の荒木美香先生、佐賀県でテント製造に取り組む山口産業株式会社と協働で活動されてきました。
現地に足を運んで竹建築の構想を膨らます


活動当初は、薩摩川内市の竹林を見学し、竹を活用した新しい建築を模索するワークショップを開催。学生たちが自由な発想で模型を制作したり、竹のプロフェッショナルや企業を訪ねてインスピレーションを受けたりするなど、竹建築実装に向けた構想を膨らませたと話す岩元先生。
プロトタイプ(試作)の第1弾となった舞台は、福岡市・那珂川河川敷。
「カヤック置き場的なパビリオンを造れないかと相談があり、国土交通省の令和4年度官民連携まちなか再生事業「那珂川みらい会議」と連携し、柱と梁、屋根があるシンプルな構造の仮設の竹建築物を目標に3Dグラフィックや、企業見学を行いながら設計を行いました」
仮設竹建築のメリットとデメリット

仮設の竹建築のメリットは、「竹は軽いので、持ち運びしやすく、使う人たちが自分たちで安全に組み立てられる可能性を感じました。また、他の材料で建てるより、成長スピードの速い竹を使うことで材料の無駄を減らすことができます」
一方、デメリットとしては、「竹は、1本1本が不揃いで太さが違う」などの材料としての扱いにくさを挙げました。しかし、「柱は4本の竹を、梁は2本の竹を束ねて使用し、束ねることで性能を平均化して強度を高めるなど、コンピューター解析しながら進めました」と話しました。

さらに、「竹に精通する企業を見学したり、日ごろから竹製品を扱うユーザーに意見を求めたりしながら、伝統的な方法をアレンジし、竹と竹の接合部分には「鉄」を使用しました」と岩元先生。
竹建築の今後の可能性について

最後に、今後の竹建築の可能性、「建築基準法の壁」を乗り越える実証実験の必要性について、「オフィスなどのインテリアとしてはすぐに実現可能である」とし、「畜舎や農業ハウスなどの生産施設における竹建築は、農村の景観を良くし需要があるのでは」と話しました。
また、この3年間の活動を振り返り、今後も実装を重ねていけば「グランピングやあずまやなどの宿泊リゾートや公共トイレや案内所などの小規模施設を実装できる可能性が見えてきた」と今後の期待を込めながら締めくくりました。

おわりに【取材後記】
以上、鹿児島県薩摩川内市で開催された「循環経済社会へ向けた、リビングラボプロジェクト活動報告会」のレポートでした。
ここまでご拝読いただき、いかがでしたでしょうか。
「サーキュラー」や「SDGs」と聞くと、どこか難しい話に聞こえるかもしれません。
しかし、自然豊かな地球を守るために、そしてこれからも人々が生活していくためには、「持続可能な暮らし」について一人一人が意識的に行動する必要があります。
日々の暮らしに関わることだからこそ、楽しさや遊び心も加えながら、資源を循環させることができる豊かな暮らしへ。
薩摩川内市では、サーキュラー都市に向け、市民、行政、研究機関、開発者、企業が協働し、「Satsuma Future Commons」のプロジェクトを進めています。
全国に先駆けたスピード感のある活動を今後もお見逃しなく。
| URL | |
|---|---|
| 屋号 | Satsuma Future Commons(薩摩フューチャーコモンズ) |