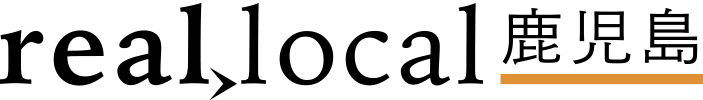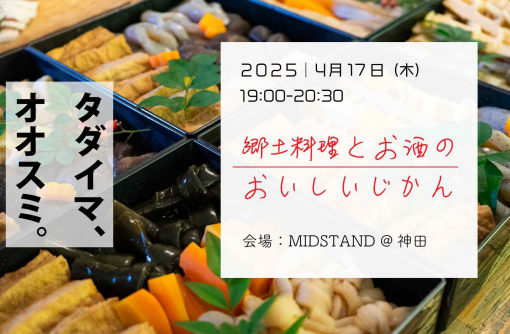【鹿児島県錦江町】それぞれの領域で小さく問い続け、誰もがたのしみ続けられる土壌をつくる / 特定非営利活動法人たがやす
錦江町の『特定非営利活動法人たがやす』(以下:たがやす)は、それぞれが実現したい未来の輪を少しずつ広げながら、誰もがたのしみ続けられる土壌をつくり、文化として繋がっていく世界を目指し、2022 年4月に設立されました。現在、鹿児島県内だけではなく鳥取県や東京都など様々な地域に理事がいる中、農福連携事業や認知症フレンドリー事業、教育事業に空き家事業と多様な事業を展開しています。今回、設立し3年を迎えるにあたり、福井県小浜市で研修を行ったとのことで、メンバー一人ひとりの過去・現在・未来を辿りながら「たがやす」の根幹に迫ってみようと思います。
「たがやす」の立ち上げ背景については
代表・山田(馬場)みなみさん
メンバー・天野雄一郎さん
それぞれのインタビュー記事をご参考ください。

誰もがたのしみ続けられる土壌をつくるために
“誰もがたのしみ続けられる土壌をつくる”
「たがやす」が目指すこの世界観は、メンバーを含む地域に暮らすすべての人々が、生きがいや居場所を見つけ、共に支え合いながら生きていくための基盤をつくることに他ならないといいます。
多様な背景を持つメンバー一人ひとりの専門領域で、それぞれが持つ課題意識を持ち寄れば、小さなことでも何かしらのアクションが起こせるかもしれない。できる範囲内で、その範囲を少し越えようとしながら、豊かな暮らしをつくっていけるかもしれない。
そんな想いで活動を続け「たがやす」は今に至ります。


「たがやす」の原点を旅する
2025年2月。
福井県小浜市にて、鹿児島県、鳥取県、東京都など、県内外に散らばっていたメンバーが一堂に会し、合宿が開催されました。
「事業が広がっていく一方で、資金面や組織のあり方、方向性など長期的な目線で話し合う機会を持てていなかったことから、一度立ち止まり対話を行う必要があると感じたことが今回の合宿の経緯です。“たがやす”の原点を旅する、振り返りのための時間です。」
そう語る代表の山田みなみさん。
合宿の目的は以下のとおりだったといいます。
①「たがやす」のロゴをデザインしたUMIHICOのお二人に会うこと
②農福連携(※1)の活動を通じて「たがやす」という言葉のインスピレーションを与えた平原礼奈(※2)氏のファシリテーションをメンバー全員で体感すること
③対話を通じた「たがやす」メンバーの相互理解
④対話を通じた「たがやす」の共通認識をつくること
(※1)農業と福祉の連携。障がい者が農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み。
(※2)編集者・手話通訳士。「ダイバーシティから生まれる価値」をテーマに企画立案からプロジェクト運営、ファシリテーション、コーディネートまで行う。人材教育の会社で障害者雇用促進、ユニバーサルデザインなどの研修企画・講師・書籍編集に携わった後に独立。現在、多様性×芸術文化・食・情報・人材開発・テクノロジーなど様々なプロジェクトに参画&推進中。



平原氏から「“たがやす”が“たがやす”であるために」という問いをもとにメンバー一人ひとりに対するインタビューが繰り広げられたといいます。
“正解なんてないし、答えが出なくてもいい。”
“その時に感じたことを、自分のペースで答えてもらえたら。”
そんな雰囲気だったからこそ、それぞれのあり方や抱えているもの、思い描くものなどを話せたのだとか。
インタビュー後は2つのグループに分かれて対話を深める時間に。暮らす場所が離れていても、共通する想いや気づかなかった一面など知ることで「たがやす」の原点に触れるという時間を過ごせたといいます。



錦江町と私を繋ぎとめてくれる存在
ここからはメンバー一人ひとりに合宿を踏まえた振り返りを聞いていこうと思います。
まずは3月末をもって「たがやす」を離れるメンバーの内田樹志さん、そして、錦江町外から関わっている大西千尋さんと田原麻里子さんの3名から。
「今年の春に“たがやす”から離れてしまうのですが、錦江町で暮らし続けますし、離れたからこそ、僕から相談したり逆に“たがやす”に貢献できる関わり方があるのではないかと改めて感じました。今後は文化を知る・体感する機会をつくっていきたいと思っているのですが、地域の皆さんの想いとギャップがあると思うんです。そのギャップを“たがやす”を通して、少しでも埋めていきながらカタチにしていけたら嬉しいです。」(内田さん)

現在、鳥取県へ引っ越し、育児を中心にした日々を過ごす大西千尋さん。離れながらも第二の故郷である錦江町に対する想いは変わらず、今の大西さんだからこそできる関わり方を模索している段階での合宿だったそうです。
「普段、錦江町にいないことや育児に追われてミーティングにもあまり参加できていなかったので合宿の前は不安が大きかったです。でも、いざ福井に行くと同じような志を持った仲間の存在だったり、家でも仕事場でもないサードプレイスのような居場所を再確認できたのが私にとって大きな収穫でした。今後は全国的に問題となっている事業承継をテーマにした仕事をしていくつもりなので、錦江町や他の地域に貢献できるように頑張っていきたいと思えました。」(大西さん)

鹿児島市からメンバーとして関わっている田原麻里子さん。同じ県内とはいえ、家庭や本業の関連もあり錦江町へ行く機会が少ない中でも、普段からメンバーの言葉やコミュニケーションには救われていることが多いのだとか。
「私も錦江町を離れてあまり事業に関われていないことに対する申し訳なさがありました。でも、ありがたいことにメンバーからはいつも“そのままでいいんだよ”“いるだけでいいんだよ”と優しい言葉をかけてくれるんです。”たがやす”が錦江町と私を繋ぎとめてくれているんだと強く感じた時間でもありました。私にしか、錦江町でしか、できないこともあると思うので、メンバーの助けをもらいながら、例えばですが、農業などにも取り組んでみたいと考えています。」(田原さん)

濃淡でありながら、対話をし続けることで見えてくる未来
続いては福井での過ごし方で見えてきたものについて話が盛り上がりました。
「たがやす」が設立されて2年目から加入した伊藤愛さん。途中で加入したからこその不安がありつつ、それが心の中にずっと残り続けていたと言います。だからこそ、今回の合宿でメンバーと過ごした時間は大きな収穫だったのだとか。
「平原さんが“この合宿で答えを見出さなくてもいいんだよ”という前提で対話を広げてくれたので気負いなく自分の想いを話せました。仕事のことを忘れて、みんなで同じ楽しい時間をゆるっと共有できたのも貴重でした。福井と鹿児島という遠い距離の中で行きと帰りの時間も含めて、少しずつ心の中で腑に落ちていく何かがあって。実際それをもとにどうアクションしていくかはわからないのですが、ふわっとしていても“それでいいんだ”と強く感じた時間でした。」(伊藤さん)

錦江町内で建築士として働きながら「たがやす」に設立時から関わっている鍋田成宏さん。他のメンバーと同じく本業をこなしながらの関わりであるゆえの不安があったそうです。でも、今回の合宿を通して「それでもいい」と思えるようになったといいます。
「合宿はとても幸せな気分になれた時間でした。“リアルな場”だったことが大きかったです。僕も含めてメンバー全員に言えることですが、本業がそれぞれあるからこそ、関わり方に不安を抱えていた人ばかりだと思います。でも、リアルな場で対話をして共通認識を持てたからこそ、濃淡であっていい、この濃淡をみんなと対話しながらいい方向に持っていけばいいのではないかと思えました。みんながいて、いろんなフィールドの人や考え方に触れるきっかけを与えてもらえているので、僕自身の仕事や暮らし方がこの3年でいい方向になったと実感できました。」(鍋田さん)

2025年の春から転職のため、県外へ引っ越すことになった山中陽さん。そのような状況での参加だったからこそ、改めて山中さんにとっての「たがやす」の存在意義を改めて問い直すきっかけになったそうです。
「合宿ではみんなが仕事を忘れて “たがやす”の時間を幸せそうに過ごしていたのが印象的でした。僕は今年の春から県外へ引っ越すこともあり、あの時間を通して“たがやす”の存在の大きさを再認識できたと思います。県外からも数ヶ月に一回は通おうかなと思っていますし、もしかしたらまた錦江町に戻ってくる未来もあるかもしれません。どんなカタチであれ、錦江町との関わりを強めた未来を想像できたので今後も楽しみだなと感じました。」(山中さん)

それぞれの領域で問い続け、手の届く世界をより良くする
東京を拠点にしながら「地域と食のしごと」を推進する事業を中心に、故郷・鹿児島を含む様々な地方に関わりを持つ福留千晴さん。さらに、空き家事業「THEDDO./スッド」などを通し、錦江町や大隅半島との関わりも今後も続けていきたいとさらに思えた時間だったと話します。
「最近、空き家事業を通じて息子が将来の夢を“大工になりたい”と語ったんです。それって、メンバーや“たがやす”の事業が息子の人生に影響を与え始めているんじゃないかと思いました。地域課題の解決と耳にするとまちや地域全体をついイメージしがちですが、目の前や隣にいる誰かといる世界をほんの少し居心地よくするだけでもいいかもしれない。だからこそメンバーにとっての“たがやす”の定義や関わり方はそれぞれでいいし、時が経つにつれて変化してもいいのではないか。そう感じました。」(福留さん)

「たがやす」設立のきっかけの声を上げ、現在は大隅半島を中心に農福連携を軸とした事業に携わっている天野雄一郎さん。合宿や振り返りを通し、メンバーの生の声を聴いたことで「たがやす」の存在意義を今まで以上に感じるようになったといいます。
「“このままでいい”と思える場所って中々ないと思うんです。元々“たがやす”にいることが100%幸せな状態で合宿に臨んだので、この合宿はさらにプラスしかありませんでした。平原さんの“たがやす”が“たがやす”であるためにという問いに対し、みんなで対話をした時間、一緒に楽しく過ごした時間が僕らをさらに勇気づけてくれたと思います。何よりメンバーが集まれたことだけで成功なんです。“たがやす”があるから、またみんなで会えたんですから。」(天野さん)

最後に代表の山田みなみさん。今回初めてメンバーでゆっくり過ごす・じっくり対話する時間を共有することで「たがやす」の原点を思い出してもらえたのが一番の喜びだったと話します。
「結局は“たがやす”は問い続ける組織なのではないかということを改めて感じました。それは自分自身や家族、地域、事業だったり、それぞれだと思います。時には辛いこともあると思います。でも、メンバー一人ひとりが問い続けて、各々の活動領域で落とし込んでいきカタチにしていくのが“たがやす”らしいなと思えましたし、今回の合宿は今後も問い続ける筋力をつける時間になったと思います。」(山田さん)

今回の取材を通して感じたのは
「たがやす」のメンバーは、
どんなに離れていても
どんな状況でも
「たがやす」に属していなくても
きっと何かしらの土壌を耕し続けていくんだということ。
耕せば土は柔らかくなり、
違った要素と溶け込みやすくなります。
それが一つのものとなり繋がっていくには時間がかかるかもしれません。でも、今回根本となる原点に立ち戻ったからこそ、それぞれのできることが見えてきたと思います。
その感覚を忘れずに一つひとつ着実に前へ進むことで「たがやす」が思い描く未来に到達できるのではないかと強く感じました。

| 屋号 | 特定非営利活動法人たがやす |
|---|---|
| URL | |
| 備考 | ●公式インスタグラム https://www.instagram.com/tagayasu2022/ ●大隅半島ノウフクコンソーシアム(ONC) https://www.instagram.com/onc_2021/ ●THEDDO.(スッド) ●real local 鹿児島で取材したメンバー 山田(馬場)みなみさん https://www.reallocal.jp/102403 天野雄一郎さん https://www.reallocal.jp/108641 内田樹志さん |