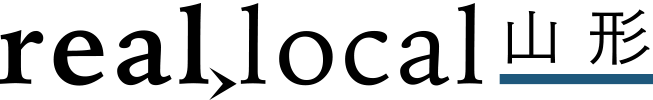中山ダイスケ × 宮本武典 × 三瀬夏之介 【後編】/ ぼくらのアートフェス最終回

日本の辺境としてではなく
リクエイティブの現場として
三瀬:今回展示した作家に、新海竹太郎という彫刻家がいます。明治元年生まれの人で今年生誕150周年を迎えましたが、企画をやる美術館はありませんでした。同い年の横山大観の展覧会が東京国立美術館で華々しく催されたのとは対照的です。
新海竹太郎は「ロダンになり損ねた男」と言われます。つまり、ロダンという彫刻の「中心」から見るとあまり評価されてこなかったわけです。でもぼくから見ると、洋と和の折衷がこの山形の地ですでに完成していたという評価の仕方もできるし、彼がそれを狙ってやっていたことは間違いない。その根本にあるのは、この山形の地で自生的に生まれた表現というものが存在していたということでしょう。

中心からの目線でこちらを捉えられてしまうと、向こうが疲れたりネタがなくなったりしたときに拾いあげられて消費されるだけのモノになってしまうけれど、そうではない価値としての新海をこのビエンナーレできちんと山形からレスポンスしておかなきゃいけないという想いがありました。山形は中心を補完するものとしての辺境ではないし、そしてもはや中心も辺境もないということ。そのことをしっかりと伝えたいし、それはみんな実感としてわかってると思うんですね。
宮本:「辺境」というのはぼくも使わないようにしたいと思っている言葉です。言ってしまった瞬間に、中央に対してここは端っこの世界だということになってしまう。でもその言葉を自分のなかで無理に封印しようと意識すると、すごくアートとして不自由になる気もするんです。
また、逆にここが中心だと言ってしまうと、今度は地域現実主義じゃないか、要するに自分たちに近しい仲間内で盛り上がっているだけじゃないのか?という批判も聞こえてくるわけです。

どうやって「辺境」でもなく「内輪受け」でもない場所を作っていくかっていうのは、芸術祭をやる地方都市のそれぞれがただ素朴にやっているだけではなかなかクリアできない課題であり、また、それぞれが回答していかなければいけないことだと感じます。
中山:まだまだ、やることがいっぱいあるところが中心になってく時代だとぼくは思っています。この東北芸術工科大学の入学式では「クリエイティブの現場へようこそ」っていうメッセージを新入生たちに伝えていますけど、本当にぼくらのいるこの場所が一番のクリエイティブの現場なんです。
なにもないことはもしかしたらこれから生まれることだし、なにかが今たりないことはもしかしたら後になってできることだし。もうどうしようってくらい飽和状態になっている東京の人たちが「地方って面白い」って言っていますけど、まだ描かれてない白いキャンバスは今はもう地方にしかなくて、それを求めていろんなクリエイションが地方に出ていっている、という状況だと思うんですね。
もちろん、お金がいっぱいあるところが中心だという考え方もあるのかもしれないし、人がたくさん集まっているところが中心だという考え方もあるのかもしれない。けれど、試すべきことが試せる土壌がある、そういうところこそが中心だと思うんですよね。

ファッション世界一の学校はベルギーの田舎のまちアントワープにあるし、いま世界的映像プロダクションが集まっているのは南アフリカだったりする。なにもないようなどこかの場所でひとつのものが作り上げられるというところからすべてはじまっているわけです。かつては東京もニューヨークもそうやって生まれたはずで、その黎明期にあるような場所が中心ということなんだと思います。
やがては山形が中心だと言われるようになり、さらには「山形は色々やりすぎちゃって、もう違うよね」なんてさえ言われるような将来だってありうると思います。山形ビエンナーレはそういうことのひとつだと思うし、その意味でも、今ここにこの大学があってよかったってぼくは思っています。
シンプルに、ストレートに、
素になって感動できる展覧会
三瀬:宮本さんは今回の山形ビエンナーレが終わっていかがでしたか。
宮本:それはもう、感動しました。単純に、めちゃめちゃたくさんの人が来てくれましたし。
またこれは言語化しづらいのですが、アートのことを考えているキュレーターとしてのパブリックな自分と、家族を想いながら山形に生きているプライベートな自分とはふつうは分かれていますけど、それが限りなく一緒になったような感じがあったんです。
胸の内に抱えている想いや、直面していることに対して強く訴えかけてきた表現や言葉に対してものすごくストレートにリアクションをしている自分がいました。それはアートとしてのかっこよさとか手法とかに感激するのとはまったく違う種類のものです。生々しく生きている自分の感情や肉体に対してすごく直接的にノックしてくる表現や瞬間をすごいシンプルに受け取ってしまったというか…。

中山:ビエンナーレのおかげで素になったんでしょうね。ぼくらアートのプロにとっては珍しいことですよね。美術館で素晴らしい絵を見ても素直に感動できないのは、その歴史やアーティストのことを知ってしまっているからで。横ではおばちゃんがブワーッて泣いていて、自分もそうなりたいのにやっぱりそうはなれない。でも、宮本さんは今回そうなれたわけです。自分がプロデュースしている展覧会のなかで。
宮本:そうですね。
中山:三瀬さんはどうでした?
三瀬:ずっと感動しっぱなしでした(笑)。
でもこの感動は、パブリックなところに所属しているキュレーターだったらできなかったことじゃないか。かなりパーソナルな価値観を共有できている仲間たちからスタートしたからできたのかもって気がしますね。
宮本:Twitterでビエンナーレについて語られていたなかに「文脈ってことにみんなが傷ついている」という言葉がありました。現代美術には文脈があってそれをどう読むかによっていい悪いが決まるけど、自分はこれが良いしこれに感動しているのに、文脈にフィットしてないと「それ違うじゃん」みたいなことになる、と。
その意味では「文脈」がデザインやアートの可能性を狭めているとも言える。それを突破するには、シンプルに自分がどう感じ、どう心を動かされたかを追求することしかない。そういうシーンを作りたいと思ってやってきて、このビエンナーレでそういう奇跡的な瞬間を生み出すことができたんじゃないかと思いました。
三瀬:「文脈」という言葉をもっと幅広く開発していく、あるいは別の言葉で名付け直さなくちゃいけない、とも感じます。文脈があるから愛着を感じるってこともあるわけだし。
「100ものがたり」をキュレーションしてぼくが感じた絶望と可能性は、あるひとりの作家の個展ってもうムリじゃないかってことでした。ある個人が自分の想いとか観測のなかでモノを作って、それが個展となって価値を生んでいく時代はもう難しい。まさにこの自分がひとりの作り手であるにもかかわらずそのように思ってしまいました。「文脈」ではないけれど、モノを星座のように並べてみることによってほんの一瞬キラリと輝くような価値をもつ、みたいなことじゃないと、芸術祭って成立しないんじゃないかなって。
中山:関係性によってそこにあるすべてが際立って面白く見えてくるというのがグループショーの醍醐味。それを作るのが本当のキュレーターの仕事なんでしょうね。今回のビエンナーレでも、これがここに置かれているからこれはここにある、みたいなことで成立するように展示が作られていたと思うんです。
キャプションを読ませて頭で作品を理解させるのではなく、「なんでこのタイトルで、これが置かれているの?」って感じでちょっとわかんなくさせちゃうくらいの方がアートショーのやり方としては面白いし、わかんないけど面白かった展覧会になると思うんですよね。

宮本:ビエンナーレ最終週、川村亘平斎さんによる影絵のパフォーマンスは震災がテーマなのにお笑いコントみたいなものになっていたから、見ながらすごくハラハラしていたんです。でも、演者の川村さんは「これは誰かを亡くして悲しんでいる人のためではなく、あの世に逝ってしまった死者たちを楽しませる喜劇としてやるのであって、それが本当の慰めになる」と言っていました。震災や死にもいろんな表現の仕方があって良いことを教えられた気がしました。
アートの持つ力とか役割とかそれがコミットできるいろんな可能性とかも、「辺境」という言葉や「文脈」というものから一度離れて、自分なりに崩したり作ったりして良いんだよってなった瞬間に、もっと自由に楽しめる。そのサンプルになるようなものを、山形ビエンナーレのなかで示せたんじゃないかなって気がしています。
中山:本当に面白いビエンナーレになりましたよね。いい意味で混乱させられたし、ハテナと感じるところも、ニヤリとするところもいっぱいあったし、とても良いショーを見た感じがしました。
宮本:逆にここにいる学生たちは「文脈」とか「辺境」っていうこともまだわからないまま、これをスタンダードとして見て、これがアートだって思ってるわけで、それもまた面白いですよね。
中山:幼少期に複雑な味覚を経験した子どもみたいだね。いいことです。アートのいろんな味わいを味わうことのできる人に成長してくれるんじゃないかな。
三瀬:味覚って文脈と関係ないですからね。どんなに説き伏せても、美味しいものは美味しいし、まずいものはまずい。現代アートの怖さってまさにそういうのと同じで、「あの作品経験しちゃったらもう元の素朴だった世界には後戻りできない」ってこと。世界がどんどん拡張していくことの怖さと自由さを獲得していくことなんですよね。

中山:せっかくだから学生には山形ビエンナーレの全部を見てもらいたかったけど、なかなかそうもいかなかったですね。週末限定開催っていうのは短くてぎゅっと詰まった感じにはなったけど、そのぶんイベントスケジュールも重なりましたし。その点は少し改善の余地があるのかもしれません。
宮本:今回のビエンナーレには来てくださったのは、6万5千人近くもの方々。これは過去最高の来場者数です。全国各地から来てくれて「すごく勇気づけられた」って声が本当に多くて、「自分たちもこの方向でやっていていいんだ」みたいな感じで受け取ってくれた人がすごく多かったみたいです。ぼくらとしてもすごく嬉しいことでした。
中山:この「ぼくらのアートフェス」について、みんなから提出してもらったレポート読むと、自分もアートフェスを作ってみたいとか、母校で作りたいとかっていう声がいっぱいありました。ぜひそういうみんなの参考になるビエンナーレであれたらいいですね。
(2018.10.11)
中山ダイスケ(Daisuke Nakayama)/1968年香川県生まれ。現代美術家、アートディレクター、(株)daicon代表取締役。共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002年まで5年間、ニューヨークをベースに活動。ファッションショーの演出や舞台美術、店舗などのアートディレクションなど美術以外の活動も幅広い。山形県産果汁100%のジュース「山形代表」シリーズのデザインや広告、スポーツ団体等との連携プロジェクトなど「地域のデザイン」活動も活発に展開している。2018年4月、東北芸術工科大学学長に就任。
宮本武典(Takenori Miyamoto)/1974年奈良県奈良市生まれ。東北芸術工科大学美術館大学センター教授・主任学芸員。展覧会やアートフェスのキュレーションの他、地域振興や社会貢献のためのCSRや教育プログラム、出版企画をプロデュースしている。とんがりビル「KUGURU」キュレーター、東根市公益文化施設「まなびあテラス」芸術監督。akaoniとの企画・編集ユニット「kanabou」としても活動中。
三瀬夏之介(Natsunosuke Mise)/1973年奈良県生まれ。東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科長、芸術学部長。京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。修士。既存の日本画の枠にとらわれない、多様なモチーフや素材、時にはコラージュを施した作品の圧倒的な表現力が高い評価を得ている。トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞(2002)、五島記念文化財団 美術新人賞(2006)、第16回VOCA賞(2009)ほか、受賞多数。2013年 個展 N.E.blood 21 三瀬夏之介展 リアス・アーク美術館、日本の絵 三瀬夏之介展 平塚市美術館、2014年 特別展 三瀬夏之介-雨土(あめつち)の記展 浜松市秋野不矩美術館その他、シンポジウムやアーティストインレジデンスに参加するなど、精力的に活動の幅を広げている。