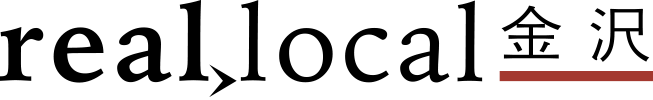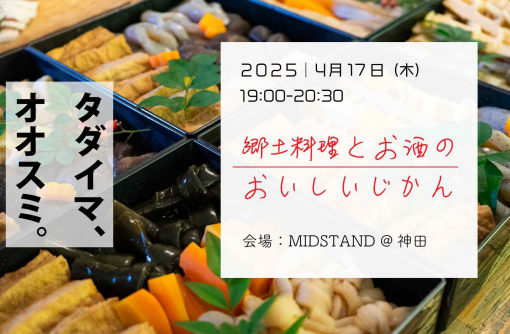「世界とは、没入して身体で認識するもの」teamLab代表・猪子寿之氏インタビュー/『永遠の海に浮かぶ無常の花』開催中!
※終了しました。
現在、金沢21世紀美術館で開催中の『チームラボ 永遠の海に浮かぶ無常の花 』(〜9月1日まで)に乗じて、チームラボ代表・猪子寿之氏にインタビューを敢行!初のお披露目となる実験的な作品に込めた想いから、「自分の街の魚が一番美味いと思ってる問題(!)」に至るまで、猪子氏が考え続ける「世界と認知の仕方」とは。

−まずは夏休み期間の開催ということで、、子ども時代にアートに触れるということをどうお考えですか?

「僕自身、子どもの頃からアートやサイエンスが好きでした。サイエンスによって、人は世界をより認識できるようになった。対して、アートは“世界の見え方”を変えてきたのではないかと思っています。そのことにずっと興味があって」

「幼少期のアート体験って、子どもにとって大きな“心の余裕”につながるのではないかと思っていて。
人と世界の関係だったり、人が世界を認知する仕方自体、実に多様に移り変わって行くものだということは、ある種の歴史的事実だと僕は思っています。けれど、子どもの頃って、大人の、それも個人的な世界の認識の仕方を一方的に、多々押し付けられるわけです。でも、それって一地域の流行り風邪か、風土病みたいなものだと思うんですよね。

その時に、その人が言ってることが真理ではないことを知っているかどうか、もしくは『この人は、世界の長い歴史の中で移ろいできた多様性というものを知らないだけなんだ』って思えるか。こういうことが子どもにとって大きな心の余裕になってくるように思うんです」
−−今回の展示も子ども達に見て欲しいという意識のもとで制作されていますか?
僕は、あまり「子ども」と「大人」を切り分けないようにしてます。違いは身体的特徴でしかないと思っているくらい。ただ、子どもに限らず、人間っていうのは常に価値観を広げていったほうがいいし、変えていった方がいいとは思っています。

「ちなみに、今回展示している作品だと、『フラワーズ ボミング』は直接的に作品に参加して、それが世界そのものを変えるんだっていう体験をしてもらいたいと思ってつくっています。花を赤で描いたら、空間の光にも赤が反映される。自分のクリエーションが世界を覆うとか、世界をちょっと変えるというかね。そういう感覚を子ども達にも感じてもらいたいと思って、一つ置いたというのはあります」
−−チームラボの作品は常にインタラクティブです。アートを“鑑賞”するのではなく“体験”する意義とは。

「本来、世界というのは自分の体で没入して認識していくものだと思うんです。例えば、パリの街を写真やテレビで見ただけで“知っている”とは言わないですよね。パリの街中を自分で歩き回って初めて知れるというか。
人は身体を動かしながら世界そのものを認識していて、決して頭だけで認知しているんじゃないと思うんです。自分が歩けば草は揺れるし、小動物たちは静かに逃げているかもしれない。世界ってそういうもんだと思う」

−−ところが、一般的に美術館というのは、ホワイトキューブに収められて、「作品に触っちゃいけません」「喋っちゃいけません」ですよね。
「なんなら『動くな』も(笑)。それって、“頭だけで認識しなさい”って言ってるようなものですよね。でも僕はむしろ頭だけで物事を認識してはいけないと思っていて。
日本美術だって、もともとは建築という“空間”とセットだったわけで。襖絵は動くし、屏風だって可動的なものです」

「それが、たまたま西洋でパースペクティブが発明されて以降、レンズで物事を切り取ることが多くなった。そういうものが身体を固定してしまったんです。そして僕らは、テレビやスマホといった“レンズで切り取った世界”をあまりにも見過ぎてしまっている。
だから僕らの作品では、自分の“意思ある身体”で歩き回りながら、世界そのものを認識してもらえるようなものにしたいと思っています」
ーー実験的な作品の『光群落』。シンクロして光る蛍みたいで、何だか愛らしく見えました。

「“群落”とは、生態学で植物が相互作用しあって生息している一つの群のことを指します。植物はそれぞれは一つの個体ですけれど、全体として互いに関与しあっている。今回の作品も、一つ一つの球は個別のプログラムで動いているわけですけど、カーブを曲がったりスピードを落としたり相互に関係し合っています。その中に入っていく、という体験を作ってみたかったんです」
ーー今回の作品を「金沢」で公開するということについて。
「金沢は歴史のある街です。大都市はあまりに分裂して連続性を失っているけれど、この街には比較的連続性が残っている印象があります。
僕らはずっと、“長い時間の中で連続していること”、“おびただしい連鎖の中にあること”をテーマとしてきているので、今回金沢21世紀美術館の、さらには市民ギャラリーというパブリックな場で展示させていただけたことには、何か時代の要請のようなものを感じています」

−−金沢は随分と久しぶりだとうかがっています。ぜひ、美味しい魚を召し上がっていってください。
「この『自分の街の魚が一番美味しい問題』は、情報の非対称性の典型的な例ですね(笑)。全ての地方の人が“自分の地域の魚が世界で一番美味しい”と言ってる。この状況がなぜ起こるかというと、例えば…初めて徳島に行ったとして、街のことをよく知らないから適当な店に入って魚を食べる。それが自分の街だと、一番美味しい魚を食べさせてくれる店を知ってるわけです。人間っていうのはいかに情報を非対称に受け取っているかという象徴的例ですね」

ーー今度は間違いなく魚が美味しい店お伝えするので(懲りない)、ぜひまた金沢いらしてください。ありがとうございました!