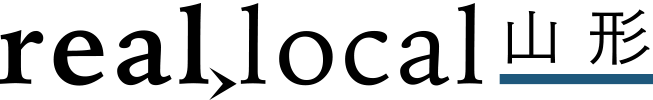ブラジル音楽と山形国際ドキュメンタリー映画祭
今年は2年に一度の山形国際ドキュメンタリー映画祭(以下YIDFF)の年だ。山形では唯一の、本当に「国際的」なイベントである。ドキュメンタリー映画には、音楽や音楽家を取り上げたものも多く、YIDFFにもその範疇の作品が数多くある。個人的にはその中でラテン・アメリカの音楽を題材とした作品にどうしても目が向いてしまう。
YIDFFのアーカイブを振り返ると、ラテン・アメリカの音楽を題材とした作品は、1995年(第4回)の「カルメン・ミランダ:バナナが商売」、2003年(第8回特別招待作品)の「モロ・ノ・ブラジル」、2005年(第9回特別招待作品)の「ミュージック・クバーナ」、2007年(第10回)の「12タンゴ ブエノスアイレスへの往復切符」、そして2015年(第14回)の「ラスト・タンゴ」などがある。この中でブラジル音楽ファンとして最も印象深いのは、ミカ・カウリスマキ監督の「モロ・ノ・ブラジル」である。
「モロ・ノ・ブラジル」は英語で言えば「Live in Brasil」、日本語では「ブラジルに生きる」という意味だ。監督はフィンランドの巨匠アキ・カウリスマキの兄、ミカ・カウリスマキ。少なくとも2003年のYIDFFで来県した当時、彼はリオ・デ・ジャネイロでライブ・ハウスを経営していた(現在は閉店したらしい)。
本作はブラジル音楽に造詣が深い彼が、サンバのルーツを求めて広大なブラジルの国土を4000キロ旅し、土地土地に根付いている音楽を巡るロード・ムービーである。多人種による移民国家であるブラジルは人種の坩堝であり、人種的に混じり合うことはブラジルのアイデンティティーでもある。従って必然的に音楽的にも多種多様なルーツを持つ音楽がミックスされて、その土地独自の音楽が形成された。伝統を維持しながらも、さらに新しい音楽とのミクスチャーを貪欲に求めるのがブラジルの音楽である。つまり人種あるいは国境を超えた横の混交と、現在と過去という縦の混交が常に繰り返されて、ブラジルの音楽が形成されているのだ。
また音楽との関わり方が、日本人の感覚とは大きくかけ離れている。ブラジルでは音楽は極めて生活に密着した存在で、市井の人々にしても音楽は生活のすぐそばにあり、日常と切り離すことができない。つまり「ブラジルに生きる」ことは、「音楽と生きる」ことでもある。ちなみにこの作品に出演している元路上生活者であったセウ・ジョルジは、今やブラジルを代表するシンガー・ソング・ライターであり、俳優としても本作の他フェルナンド・メイレレス監督の「シティ・オブ・ゴッド」や、ウェス・アンダーソン監督の「ライフ・アクアティック」などに出演をしている。
ミカはその後、ブラジル音楽の一種「ショーロ」に関するドキュメンタリー、「The Sound of Rio: Brasileirinho」を発表した。この映画には、山形でパンデイロ(タンバリンに似たブラジルの打楽器)のワークショップを二度行ったマルコス・スザーノも登場するし、この4月に山形で日本初となる公演を行ったばかりのブラジル音楽界の至宝ギンガも登場する。本作では音楽だけでは生活できなかった彼が、歯科医を副業として生計を立てていたエピソードなども紹介されている。

音楽に関するドキュメンタリーによって、音だけを聴いていたのでは決して知る由も無い、音楽の背景にあるもの、アーティストの置かれた環境や状況、ひいては人生を垣間見ることになる。無論それを見たからといって、音楽自体が変わるわけでは無いのだが、音楽ファンにはそれが堪らないのだ。
そして今回のYIDFFでは、昨年亡くなったブラジルを代表する映画監督ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督の遺作で、日本未公開の「トム・ジョビンの光」が、追悼上映として上映されることになった。ボサ・ノヴァの創造主であり、20世紀を代表する偉大な作曲家、故アントニオ・カルロス・ジョビンの生涯を、彼に深く関わった3人の女性のモノローグで綴る作品だという。ブラジル音楽ファンにとっても、ブラジル映画のファンにとっても見逃す事のできない作品である。
The Sound of Rio: Brasileirinho予告編