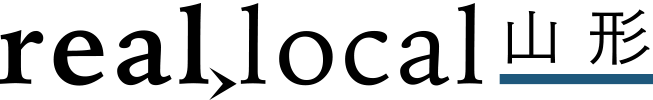山形ドキュメンタリー道場(1)/映像制作者たちの4日間 後編
前編では、山形ドキュメンタリー道場(以下、山形道場)の4週間のアーチスト・イン・レジデンス(AIR)中の4日間で開催されたワークショップで、「被写体といかにして関係性を構築するか」が論点となった発表とディスカッションのようすを伝えました。ワークショップでは、制作の原点にある作り手の体験や制作者のジレンマが、表現のスタイルや作家性と深く結びついていることにも、しばしば気付かされました。状況やテーマは異なりながらも、何か大事なものが共有されていくようすを目にしていたように思います。
引き続き、その対話の内容を紹介します。
「個人的体験と表現」
「別の文化に入り込んだ人たちやその子どもたちがどんなふうにアイデンティティをつくり上げていくのかに興味がある」と話したのは、大阪に生まれ韓国籍をもつ在日コリアン3世の梁貴恵(ヤン・キヘ)さん。

ロンドン大学クイーンメアリーでドキュメンタリーを学び、自身の体験とも重なる「移民」や「同化」をテーマとして映像を制作しています。「共産主義者のユートビア」とも言われるスペインのマリナレダで『UTOPIA』を制作した際に出会った少年が魅力的だったことから、子どもたちを撮ることにも興味が湧いたと梁さん。
次回作では移住者が感じる文化的ギャップなどをテーマに作品をつくりたいと構想を話すと、講師のタン・ピンピンさんは、「あなたのなかにある具体的な感覚を自分のものにできるように、もっと引き出してみてはどうか」とエールを送りました。

タンさんの言う「具体的な感覚」とは、ドキュメンタリー表現の根幹を成すものではないかと思います。また、作家が体験した感覚がどのように表現されるかによって、観客の体験は異なるものになります。
タンさんは、台湾の侯孝賢監督の映画『悲情城市』を観て、当時映画では聞くことのなかった福建語での会話に衝撃を受けた体験から、母国の人びとの言葉や音を探して記録したいと『シンガポール・ガガ』の制作に取り組むことになったと語ります。編集時には、約60時間分の膨大な撮影データを前に途方に暮れましたが、「撮りためた映像のなかでも、居場所がない人たちにフォーカスしてまとめよう」と思い立ったそうです。
政治的亡命者をインタビューして制作した2013年の作品『シンガポールへ、愛をこめて』は、政府により上映禁止の決定が下されました。しかしマレーシアのジョホールバルで開催された映画祭での上映が決まり、上映当日には約360人ものシンガポール人が貸切バスで作品を観にやって来たそうです。それを見て、「この人たちの物語もまだ語られていないのだと感じた」とタンさん。映画を通して、具体的な個人が語り出す場をつくろうと挑む姿勢が、そこにはありました。
ワラ―ラック・ヒランセータワット(サリー)さんは、編集者のドゥアンポン・パカヴィロジクル(ビー)さんとともに今回の山形道場にAIRで参加しました。

「精神的に辛くなり撮影ができなくなった時期もあった」とサリーさんが語った制作中の作品『Audacious Dreams of Kith and Kin(身内にまつわる大胆な夢)』(仮題)では、自身の親族間で持ち上がった先祖の墓をめぐる論争を追いながら、軍事政権によって分断されたタイ社会を描写し、宗教間・世代間ギャップをどのように民主的に乗り越えるかがテーマとして意図されています。
登場人物が多く、ストーリーラインが錯綜しており、質疑では映像からそれぞれの要素を理解する難しさが指摘されましたが、講師のアヴィ・モグラビさんは「家族や親族間のやりとりにはダイナミズムがある。しかし一人ひとりのキャラクターを判別しやすくする必要はあるだろう」とコメント。政治的な複雑さや深刻さをたやすく消し去ってしまわずに、どのような視点で選択をして観客に届けるか。また、映像と音との関係性のなかに、映画の重要な表現と体験があることを確認するディスカッションでした。
その音に対する感覚を体感し、再発見した時間が、最終日のみ講師として参加したサウンドデザイナーの森永泰弘さんのプレゼンテーションでした。森永さんは、主に東南アジアをフィールドに音のリサーチを行ったり、現地のアーティストとの協働による作品づくりに取り組んでいます。

プロジェクト映像の紹介後には、実際に全員で外に出て、どんな音が聞こえてくるか「聴く」行為を体験してみることに。
サリーさんは「上から下まで意識して聴くと、これまでとはまるで別次元にいるかのよう。隣から聞こえていると思っていた音が実は上のほうから聞こえてきたり、驚きの体験だった」とコメント。聞こえた音を具体的に尋ねられたビーさんは、「葉が揺れる音や、鳥の鳴き声、それから私の呼吸の音も」と一つひとつ挙げると、森永さんは「それらすべてが重要なリスト。体験には様々な音が関わっていて、音というのは体験を充実させるためにとても大事なものです」と語りかけました。

「制作者のジレンマ」
「私の作品は自省的なものになっており、自分が映画をつくるなかで体験するジレンマや迷い、躊躇というものを描くことを大事にしてきた」と話したのは、講師として参加したアヴィ・モグラビさんです。

モグラビさんは、フィクションの技術を用いながら中東の政治状況をテーマにドキュメンタリーを制作しているイスラエルの映画作家です。自身3本目の作品『私はいかにして恐怖を乗り越えて、アリク・シャロンを愛することを学んだか』では、イスラエルの政治家であるアリエル・シャロンへの接近を試みる自らをユーモラスに撮影しています。
「1982年のレバノン戦争でシャロンは国防相としてイスラエル軍の指揮をとり、一方で私はレバノン戦争への従軍を拒否した罪で、のちに刑務所に入れられました。そのことから、私は彼の映画がつくりたいと思っていたんです」。そうしてジャーナリストを装いながらシャロンに接近し、ある種の親交を深めて撮影を進めます。しかしある時点で、自分が当初に撮りたいと思った映像が撮れていないと気付いたモグラビさん。「これはシャロンについてではなく、映画作家のジレンマについての映画なのでは」という結論に至ったと話します。
モグラビさんの作品には、しばしばモグラビさん自身が登場します。時には活動家としてイスラエル兵に激昂し、時には何役もを演じ分けて笑いを誘いますが、相対する現実のあまりの信じがたさに、現実のほうがフィクションであるかのように映像は迫ります。「現実というのは単純なものではありません。ですから私は複雑性をなるべく引き入れながら作品をつくってきたつもりです」。政治運動に自ら参加し、問いを重ねるなかで生まれるモグラビさんの表現を、実際に観て肌で感じた時間でした。
一方で、モグラビさん同様に活動家でありドキュメンタリー作家でもある黄恵偵(ホァン・フイチェン)さんは、「私が伝えたいものは、怒りと悲しみ」だと発表のなかで力強く語りました。前作『日常対話』では、ひとり親である母親との対話や母をとりまく人びとへのインタビューを通して自らの思いと向き合う作品を制作。現在制作中の作品では、やはり元夫などの近しい人びとを撮影しながら、自身がかかわった台湾の原住民族の居住権をめぐる抵抗運動を追いかけています。しかし、運動にかかわった10年間に、ともに活動した夫との離婚や、人びとの分裂、歴史的には為政者として先住民を支配する側にあった漢民族という自身の立場などに煩悶してきました。
モグラビさんは、「活動家がよかれと思ってやることが思いがけない状況を生み出すのは、活動家と先住民とでそれぞれ違った考えを持っているから。ある程度の成果が出た段階で活動家はそこから去るべき」と自らの経験にも照らすようにコメント。編集者の雷震郷(レイ・ヂェンチン)さんとプロデューサーのステファノ・チェンティニさんとともに参加し、今作ではどのような表現のスタイルをとるべきか決めかねていた黄さんですが、AIR滞在を終える頃、「まず私自身でよく考えてみた結果、やはり自分にもカメラを向けてみようと決めた」と語りました。

制作者が被写体や地域にかかわるなかで抱えるジレンマは、モグラビさんや黄さんと同様に、福島で撮影する作家たちにおいても共通するテーマでした。ただ一方で、地域を映し、地域とともに希望を見出そうとし続ける姿がそこにはあります。
羽田澄子監督に師事して独立した山田徹さんは、2011年の福島第一原子力発電所の事故直後に福島県相馬郡の新地町に入って撮影した前作『新地町の漁師たち』に続き、現在は国道を東京から福島へと北上するなかで出会う人びとにカメラを向けています。

「なぜ縁のない福島の人びとを撮ろうと思ったのか?」との質問に、山田さんは「震災や原発事故による現地の人たちの喪失感は、地縁のない自分が聞いていても心が痛むものだった。何を通じて人と人は痛みを共有できるのか、つながることができるのかを考えたいと思った」と回答。前作では撮影に必死で何を伝えたいのかわからなくなる時期もあったことから、「新作では自分の思いや葛藤も、作品のなかで表現したい」と語ります。
同じく福島で撮影を続けてきた野村知一さんは、2011年から福島県内の異なる地域で農家や漁師など5組の人びとの暮らしを追いかけてきました。ラフカット上映後のディスカッションでは、撮影映像を地域性や原発事故の被害などの共通項を手がかりに1本の映画にまとめる選択肢もあるのではと多くの意見が挙がりましたが、野村さんは「別々の作品として5本を完成させたい」と繰り返し表明します。

「大学を出てから田舎に行かなくちゃと思って行ったんです。都会では野菜も魚もすでに加工されたものばかりを享受していて、なにか薄っぺらいのではないかと思って」。農家や魚市場で働いた経験もある野村さんが語った言葉は、その土地に続いてきた生業そのものや水中の魚たちをじっくりと追いかける映像とも通じていたように感じます。
今回の道場のカメラマンとして参加した映像ディレクターの岡達也さんは質疑のなかで「これまで被災者は撮影者によって都合よく消費されてきた経緯がある。私自身も野村さんが撮影した地域出身で、なおかつ撮影者という立場だが、野村さんの映像からは被写体への愛情がひしひしと伝わってきた」とカメラをおろしてコメントしました。

講師のタン・ピンピンさんは、ワークショップ終了後に「今回印象的だったのは、福島の作品がカメラマンの岡さんのものも含めると3本あったこと」だと語りました。そのうえで、「東日本大震災や原発事故をめぐっては、若い世代にトラウマを残してしまっているのではないかと気付かされました」とタンさん。その言葉は、長引く日本の特殊な状況を、より濃く浮かび上がらせるものでした。