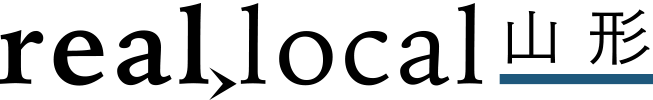山形ドキュメンタリー道場(3)/アヴィ・モグラビ監督 ✕ タン・ピンピン監督 ✕ 藤岡朝子さん 〜 なぜ「山形」で「ドキュメンタリー」の「道場」なのか?〜
国内外の映像制作者が集って行われた山形ドキュメンタリー道場(以下、山形道場)。そのワークショップのようすと、参加した映像作家の池添俊さんのインタビューを(1)(2)でお伝えしました。制作者同士が心を裸出して作品を見つめ直す場のほかにも、山形道場のプログラムには特筆すべき点があります。
それは、台湾、タイ、シンガポールといったアジアのドキュメンタリー制作者の滞在制作(アーチスト・イン・レジデンス<以下、AIR>)をサポートする4週間に、大学や小・中学校の学生たちとの交流機会がもうけられていたり、山形国際ドキュメンタリー映画祭が定期開催する「金曜上映会」にてAIR参加者の作品を上映するなど、このプロジェクトと地域との文化的交流にも重きがおかれている点です。

AIR映像制作者たちは、蕎麦を打ち、紅花染を体験するなかで山形の人と歴史に深く触れ、他方で大学生や小・中学生たちは、ドキュメンタリーというひとつの場所と結びついた視点に触れながら、日頃知ることのない世界の動きに目を向けるきっかけを得ていたように思います。

2019年11月13日に学生を対象に山形大学で行われた講演会は、土地や国に潜在する政治権力を見つめ続けてきたドキュメンタリーを介しての対話でした。登壇したのは、講師として山形道場に参加していたアヴィ・モグラビ監督とタン・ピンピン監督で、二人の対談とモグラビ監督の作品上映とが行われました。映画制作をめぐってタン監督が語るシンガポールの状況や、モグラビ監督が語るイスラエルの状況は、現在の日本に暮らす私たちにも多くの示唆と警鐘を与えるものだったように感じます。
こちらではその対談の一部をお伝えするとともに、山形道場という場でアジアの制作者をサポートしているのはなぜなのか、主催するドキュメンタリー・ドリームセンター代表の藤岡朝子さんに伺ったお話も紹介します。

無意識な自己検閲を強いる
シンガポールの法規制
タン・ピンピン監督の『シンガポールへ、愛をこめて』は、国内治安維持法を逃れてシンガポール国外に暮らす共産主義者や政治活動家などにタン監督自らがインタビューした2013年の作品です。アヴィ・モグラビ監督は、「ピンピンさんの作品は基本的に観察することによって非常に独自の映画文法や映画言語を生み出しており、シンガポールのポートレートのような政治的な作品をつくっている」と切り出し、なぜそのような作品をつくるようになったのかと質問。それに対してタン監督は、「自身のこれまでのキャリアは、カメラを通してシンガポールについて考え、カメラを通して自分の視点を確立するなかで構築されてきたもの」だと返答。『シンガポールへ、愛をこめて』では、亡命中の人びとがシンガポールに寄せる思いを作品で一番に伝えるために、自身の表現欲や思いを排除したインタビューという古典的な形式をとった経緯を説明しました。

そのうえで、「アヴィさんの映画は遊び心に溢れ、アヴィさん自身を前面に打ち出したものになっている。自分自身よりも政治的な状況や現実を優先させて映画をつくろうと思ったことはありませんか?」とタン監督から率直な質問が飛びます。
モグラビ監督は、映画のなかで自身を登場させるのは、映画作家が撮影プロセスの担い手であることを示すためであり、どんな作品にも必ず作り手がいることを伝えるためのメタファーだと強調。あらゆるメディアは、客観的な真実があるようにして情報を伝えますが、それらはすべて誰かが情報の取捨選択をして編集しているものであり、ある種の操作が伴っていると述べます。
「ドキュメンタリーというのは、現実を素材にしながら、それらを解釈し、編集して再構成しているもの。ですから、映像として登場しようとしなくとも、監督は作品のなかに必ず存在しています。ピンピンさんも、顔は見えなくとも、やはり作中に間違いなく存在している。しかし、シンガポールの現実と人びとの厳しさとを目の前にしてあなたが選んだスタイル、自分の操作や遊び心を最低限にしようとしたことに、私はとても共感します」と応じました。
タン監督が制作を行なうシンガポールは、アジア・太平洋戦争下では日本の軍政下におかれますが、日本の敗戦後に英国の植民地支配下で選挙を実施するなど政治活動を活発化させてきました。独立への機運が高まった1958年にシンガポールは英連邦内自治州となり、ともに独立をめざしたマラヤ連邦とボルネオ北部のサバ・サラワクとともに1961年にマレーシア連邦を樹立。しかし1965年にはマレー人の優遇策への反発を機に、シンガポールはマレーシア連邦から追放されるかたちで独立国となります。その建国以来、シンガポールではリー・クアンユー率いる人民行動党の一党支配により、経済成長と社会的統制が進められてきました。そのなかでは、表現の自由に対する国の関与も著しく、盛田茂著『シンガポールの光と影』によれば、「1998年改正映画法」により規制は一層強化され、検閲委員会への映画の送付義務化や、検閲委員会はフィルム及び機材を没収する権利をもつこと、また規制条項への違反者に対しては警察が介入できることなどが法律で定められています。
タン監督は、こうしたシンガポールの約60年間の政治体制下で表現が抑圧されてきたことを挙げながら、「シンガポールでは物質的に満たされた消費主義的な暮らしの代償として、重大な何かが失われてきたのです。政治的に対抗する人びとを沈黙に押しやるような法律が力を振るい、私たちの頭のなかに検閲システムを植え付けて心理的な自己検閲を強いている。そのことによって、権力の駒として動くような考え方が日常化し、現在のシンガポールに疑問をもつようなイマジネーションの芽が摘み取られてきました。これこそがシンガポールの最大の悲劇だと思います」と訴えました。

占領地で法律化された行政拘禁
二重性を抱えるイスラエル
このような政治的背景から、『シンガポールへ、愛をこめて』では自らの資金で秘密裡に撮影を進めざるを得なかったタン・ピンピン監督は、自身の状況とは対象的にも見えるアヴィ・モグラビ監督の制作に対し、「アヴィさんのような国家を厳しく批判する表現が可能なイスラエルの状況には、非常に驚かされる」とコメント。モグラビ監督は、例えば『二つの目のうち片方のために』では、イスラエル軍が占領地とのあいだに設置した分離壁の検問所へと自ら出向いて撮影をしています。国際的にイスラエル領と定められたグリーンラインよりもパレスチナ自治区のヨルダン川西岸に入り込んで建つ分離壁は、パレスチナ側の村を分断し、パレスチナ人は検問所前で日々理不尽な足止めにあっています。そのような状況を目の前にして、モグラビ監督が若きイスラエル兵に憤りあらわに抗議するようすも作品のなかに映し出されているのです。
しかし、タン監督の、イスラエルはシンガポールと異なって民主的な法整備が進んだ地にも見えるという発言に対し、モグラビ監督は「シンガポールの国内治安維持法のような、裁判なくして逮捕・勾留できる行政拘禁の法律が、実はイスラエルにも存在しているのです。ただしそれは、パレスチナの占領地においてのみ適用されるという奇妙な法律となっている」と応答。
イスラエルは、パレスチナの分割案に関する1947年の国連決議を受けてその翌年に建国された国です。しかし、土地を追われたパレスチナ人たちや周辺のアラブ諸国はその決議を拒否してイスラエルとの中東戦争が勃発します。第3次中東戦争の勝利でパレスチナの全土を支配下におさめたイスラエルは、さらにユダヤ人の入植を継続し、パレスチナ人の土地を占領し続けました。そうした状況下でパレスチナ人の大規模な抵抗運動が起こり、交渉の末に1993年にオスロ合意が成立。イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)とが相互を認め合い、ヨルダン川西岸地区とガザ地区でのパレスチナ自治政府による自治が開始されます。しかし、ヨルダン川西岸地区の自治地域はA地域とB地域とに分けられ、実際にはA地域のみにパレスチナ自治政府の完全な支配権があり、B地域はイスラエルとパレスチナ自治政府双方が治安権限をもつ地域として規定されたものだったです。高橋和夫著『なるほどそうだったのか!!パレスチナとイスラエル』によれば、B地域はイスラエルが警察などの治安権限を握る地域であり、しかもA地域はパレスチナ全土の4パーセント以下に過ぎないほどの面積という実態でした。

「つまり、イスラエルは二重の法制度を掲げており、イスラエル本土では正しい民主主義といえるような法を整備する一方で、占領地にはまったく違う法律を布いている。イスラエルという国は、そのような二重性を抱えてしまっているのです」とモグラビ監督は語気を強めます。
質疑応答の際に学生から「イスラエルを批判しながらも、イスラエルに住み続けるのはなぜなのか」と問われると、「それは、私もイスラエルの政治の一部だからです」と答えたモグラビ監督。「自分がこれまで映画制作において取り組んできたテーマは、人から勧められて始めたものは一つもなく、すべて個人的に自分が直接かかわったことから生まれています。イスラエルは自分の愛する場所であり、批判をしなければならないというモチベーションが、もしかしたら私をこの地に留まらせているのかもしれません」と語りました。
商業的しがらみを離れ
互いの映画と向き合う「道場」
山形道場のワークショップで参加者にコメントする際にも、常に「自分ならば」という視点での提案や議題提起が印象的だったモグラビ監督。対談終了後にその点について尋ねると、「山形道場でみなさんが発表した内容は、自分の映画づくりにおける悩みや課題とすべて共通するものだった」と話したうえで、「映画をつくってきてある時に気付いたのは、政治的なリアリティと私自身のリアリティというものが、必ずクロスしているということでした。私が一方的に現実を見ているのではなく、現実の側からも常に見返されているということです。ドキュメンタリー制作においては、映画をつくるプロセス自体が創造性に関わっており、だからこそ、そのプロセスの倫理的な側面が問題になってくるのです」と語りました。

また、山形道場のユニークな点については、「まさにキャスティングですね。講師やアドバイザーの選び方や組み合わせのみならず、蔵王という場所や環境も、作品について深く考えるうえで素晴らしいものだった」とコメント。対談のさなかには、政治的背景や法制度のディテールまで逃さず忠実に訳し続ける藤岡さんに感嘆の言葉を漏らしたタン監督も、「山形道場はいわゆる商業的なプロジェクトやワークショップとは全く質の異なるもの。ドキュメンタリーを題材としてお互いのために組み合って練習をする、それがまさに『道場』なのだと思う」と言います。

滞在中に通うことになった温泉は、タンさんの暮らすシンガポールにはないため、「裸になって入るなんて、恐ろしい」と当初は戸惑ったそう。けれどそのうちに慣れて、ゆっくり湯に浸かりながら語り合うなど、温泉は絆を強める特別な場所だったと話します。初めて大露天風呂に入ったときは、「『どうだった?』と朝子に聞かれ、思わず『日本人になりたい!』と答えた」と大きな笑みがこぼれました。
山形道場の企画者であり通訳者でもある藤岡朝子さんは、山形国際ドキュメンタリー映画祭でアジアの作家に光を当てる「アジア千波万波」部門のプログラムコーディネーターや映画祭のディレクターを約20年間務めてきました。そこで作り手と伴走するなかで、経済成長の著しいアジアにおいて、時間的な余裕を失っていく作家たちを目にしてきたと言います。

また、加速化するデジタル産業や、補助金の資金獲得の仕組みに合わせ、仕上げを急いでしまうばかりに素材のもつ可能性を自ら潰している作品が多いのではと、助成金の審査に関わるなかで気になるようになりました。そのような事態がなぜ起きているかを考えているうちに、この山形道場のアジアの制作者を招く企画に行き着いたのだと言います。「人と話していて気が付くときってありますよね。一人でこもって考えるより、人と対話して刺激を受けるとおもしろいと思うんです。また、季節が深まるようすを日々じっと眺めるなかで、表現したいものが何だったのか、見えてくることもあるのではないかなと」。
「誰かが作りたい映画について、他の人が『こうしなさい』と言うことはできないんですよね」と藤岡さんは言います。「それは、自分で考えて、自分で自分を知るところから始めなければならないので。これは山形国際ドキュメンタリー映画祭が、あれだけのプログラムのなかから、自分がおもしろいと思う映画を自分で見つけ出せる映画祭だということとも通じているように思いますね」。
山形国際ドキュメンタリー映画祭の理事として、これまで以上に足繁く山形に通うなかで、「こんなに豊かな山形があったのかと、私自身、新しい発見があった」と語る藤岡さん。今年の山形道場の滞在を終え、アーチスト・イン・レジデンスに参加した制作者たちと蔵王を降りる際には、淡い雪景色ときれいな虹に見送られたと、写真を添えて喜びのメールをくれました。蔵王の季節の豊かさと癒やしの源の温泉は、いま世界の映像制作者たちの目を通じて、再発見されています。


山形ドキュメンタリー道場2019
ドキュメンタリー・ドリームセンター