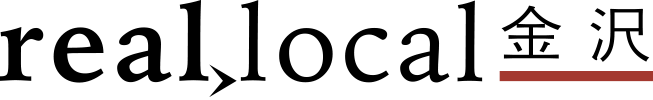九谷焼の“わからなさ”と向き合いながら/森義隆監督インタビュー
インタビュー
伝統工芸”九谷焼”の魅力を世界に伝える、産地のオンラインミュージアム「KUTANism(クタニズム)」。
2020年10月24日(土)〜12月20日(日)の期間中オンライン上で開催されており、そのこけら落としとして映画監督・森義隆氏による、撮りおろしショートフィルム「九谷棲む人々」の試写会が10月23日に行われました。(ショートフィルムはこちらにて12月20日まで公開中)
一ヶ月間、産地に張り付いて取材を重ね、「最終的には“九谷焼”という言葉すら使えなくなるほど迷った」と語る森監督。九谷焼と向き合う日々の中で、森監督が選び取った“九谷産地”を見つめる視座とは。試写会後にインタビューさせていただきました。
(※こちらは「GO FOR KOGEI」連携記事です)


何をもって“九谷焼”とするか
−−ご自身でも作陶されている森監督ですが、このショートフィルムの依頼を受ける以前の「九谷焼のイメージ」とはどのようなものでしたか。
「“一体どれが九谷なんだ”という印象は正直ありました。土産店や工芸のショップで九谷焼を見ていたときに、青や緑といった和絵の具(※)のものが九谷焼なのかなと思っていたら、全然違う様式のものもあって。“これが九谷焼か”と思ったら遠ざかる、その繰り返しというか。それが九谷焼との出会いですね」
(※)和絵の具…顔料をガラス質の原料を数種類合わせてつくる磁器絵の具。
−−舞台挨拶でも「知れば知るほど、九谷焼が分からなくなっていった」とおっしゃっていましたね。
「はい。もちろん勉強すればするほど、歴史の理解はどんどん進みましたし、現状も取材すればするほど、どんな作家さんが何を作っているのかという情報も増えていく。そうやって知識のパーツは増えて行くんだけど、何をもって“幹”として構成するか。『九谷焼』という主語を語るとき、何を以って『九谷焼』とするか自覚がないと、安易に語れないほど九谷焼って多様なものなので。最終的には『九谷焼』という言葉を自分が使えなくなるまでに迷ってしまいました」
(※)秋元雄史…東京芸術大学大学美術館館長・教授。練馬区立美術館館長。「KUTANism」総合監修。

土地の物語る詩情と、時間の奥行き
−−埼玉のご出身で、長らく東京の第一線で映像づくりをしておられる森監督ですが、そういった“外からの視点”で、九谷産地の魅力はどのように映ったのでしょう。
「改めて凄いことだなぁと思ったのが、この土地の石から器をつくって、その歴史を途絶えさせることなく、この狭い地域の中でみんながそのことでちゃんとご飯を食べてきた、という事実ですね。
それはもしかしたら『他の産地と比べたらどうなんだ』という議論はあるかもしれません。けれど、僕が“九谷焼”という言葉すら忘れて、純粋に九谷焼を見つめたときに、この土地での人々の営みや、その豊かさへの敬意というものが自然と生まれていたんです」


−−ご自身も4年前から金沢市に移住されてきているということも何か影響はあるでしょうか?
「能美・小松というエリアを見るうえで役に立っていると思います。東京からパッと能美・小松に来ていたら、もしかしたら『田舎だから豊かなんだよね』という見方に陥っていたかもしれません。
けれど自分自身が金沢に住んで、金沢という文化圏を介して能美・小松を見ると、また違って見える。つまり、藩政時代金沢にお城があって、加賀藩というところから派生している歴史や風土だということが理解できた上でこのエリアのローカリティが捉えられたのはよかったと思います」
九谷焼はひとつの“生態系”
−−徹底した下取材で知られる森監督ですが、今回も30人近い産地の人々に取材された上で、最終的にはこのショートフィルムで5名を撮られています。人選のポイントなどは?
「下取材させていただいた方は、みなさんとても魅力的でした。言葉も作品も、みなさんそれぞれで、その中で誰を選ぶかというのは非常に難しいところではありました。
誰を撮っても“九谷の美しさ”というものは撮れたとは思いますが、より映画的にしたいと考えたときに“物語る人”が良いなと。それは言葉だけじゃなく、姿や佇まいで“様々な時間”を物語ることができる人。実際に映像では、ひとつの場所には収斂されていかないけれど、みんなそれぞれに“時間の奥行き”について語っているんですよね。そしてその中で牟田さん(※)は“たった今”のことだけを話している、そういう構造をつくりました」
(※)牟田陽日さん…女性九谷焼作家。若手作家の中でも今注目を浴びる一人。作品集『美の器』(芸術新聞社)発売中。

−−「九谷棲(ず)む人々」というタイトルからも、人の営みへの目線を感じます。
「“棲む”というテーマが、途中から自分の中に生まれてきていて。もちろん『KUTANism(クタニズム)』とかけたというのもありますが(笑)。
そもそも“棲む”って、動物に用いる言葉ですよね。人間は“住む”ですから。撮り始めると僕には、この九谷焼の世界が次第にひとつの生態系のように思えてきて。豊かな自然のなかに、生命力の高い個々がいて、それぞれの食べるものが違っていて、食い合うことなく共存・繁栄しているといったような。そこで途中から『生態系を撮るように』という感覚に切り替えたんです。
本来であれば、人物が出てきたら名前をテロップで入れますよね。でも今回は一切名前も出さずにやっています。名前がでると、その人がどんどん情報化されてしまい、誰が偉いとか売れているとか、そういう文脈ではないところで語りたいと思った。九谷でその生命を営んでいる人々を、“九谷という生態系”を見つめました、という感じにしたかったんです」

細分化していく“エントロピー”をパワーに
−−今回の映像を撮り終わられて、「何が九谷焼なのかわからない」といった当初の想いに変化はありましたか?
「それが言語化できなかったから、こういう表現になったというのはあります。でも“焼き物”や“産地”の歴史といったものの面白さは、九谷焼を通して自分の中で非常に消化できたという部分はありますね。
それは土地と絶対に切り離せないものだということ。土から錬金術をして焼き物をつくり、何百年もの間その土地で人々が栄えてきた。それが例え今は大きな工場でスタンパーを用いてやっていることだとしても、それを土からつくっているということは変わらない。九谷焼がいかに多様であっても、根っこの凄さというのはそこだなと。それがなおかつ、自由で百花繚乱だから面白いのが九谷焼なんだと。
“自由である”ということは、“繋がって行く”という保証がないわけじゃないですか。なぜなら収斂されていった方が後世に残っていく確率が高そうなものだけれど。これは秋元さんがおしゃっていたんですが『むしろ、その細分化していくエントロピー(※)そのものこそが”九谷焼”なのではないか』と。そういう“個性的な歴史の繋ぎ方をしている九谷焼の面白さ”という視点が、自分の中にできた。
だから今なら土産物屋にいっても、九谷焼が多彩であればあるほど、分からなければ分からないほど、きっと面白く見ていける。ぐるっと一周しましたが、そういう思索の旅だったように思います」
(※)エントロピー…原子的排列および運動状態の混沌性・不規則性の程度を表す量。
PROFILE
森 義隆(もり よしたか)
1979年埼玉県出身。08年「ひゃくはち」で映画監督デビュー。同作が、新藤兼人賞銀賞、ヨコハマ映画祭新人監督賞を受賞。「宇宙兄弟」でプチョン国際ファンタスティック映画祭グランプリ、観客賞をダブル受賞。16年、「聖の青春」では高崎映画祭最優秀監督賞ほか国内外の映画賞を多数受賞。同年、金沢市に家族で移住。ほかに「パラレルワールド・ラブストーリー」、「バイバイ・ブラックバード」など。