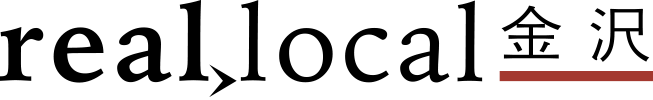金沢 能楽師・渡邊茂人さん 「型から入り、充実し行く中で的を射る。」
ローカル気になる人
reallocal金沢が制作した「KANAZAWA TRIAL STAY FILM -而今-」にもご登場いただいた能楽師・渡邊茂人さんへのインタビュー。能で生きていくことを選ばれた経緯や、今も能文化が息づく金沢への想いなどを語っていただきました。

能の美意識が、自分の中にあるものと合致した
父は能楽師の故・渡邊容之助ですが、正確にいえば私は渡邊家の養子なんです。母の姉の嫁ぎ先がこちらで、物心着いた時から日中はよく渡邊家に預けられていました。
能にも「子方」という子役が必要でして、そんなに人もいないものですから、めぼしい子どもには一通りやらせていたんですね(笑)。私もその一人として稽古を受け始めました。あと能は稽古事ですから、行儀・躾(しつけ)の意味合いもあったのだろうと思います。
最終的に東京藝術大学の邦楽科に進学し、「能で生きていく」ということを自分で決断するわけですが、そこに行くまでには葛藤もありました。やはり思春期と言いますか、他に楽しいことも色々と目に入る時期ですからね、高校に入ってからは一切稽古をやっていなかった時期もありました。当時はコンピューターなんかも好きで、理系の道に進もうかと考えたりもして。

ただ、能の舞台自体はずっと好きだったんです。男の子なので刀を抜いて様々な所作をする演目もあったりして、役になって舞台に立つということに面白みも感じていました。同年代から見れば、「なんてつまらないことやってるんだ」と、きっと思われているんだろうなぁとは思いながらも(笑)。
そして何より、能の様式美というか、その美意識がすごく自分の中にあるものと合致するところがあったんですね。私は高校時代に弓道をやっておりまして。弓道も日本的なものなので、能と通ずるところが非常に多いわけなのですが、要は「型」なんです。型にはまって、そこに美しさと実(じつ)が伴うと的に矢が当たる。型から入って、何か的を射るために充実していくという。
能に興味を持たれる方で、精神性のようなところから入って行かれる方もいらっしゃると思いますが、私の場合は子どもだったこともあり、内面的なことは分からないまま「型」から入りました。「型にはまって、出来上がっていく美しさ」というものには、非常に興味を持っていました。

時を超えて、人の心に響く普遍性
あと、古典ではあるけれども「能は現代を生きる人の心にも非常に響く舞台なのではないか」という想いも、幼いながら感じていました。
「隅田川」という悲劇の名曲がありまして。人さらいに遭い行方不明になった子どもを探していた母親が、子が葬られている塚を隅田川で見つけるという話です。その舞台では亡霊となった子どもが出てくるのですが、彼はすでに死んでしまっているわけですから触れたくても触れられない。抱きしめようとする母親の腕をすり抜け、最後には草茂る塚だけが残っているという-…。
これを初めて私が演じたのは小学校の低学年だったので特に何も思っていなかったのですが、舞台から涙を流すお客さんの顔が見える。「あぁ、能で泣けるんだ」ということをその時に経験したんですね。
「谷行」という演目なども、病にかかった少年が谷に置いていかれることを恐れて隠そうとする山伏がいたりと、どこか今日のコロナウイルスに通ずるところがあったりもして。能には人の心の普遍的な部分があるなと。

“気づける人”であること
生意気だった私が、能と真正面から向き合うようになったのは、大学に入学してからです。私達はちょうど第二次ベビーブームの世代でして、能楽専攻の生徒も稀なことに非常に多かったんですね。金沢には宝生流しかありませんが、藝大には観世流もありましたし、お囃子の生徒さんも一通りいらっしゃった。東京でやってきた彼らの意識というものが非常に高くて、私は“井の中の蛙”だったということを思い知らされまして。そこから闘争心に火がついて、能に没頭して行きます。
大学入学と同時に、東京にある宝生宗家の内弟子として、住み込みで修行するようになったことも大きかったです。そこでは芸事上のことはもちろん、日常生活の細やかなことに至るまで、先生方に厳しくご指導いただきました。
今まで生きてきた中で気にも留めたことがないような些細なことも、一つ一つご指摘を受ける。そこには“気づき”があるんですね。今で言うなら「〇〇ハラスメント」といった言い方で片付けて、気づかずに終わらせる人もいるかもしれません。けれど、そういった隅々にまでアンテナを張り巡らせ、“気配り”ができる人間であること、その全てが良い舞台に繋がるのだということを先生方から教わりました。

日常に「能」がある金沢の街
金沢では能が日常生活と密接に歩んできているのは感じます。良いか悪いかは置いておいて、東京では能舞台はもっと高尚な印象といいますか、非常にかしこまっていく場所になっていますよね。でも金沢ではふらっと入れる身近さがある。舞台と見所が近いというか、ご覧になっている方もある程度リラックスしてご覧になっていただいているのを感じます。観賞価格も別格の手頃さですし。
舞台数でいうとやはり東京・京都・大阪といった都市部が多いのですけれど、人口規模で比較した時に、これだけ狭い街でここまで頻繁に能舞台をやっているというのは、金沢が日本一なのではないでしょうか。
お酒が好きだった父が「いろんな土地のお酒がある中でも、やはり地元で、地元の酒を飲むのが一番美味い」とよく申しておりました。能にも似たようなところがあるように感じていて、加賀宝生においては、金沢の街で金沢の人たちがやっている舞台を見る、というのが一番良いのではないかと思ったりもします。

稽古に通われる市民の方も多いです。若い方なら大学のサークルから興味を持たれた方や、ご年配の方だとお弟子さん同士でコミュニケーションをとることを楽しみにして来られる方もいらっしゃいます。
ひと世代昔ですと、親なり上司なりに「やりなさい」と言われて始めて、今度は先生に「続けなさい」と言われて通っている方も多かったのだろうと思うのですが(笑)。けれど、そういう方でも10年20年、長い方だと30年40年と続けられているうちに、生活の一部となっているというか、もはやアイデンティティになってくるんですね。やっていないと、何か落ち着かない。新型コロナウイルスの感染拡大で稽古を休止した時期も、非常に残念がっておられました。

「実用品」として、次の世代につなぐ
時代とともに変わって行かなくてはならないものと、変わらずに残って欲しいものとがありますよね。けれど、一方で「変わらずに残って欲しいもの」が、あまり必要とされなくなったりもしています。例えば、能で使う道具や装束といったものの技術もどんどん失われている。実生活ではそれがなくても世の中的には困らないのでしょうけれど、我々としては例えそれが骨董品のようなものであっても全て「実用品」です。それは博物館に入れて大事に取って置かれたところで困るわけで。
現代社会は時間の流れが速いので、目の前の「今」を見ることだけで精一杯ですから、100年200年先のことを考えるというのはなかなか難しいことだと思います。けれど今私たちがこうして能を舞えているのも、先人たちのご苦労のおかげであるわけです。
「能」という室町時代から続くものすごく長い時間軸、その流れに身をおく一人としては、今度は自分たちが200年300年先の人たちに向けて何かしていかなくてはいけないなと、そういう風に感じています。
Photo(1枚目以外):Ryo Noda