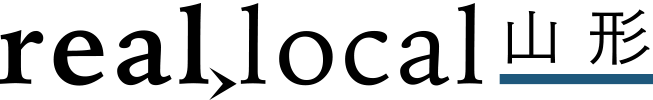旅人を応援するゲストハウス。「ミンタロハット」佐藤英夫さん
ローカル 気になる人

桜の名所、霞城公園のすぐ近く。山形市大手町に「ミンタロハット」というゲストハウスがある。
共用リビングを中心に、ゲスト同士が時間をシェアする宿。2007年の開業以降、旅好きな人たちから愛され、一見さんの観光客だけでなく、全国から多くのリピーターもやってくる。中にはこの場所を目的に山形を訪れる人もいるほど。私自身も何度か宿泊する中で、あたたかい空間と人に包まれ、癒されたひとりだ。
ミンタロハットを運営するのは、旅が大好きだという佐藤英夫さん。この場所はどのようにして生まれ、どんな思いで営まれているのだろうか。改めてお話をうかがってみることにした。

佐藤さんは山形市出身。現在ミンタロハットがあるこの場所で生まれ育ち、高校卒業後に大学進学のために上京、4年間を東京で過ごした。ご実家が呉服の卸業を営んでおり、家業を継ぐために22歳でUターン。数年間勤めたものの、仕事が合わずに退職。幼い頃から慣れ親しんでいた音楽をやろうと、ピアノの先生を始めることにした。
ピアノ教室の合間をぬって、ときどき海外へ旅に出ていた。バックパックひとつ背負って、ニュージーランドに5回、南米のパタゴニア地方にも訪れ、数週間から1ヶ月かけての山歩き。散歩の延長のように、景色のいい森の中や湖のほとりを歩く旅が気に入り、「バックパッカーズ(または、ホステル)」と呼ばれる素泊まりタイプの宿に泊まっていた。
「バックパッカーズの良さは、誰かと会話ができること。共有のキッチンやダイニング、冷蔵庫があって、自炊しながら旅をして、話ができる。値段が安いのも魅力でした。こんなタイプの宿は日本にはないなと、訪れるたびにいいなぁと思っていて。いつか自分でつくってみたいなと思っていたんです」
ピアノの先生を始めて20年が経った頃、自宅が老朽化して建て直すことになり、そのタイミングで増築して宿をやろうと踏み出した。47歳のときだった。


初対面のゲスト同士や宿のスタッフなど、他者との繋がりを楽しめる宿。従来のホテルや旅館とはまったく異なるスタイルで、当時は山形はおろか、首都圏にもゲストハウスと呼ばれる宿はほどんどなかった。それでも不思議と、開業に迷いや不安はなかったそうだ。
「ミンタロハット」とは、ニュージーランドで泊まった山小屋の名前からとったという。“世界で一番きれいな散歩道”と呼ばれる「ミルフォード・トラック」という山道沿いにある小屋で、「ミンタロ」という日本的な響きが気に入って名付けたそうだ。
「その山小屋には、同じ山道を歩いた人たちが泊まっているので、宿泊者同士が『あのスポットよかったよね』と、共感を持って話ができるんですよね。その雰囲気をここに持ってきたかったんです」
自分の旅の経験と想いを詰めこんで、平面図を描いていく。特にダイニングにはこだわりをもってつくった。みんなで暖まれるように、部屋の中心にはペレットストーブを設置することにし、すべての部屋に一体感を持たせるため、ダイニングから2階通路に吹き抜けのある空間が完成した。

こうして2007年にミンタロハットを開業。
ここには、日々あらゆるバックグラウンドの人が訪れる。山形観光のため1泊する人、ビジネスマンの出張や、さくらんぼ収穫やドキュメンタリー映画祭のボランティア、季節労働のため数ヶ月単位で滞在する人など。コロナ以前は台湾やヨーロッパなど海外からのゲストが半分ほどだった。
バックパックひとつ背負って、自転車やバイクで日本を横断したり東北を巡る旅人たちも多く訪れる。
取材中にこんな出来事があった。日中に玄関のチャイムがなり、飛び込みでチャリダー(長期自転車旅行者)が訪ねてきた。北海道から大阪までの横断中、連日野宿をしてきたそうで疲労困憊の様子。佐藤さんは急遽寝床を確保して、作り置いていた食事を提供していた。
「自分も20〜30代の頃はチャリダーをしていて苦労がわかるので、特に労ってあげたいと思うんですよね」と佐藤さん。さまざまな旅のスタイルを受け止めて、旅人を応援するゲストハウスなのだ。


リピーターの多さもミンタロハットの特徴のひとつだろう。コロナ以前から宿泊者全体の約4分の1ほどがリピーターというから驚きだ。宿についてわからないことは、常連さんに聞けばなんでも教えてくれる。
こうして常連さんを多く持ちながらも閉塞感はなく、初めて訪れたときから馴染みやすいのがミンタロハットの不思議な魅力だ。
「新規の方が疎外感を感じないように、特に新しいゲストさんのことを大切にしています。それが常連さんにも浸透しているようで、常連さんたち自らが新規の方を気にかけて話しかけたりしてくれるんです」
もはやお客さん自身も一緒にミンタロハットをつくっている感覚なのかもしれない。

ミンタロハットには、「フリーアコモデーション」という制度がある。ヘルパーとして、清掃やベッドメイキング、ゲストの案内などゲストハウス運営を手伝う代わりに、3食付きで無償で滞在できるというものだ。日中は別の仕事に出る人もいる。
6年ほど前、とあるゲストに作業を手伝ってもらったことをきっかけに、入れ替わりでヘルパーが常駐するようになった。1週間ほどの滞在もあれば、1年以上じっくりと暮らす人もいる。ゲストからヘルパーになったり、人の紹介だったり、きっかけは人それぞれ。「試しに山形で暮らしてみたいから」とヘルパーを志望する人もいるそうだ。
「ヘルパーのみなさんは家族のような温度感でミンタロハットを運営してくれています。次はどんな人が来るのかな?と楽しみにしているんです」

ミンタロハットには「ゆんたく」と呼ばれる交流会がある。「ゆんたく」とは、沖縄の方言で“おしゃべり”や“団らん”といった意味。
夜になるとダイニングからは調理をする音が聞こえて、いいにおいがしてくる。パスタや煮物、炒め物、ときには芋煮やだしといった山形名物などが並び、ゲストたちはダイニングに集まり料理やお酒を囲んでゆったりと語らうのがミンタロおなじみの風景だ。
そこでは「今日はあそこに行ってきた」とゲストから観光の話題があがったり、佐藤さんやヘルパーさんから「ラーメンだったら、〇〇がおいしいよ」といったグルメの話があったり、日常的にディープな山形の情報が交換されている。観光だけではない。いろんな人の人生の話を聞くことで、「いろんな生き方があるんだなぁ」と気付かされることもある。
「食べ物があることで人が集まり、会話が弾んで、初めての人同士でも『あ、これおいしいね』と共感が生まれますよね。そういう場所がつくれたらなと思っているんです」
みんなそれぞれ違う目的でここに来ている。初めての人もいればリピーターもいて、ご近所や地元の人が参加することもある。このゆんたくもまた、ミンタロハットの風通しがよく、あたたかい場所である秘訣なのだろう。

ぬくもりある空間、ヘルパーさんたちのきめ細やかな気遣い、気まぐれな猫たち、ゆんたくの時間。このゲストハウスに世界や全国からたくさんの人が集まり愛されるには、いくつもの要素があるだろう。ただ間違いなく言えることは、その大部分はオーナーの佐藤さんの存在にある。
日々入れ替わり立ち替わり、いろんな人が訪ねてくるゲストハウス。ホストとして大変な場面もあるだろうが、佐藤さんはいつでも変わらない。
ゆんたくの時間はだいたいダイニングの端に座り、みんなの会話に耳を傾けて見守りながら、ときどき話題を振ってくれる。肩にブランケットをかけるような、そんな穏やかな声のトーンと語り口で、果てない懐の深さを感じる。
「なぜいつもそんなに優しいのですか?」
思わず掴みどころのない質問をしてしまった。
「この場所をやっていると思うんです。みんなそれぞれ自分の中で『これは常識でしょ』って思っているけど、100人いたら100人の常識があって、本当の常識なんてどこにもない。自分の価値観を押し付けて『違うでしょ』とは言えない。『なるほど、この人はこういう考え方なんだ』って、受け入れるほうがずっといいですよね」

ミンタロハットの空気感は、佐藤さんの生き様そのものなのだろうと思う。この場所に癒され、救われた人はどれだけいるのだろうか。今日も全国各地から誰かが山形を訪れ、ミンタロハットのドアをノックする。
「酒田市の『ケルン』というバーに、『雪国』という伝説のカクテルをつくった井山計一さんというバーテンダーがいらっしゃいました。今年の春に亡くなられたのですが、井山さんのドキュメンタリー映画を見たら、90歳まで現役でお客さんの前に立ち続けていたというんです。僕もあと30年はできるんだ!と嬉しくなっちゃって。
この仕事をやっていて、いろんな人に出会えることがすごく幸せで、毎日楽しいなと思っています。これからもきっとこのままいくんだろうな、いけたらいいなって思っています」

取材・文:中島彩
写真:伊藤美香子