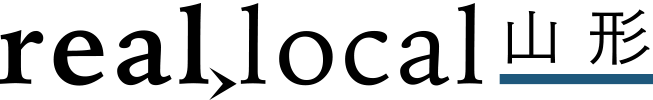山形移住者インタビュー / 菊地翼さん「自分のまわりから楽しく」
移住者の声
#山形移住者インタビュー のシリーズ。今回のゲストは、映像・音楽・まちづくりなどマルチに活動する菊地翼さんです。
菊地翼さん31歳。映像作家・ディレクター、カメラマン、イベントオーガナイザー、VJ、ナレーター、そしてコミュニティースペースの事務局長など、マルチに活動する若手クリエイターだ。コロナ禍以降は、一気に需要が高まる映像配信の現場にひっぱりだこ。「山形国際ドキュメンタリー映画祭」や「山形ビエンナーレ」など、山形を代表する催しに映像配信ディレクターとして参加している。山形の未来を担うマルチプレーヤーは、これまでどんな人生を歩み、今なにを見ているのだろうか?

山形県のほぼ中央に位置する人口約7800人の町・大江町。重要文化的景観に指定された昔ながらの風景が残る商店街の一角に「大江町まちなか交流館ATERA」はある。

菊地さんは山形市の自宅から週5日この場所に通い、運営から接客までをトータルにこなす。そのかたわら、映像制作・配信、スチール撮影、ナレーションなどのフリーランスで受けた仕事も遂行する。もはやどちらも本業。クライアントは、企業や自治体などさまざま。活動の中心は主に山形だが、県外に行くこともあり「ここ数ヶ月は休みがありません」という多忙ぶりだ。
目下の目標は、ドキュメンタリー映画を1本撮ること。
「仕事をいただけるのはすごく嬉しいんですけど、クライアントワークばかりやってきたので、これが自分の作品だって言えるものがまだないんです。本当に自分がやりたいことからずっと遠ざかってきたので、今後は自分の興味の対象のところに行って話を聞いていくような、フィールドワークとしての活動を1本の映像にしたいんです」

菊地さんの生き方を捉えようとするとき、もうひとつ重要な側面がある。それは「イベントオーガナイザー」としての顔だ。菊地さんはそれらの活動を「遊び」と言い切るが、これまで企画した音楽イベントは、遊びの域を超えた音楽コミュニティに成長している。
友人たちと企画開催した「岩壁音楽祭(2019)」。「素人が無茶をやっているというのを聞き、たくさんの人が手伝ってくれました」と菊地さん
「イベントで出会うのは皆ストリートの人たちで、本名も年齢もわかりません。そんな音楽コミュニティみたいなものが一番心地いい。その時間が仕事のストレスを清算してる気がします。今では一周してそこで出会った人たちと一緒に仕事をすることもあります」
気の合う仲間たちとともにつくる居心地のよい時間と空間、それはまさに自らの手で作りだしたサードプレイスだ。
お気に入りの場所を聞くと、「七日町の飲み屋街によく飲みに行くんですが、常連さんのコミュニティがあって、隣で飲んでる人にも話しかけてくれるような雰囲気が好きです。20代前半の頃は、緊張しながら入った店も、最近は『今日は誰かいるかな』みたいな感じで行くようになりました。ふらっと一人で行ける良いお店があるのは嬉しい。」と菊地さん。
20代の葛藤
なんでも器用にこなし、どこでも重宝される存在。仕事も遊びも順風満帆。そんな風に見える菊地さんにも、前にすすめない時期があった。
3人兄弟の三男として福島県で生まれた菊地さん。小学4年の頃に宮城県古川市に引っ越し、高校は市内の進学校へ。「自身の道は定まらないが誰かの敷いたレールには乗りたくない。地方都市に生まれ育った劣等感や未来への焦燥」そんな気持ちを満たしてくれたのが、音楽や文学、そして映画だった。大学は映画を学びたいと美大に決めた。映像を学べる学科がある東北芸術工科大学へ入学。30年以上も続いている山形国際ドキュメンタリー映画祭の存在も、山形に来たいと思う決め手のひとつだった。
大学では映像を学ぶかたわら、ラジオドラマをつくるサークル活動にのめり込んだ。
「月1ペースでラジオドラマを作り、それを地元のコミュニティFMが流してくれました。ナレーションやお芝居が入った声の掛け合いや、SEといった効果音や音楽付けもすべて仲間内でやりました。結構な数を作って、とくに台本はだいぶ書きましたね」
遊びの延長で、気の合う仲間と音楽イベントを始めたのもこの頃から。大学、バー、クラブ、友人の家のキッチン、さまざまな場所で毎月のようにイベントを企画した。どうしたら客が来るのか? 運営を上手くまわせるのか? そんなイベントオーガナイズのイロハを学んだのもこの頃だ。

しかし、大学2年の後半から徐々に学校から足が遠のいていった。
「台本を書いてると、どんどん自分の世界に入って抜けられなくなっちゃうんですよ。もう、ずっと書いてたいって。大学に行ってもずっと図書館にいたり。授業に出てもそわそわしてしまって」
さらに、慣れない一人暮らしが追い打ちをかけた。ひどいアトピーとそれに伴う鬱。気付いたら自分だけ単位を取れないまま4年生になり、同級生たちは卒業していった。大学は5年間行き中退。「自分だけが」という負い目。でも、決して後悔はしていなかった。
「自分は誰よりも真面目にやってたと思ってます。自分を追い込んで講義にも出ないで台本書いていた。だから、まわりの友達よりも『もっと何かできる』と思っていました」
ある日、コンビニで求人誌をながめていると、お世話になっていたコミュニティFM局の社長に偶然出会った。
「うちにおいでよ」
その一言に、ラジオ局への入社を決意。入社後はラジオの制作業務の傍ら、フリーペーパーや映像、webの制作事業を担った。撮影、ナレーション、紙モノのデザインや文字組みまで、すべて一人でこなした。そして半年後、産休に入ったパーソナリティの代行としてラジオパーソナリティに抜擢。生放送まで準備期間が1週間しかないという危機的状況の中、構成を自ら考え原稿も準備、生放送2時間半をやってのけた。その後、番組は週2回に。2年半続いた。
「最初の頃はニュースを読み間違えたり、失敗ばかりでした。でもリスナーの人たちは『若いヤツが急に番組まかされたな』ってなんとなく分かってて。応援のメッセージを送ってくれたり、あたたかかったですね」
このときに現場で叩き込まれた放送ノウハウが、後のコロナ禍で引く手あまたとなる映像配信での活躍へとつながっていく。

自分でつくろうとする人にこそチャンスがある
持ち前のセンス器用さでなんでもこなす菊地さん。そんな彼にでもできないことってあるのだろうか。
「できるか不安なことでも自分がやりたければ『やります』って言ってからどうやってやるか考えます。失敗することもありました。でもここには、自分でつくりたい人に環境とチャンスがたくさんあって、僕はそのチャンスの方を取った。学ぶより先にやっちゃえと。たくさん失敗もするし怒られるときもあるけど、切腹するわけじゃないから、やって失敗した方が早い」
ラジオ局で奮闘し3年が経過した頃、自転車操業状態だった会社の資金繰りが悪化。菊地さんは悩んだ挙げ句、退職を決断。その後、再就職も考えたが、自分ががやりたいと思う仕事には出会えなかった。
結局、知り合いから依頼されるナレーション・映像・写真などの仕事をこなしていたら、自然と働き方はフリーランスになっていた。
転機が訪れたのは、それから数ヶ月後。大江町を拠点に活動するフォトグラファーがスタッフを募集しているという話を聞きつけた。さっそく会いに行くと、これからスタートする町の魅力を発信するメディアに制作メンバーとして誘われた。「楽しそう」と直感し参加を決めた。
「やってみるとフィールドワークとしてすごく興味が湧いてきて、これはライフワークとしてやっていきたいなと思えました」

まちづくりという新たなフィールド
約300人以上の町民へのインタビューを通し、等身大の町と人の魅力を発信したwebマガジン『おいでおおえ』は、2019年度やまがた公益大賞を受賞。これが機となり、菊地さんはクリエイティブチームの一員として、さらに活動の幅を広げていった。そしてその延長にあったのが、「大江町まちなか交流館ATERA」運営団体の事務局長というポジションだった。
「前事務局長が退職した後に誘われて。でも自分は町民でもないし地元民でもない。そこまで責任を持てないと始めは思ったんですが、なかなか後任が見つからなくて。内情も知っていたし、フリーの仕事も続けていいということだったので、ひとまずの繋ぎのつもりでした。結局そこから3年も経っているんですけどね笑」
菊地さんにとって「まちづくり」は、まったく新たなフィールドだ。大江町に関わりはじめて5年の今、見えてきたことがある。それはまちづくりは一人ではできないということ。
「ようやく行政と一緒に歩めるようになってきたとか、近所の人たちと顔と名前がわかって緊張しないでコミュニケーションとれてるなとか、まだまだそんなレベルです。まちづくりって本当に時間がかかる。今は仲間を集めている段階かな。もし今、成果として言えるとしたら、それは今ここで一緒に活動している20代たちが、この場所を選んでやってきてくれたということでしょうか。人がひとり来るって本当にすごいことですから」
菊地さんが今、そんな若手たちとともに挑戦しているのが、この場所を地元の高校生たちのサードプレイスにしていこうという取り組みだ。当初、生徒とのつながりができず難航していたが、共に取り組む若手のひとりである東北芸術大学コミュニティデザイン学科の学生が関係構築に動き、活動が展開。高校生が写真展をひらいたり音楽や食のイベントを開催するなど、地域を巻き込んで主体的なアクションを起こすまでに成長している。
ここには今、ココアを飲みながらリラックスした表情で談笑する高校生たちの姿がある。共に歩む20代へ、そして高校生たちへ。彼らを見守る菊地さんの眼差しはあたたかい。

「自分が道を探り始めたとき、すごく辛かった。だから彼らのサポートになることをしたいなと思うんです。それは助言を与えて彼らが生きやすくするということではなくて。きついときに隣で『きついよね』って言える人になりたい。そして自分は彼らに恥ずかしくない仕事をしたい。そういうものを作っていきたいんです。」
学生時代の恩師が言った忘れられない言葉があるという。それは、ものをつくる社会的意義と責任について。
「自分が映像を作るということは人に影響を与える、だから正しい方向に導くものを作りなさい、と。今自分が正しいと思っているものに向かわないと世の中は良くなっていかない。少なくとも自分のまわりは良くなっていかないと思うんです」
まちづくりを通して浮かび上がってきた新たなアイデンティティ。
菊地さんの挑戦は始まったばかりだ。
取材・文:高村陽子
写真:伊藤美香子