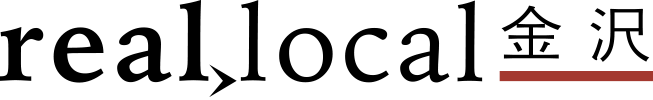「自分に何ができるのか」。“ほわっと”した想いに形を与え、地域課題の“What”を見極める力。/「ほくりくみらい基金」団体への寄付募集
NPOなどのソーシャルセクターが弱いとされてきた石川で、2023年4月に発足したコミュニティ財団「ほくりくみらい基金」。設立から1年にも満たない2024年1月1日、令和6年能登半島地震が起きました。ほくりくみらい基金では翌日の1月2日には基金を立ち上げ、この一年で総額約1億1千万円もの寄付金を集め、のべ134団体へ助成。同時に、助成先団体へのきめ細やかなサポートにも定評があります。
今回は、震災など目的別の「基金」とは別に、「ほくりくみらい基金自体への寄付」を募集中とのことで、代表理事&理事のお三方へのインタビュー。地域やコミュニティの課題解決のために寄付や基金を仲介する「コミュニティ財団」。その価値や存在意義への認知が広がる一方で、コミュニティ財団をはじめソーシャルセクターで働く人々への「人件費」への理解がなかなか進まないという現状があります。今回は、団体設立の経緯から、現場で感じる課題感、そして次なるフェーズの展望まで、お話をうかがってきました。


震える手で作業していた、あの日
ーーほくりくみらい基金さん、側から見ていてもこの一年ものすごい活動量でしたが、こんな少人数で回しておられるなんて、にわかに信じがたいです…。まさに八面六臂の活躍というか。
永井:あとは経理担当の道下さん含めて、実質4名が実務メンバーという感じですね。ちなみに守山さんと須田さんは、こう見えてダブルワークで関わってくださっているんですよ。
守山:去年一年間は、感覚としては週8日くらい働いてたような気がしてます(遠い目)。

ーーそれぞれご家庭もあって、子育てもされていて、当然ながら“生活”もある中で。
須田:家庭はだいぶ犠牲にしていましたね(苦笑)。とはいえ、能登の方たちは比べようもない困難に直面されているので、この一年できる限りのことはやろうと。
永井:私達はまだ“日常がある中”での忙しさや苦労ですけど、能登の方達はその“日常”が無くなってしまっているわけですからね。
ーー活動量はさることながら、スピード感も目を見張るものがありました。令和6年の能登半島地震の際は、元日の発災にも関わらず、翌日には「令和6年能登半島地震 災害支援基金」を立ち上げ寄付受付を開始されていました。
永井:発災直後にメンバーの安否確認をして「これは基金が必要だね」と。翌日ミーティングして、技術的なことは全国コミュニティ財団協会の方にサポートいただきながら、その日のうちに寄付受付のサイトを公開させました。
須田:これまでに経験したことのない、全くの未知の事態に、作業する手が震えていたのを覚えています。何の見通しもないけれど、今できることとして、とにかくこれ(災害支援基金)を立ち上げねばと…。

「ほくみさんが、あってよかった」周囲の変化
ーー団体設立から1年未満で経験した大地震、特にどんなことに苦労されましたか。
永井:まだ出来たばかりの小さな団体だったので、“基盤整備”をしながら膨大なオペレーションを回していくということが、なかなか大変でしたね。
また、財団としても個人としても、こういった災害支援は初めての経験で。友人や知人の家が潰れたり、ご家族が亡くなられたりー‥すごく近しい人達が被害に遭っていて、「何とかしたい」という当事者感や現場感と、災害支援のあるべきセオリーとの間を行き来しながら、ずっとフル稼働しているような日々でした。
今でも何が正解だったのかはわかりません。けれど、コミュニティ財団として「まとまった基金」を集められたことは一つ役目を果たせたのではないかと思っています。そしてその基金の助成先団体さん達が、各方面で出された成果に救われてきた一年でしたね。

ーー北陸ではまだまだ「コミュニティ財団」の存在意義が認知されていなかったように思いますが、震災を経て変化はありましたか?
永井:180° 変わった感はあります。「ほくみさんがあってよかった」というお声を、沢山頂戴しましたね。
守山:確かに設立当初は「そういうのが新しく出来るんだね、頑張ってね」というご祝儀的なお声だったのですが、地震後は「本当に頑張って、頼んだよ」という切実な感じになったというかー‥。
永井:令和6年奥能登豪雨の時も、地震の際の実績があったから「ほくりくみらい基金に寄付をして!」と、たくさんの方がSNSでのシェアや呼びかけをしてくださって、「やっていてよかった」と感じられた瞬間でしたね。

「立ち上がろうとする人達」を応援する「お金+仕組み」を
ーーでは、そもそもの「ほくりくみらい基金」立ち上げ経緯から改めて教えていただけますか?
永井:社会のために「何かをやろうとしている人」を、応援するための「お金」や「仕組み」があればいいなと、私はずっと思っていたんですね。
というのも、OUIK事務局長としてSDGsを推進する「IMAGINE KANAZAWA 2030.」のイニシアティヴを担当して時に、「こういうのいいよね!」っていうアイディアがいつも沢山出るのですが、お金がないと実際に「やっていこう」とはならないという現実を何度も経験してきて。
もちろん行政の支援もありますし、金沢市は市民協働が充実している地域ではあると思います。とはいえやはり「行政」なので、申請などが厳しかったりと“硬さ”がある。
もう少し柔らかい“人と人”というか、“ご近所さん”のような顔の見える関係性の中で、一緒に働くための仕組みがあるといいと思ったし、その「具体例」を実際につくりたかったんですね。そういうことを考えていた時にコミュニティ財団立ち上げのための助成があることを知って、応募したことがきっかけです。

ーー永井さんの代表理事メッセージにも「地域課題解決のための資源投入や意志が個別の成果に終わり、大きなうねりにつながっておらず、なんとなくモヤモヤしていました」との一文がありました。「大きなうねり」になっていかないと。
永井:それぞれの活動や人を、“繋いでいく装置”がないんですよね。つまり、それをやる経済的な原理がない。マーケットでやるのは難しいので、行政がやるしかないけれど、行政には常に“公平性”が求められるので、スムーズな動き方はなかなか難しい。行政よりも、もう少し柔軟で開かれた「お金+仕組み」があるといいなと。
もしこれが「企業」なら、そういった仕事に対して「人事の仕事」としてお金が行き渡るようになっているけれど、ソーシャルなセクターにはそれがないんですよね。

「ちゃんと面倒を見る」とは、どういうことか
永井:財団って、寄付で集めたお金をただ“右から左”に助成団体さんにお渡ししているわけではなくて、団体さんと面談して「それはいいと思いますよ」って励ましたり「そこは弁護士さんに聞いた方がいいかもしれない」といったことを、時には電話で2時間相談にのったりもしています。
でも、こういった仕事の大切さが中々伝わらないというか、そもそも皆さん知らないと思うんですよね。つまり「団体を応援する」という仕事とその価値ですよね。設立当初は「お金」を助成することが何より大事だと思っていたんですけれど、その前後にある「ケア」というものがいかに重要か、これはやってみて気づいたことです。
そこをどう伝えたらいいのかー‥「あたたかな繋がりを」って表現しても「それって絆だよな」みたいに抽象的な話になっちゃうし、「応援する」って「いいね」を押すくらいの軽い感覚だと思われてる。そうじゃなくて「ちゃんと責任持って面倒を見る」ってことなんです。

ーーなんだか、子育てや作物の手入れなどにも通じる気がしてます。「〇〇してね」って口で言って、後はまかせたので知りません、なんて通じるわけもなく。例えば「子どもが自分で歯磨きができる」まで、どれだけの目配せと配慮があったかというー‥。
永井:そうなんですよね。一緒に時間を過ごす、伴走することの大切さというか。「ちゃんと面倒を見る」って、「どれだけ目をかけられたか」ということでもあって、時間がかかることなんです。システムとかコマンドとか、そういう世界の話じゃないんですよね。
立場が違う「みんな」の想いを守ろうとすると
守山:私はほくみの中でも、主に「寄付を集める」までを担当してきたのですが、助成プログラム一つ作るのにもすごく時間がかかっていて。ただ申し込みがあったから「はいどうぞ」という話じゃないんですよね。
私達はどういう活動が必要だと思っていて、それにはこういうニーズがあって、かつ使い勝手が良いようにある程度柔軟性も持たせたいし、かといって緩くなりすぎるのも心配だからある程度の制約もー‥と。
私たちの想い、寄付者の想い、団体さんの想いー‥みんなの想いを守っていこうと思うと、「この言葉で伝わるだろうか」「この表現を入れることで溢れてしまう人はいないだろうか」と、要項一つ作るのにもすごく考え込んでしまいます。でも、ここで手を抜いたら結果として如実に返ってくることは、これまでの経験で実感してきたことなので。

「ソーシャルな活動経験がない人達」こそ、応援したい
ーー特に、ほくりくみらい基金の助成先団体さんって、元々“プロボランティア団体”だったようなところは少ないですよね。むしろ、これまでソーシャルな活動経験のない方をエンパワーメントするというか。それって「手取り足取り」になる部分もあると思うので、なおのこと大変だなぁと。
守山:でも私達は、そういう人たちこそ応援したいという気持ちがあるので、その労力は甘んじて受け止めなければいけない、とも思っています。
私は関西の出身で、以前は京都のNPOで仕事をしていたんです。京都って市民活動が盛んで、コミュニティ財団も15年以上前に作られていて。私が結婚を機に石川県に引っ越すことになると伝えたら「石川ではあなたが思うようなソーシャルな活動はできないんじゃない?大丈夫?」とすごく心配されたんですね。確かに引っ越してきてみたら、当時石川県にはコミュニティ財団はなかったし、NPO団体もすごく少ないという状況が見えてきて。

守山:ソーシャルな活動ができないと心配されていた石川で「コミュニティ財団」を立ち上げた矢先に、地震が起きました。そこで、今までは「何かやりたいけど、何をしたら」と思っていた人達が「今やらんとあかんやろ!」と一念発起して立ち上がった。その方達にはボランティアやNPOの経験は少ないかもしれないけれど、「何かやりたい/やらなくちゃ」と思ってパッと動いた人達。その背中を押してあげたいなと。
もちろん震災って、ものすごくネガティヴな出来事ですが、せめてそれが、これから石川の市民活動を作っていく一つの契機になったらいいなと願っているんです。
須田:スーパーボランティアのような「特別な人たち」だけじゃなくて、「世の中に役に立ちたい」と思った誰もの想いを形にすることができたなら、世の中だいぶ良くなるんじゃないかと思いますね。

寄付者と団体、両者の「ほわっと」を繋いで、現実の力に変える
ーー今回取材同行する中でも、寄付者さんは「何か力になりたいけれど何もできなくて」とおっしゃるし、団体さんも「何かしたいけれど、自分に何が出来るか当初はわからなかった」と、どちらの想いも元々はすごくぼんやりとしていたということを感じました。ほくみさんがやっていることって、両者の「ほわっと」した想いを繋いで、現実の形を与える精錬作業なんだなって。
永井:言われてみると、確かにそうかも。それ、プレゼンのスライドに使わせてもらおう(笑)。

ーーだからこそ、ターゲットも違えばテーマも違う、それぞれ「出来ること」が違う団体を支援することの意義があるというか。「多種多様な小さい団体」って、バラバラなだけに統括が大変だと思うけれど、「だからこそ手が届く人々」がいるのだと感じました。こういった小さいところに積極的に助成するというのは、コミュニティ財団の特徴なのでしょうか?
守山:もちろん大きいところにも出せるけれど、「小さいところにも出せる」というのはコミュニティ財団の一つの特徴だと思います。でもそれって、「地域にいる財団」だからこそ、見えることだと思うんですよね。
須田:ありがたいことに「ほくみさんが選んだ団体さんだから、信頼できる」というお声もいただきました。目利きというか、これもコミュニティ財団の一つの役割のように思います。

ーーさて、今回の本題は、「ほくりくみらい基金」自体への寄付募集だったかと思います。今回この募集をされる理由をお聞かせ願えますか?
須田:はい。ほくりくみらい基金への昨年の寄付額は、総額約1億1千万円でした。しかし、そのうち私達が財団として自由に使える金額は約360万円。それは、ほとんどが「災害支援」のための基金への寄付だからです。まず基金は“目的別”に立ち上げられていて、それ以外の目的にそのお金は使えない、という大原則があります。
昨年は災害支援一色でしたが、本来ほくりくみらい基金は石川県全域を対象としている団体です。なので、例えば「震災の文脈ではないけれど、これから広げていきたい先進的な取り組みをしている団体」へ助成したい時、「360万円」の私たちの運営費を削って出さざるをえないわけです。もしくは、新たな基金を立ち上げる必要があるのですが、外から見れば「ほくりくみらい基金さんはあれだけ寄付金が集まっているのに、何でまた基金を立ち上げるの?」と思われるでしょう。

ーー確かに。この1年は災害支援に注力されていたと思いますが、本来の支援対象はそこだけではなかったはずですからね。
須田:もちろん、震災で潜在的にあった問題が顕在化して、平時の課題解決につながる、という側面もあるのですが、それにしても震災文脈をつけないと助成できない、というところにもどかしさがあります。
基金が目的別に作られていることによって、お金に「色が付いている」ということは、支援対象者を色分けしないといけないことにつながったり。そうはしたくないけれど、けれどそれが寄付者の想いに答えることにもなるのかな…など、いつもその間で葛藤しています。
「人を支える」には、「支える人」の人件費が一番大事
ーー昨年ほくりくみらい基金さんの「つづける支援活動助成」の助成団体取材に一部同行させていただく中で「助成金を『人件費』にあてられることに救われた」というお声を何度となくうかがいました。人件費に使って良い、ということは画期的な試みだったのですね。
須田:「つづける支援活動助成」を立ち上げた時は、発災から4ヶ月が経過していたこともあり、ボランティアの人たちが無償で活動を続けていく“分岐点”にあったと思っています。でも、今頑張ってくれている人たちが続けてくれないと、そこで支援がプツリと途絶えてしまう。そこで、発災から1年を迎えるまでは活動を継続していただくために「仕事」として請け負っていただける資金が必要だろうということで立ち上げました。


ーーその助成を出しているほくみさんが運営費で困っているという状況は、灯台下暗しというか…。
永井:「運営費」や「経費」といった「モノ」にかかるコストに対してはすんなりご理解いただけるんですけど、「人件費」となると、急に目が厳しくなるという傾向はありますよね。
守山:「ボランティアは清貧でないといけない」というイメージがあるというか。
永井:でも結局、人が人を支えるには「支える人の人件費」が一番大事なんですよね。極論をいえば、私たちのこの事務所だって机だって、なくたって別にどうにでもなるんです。大切なのは、このチーム。必要なのは結局「人」なんですよ。

「なりたい職業ランキング」に「NPO職員」があっていい
守山:震災が起こる前から、私も須田さんもソーシャルセクターの人件費について問題意識を持っていました。私は「仕事」としてソーシャルセクターがあっていいって、ずっと思っていたので。「小学生のなりたい職業ランキング」に「NPO職員」があってもいいじゃないかって。
須田:「人をケアするには、ケアする人の人件費が一番必要」という課題って、福祉や保育の人件費が上がらない問題ともすごく重なる部分がありますよね。「+α」のサービスやエンタメにはすごく付加価値がつくのに、何で「人のケア」にはこんなにもお金がつかないんだろうって、いつも思います。

「本来、どういう姿がよかったのだっけ?」
ーーその「つづける支援活動助成」も、2025年1月を持って満了となりましたね。震災から一年、この一年を振り返ってみていかがでしたか?
須田:助成先の団体さんから学ぶこと、気付かされることがとても多い一年でした。特に興味深かったのは、元々ソーシャルセクターじゃない、地震をきっかけにボランティア活動を始めた人たちから出てくる言葉。
例えば「困っているから無償で支援を続ける」ということで、むしろ「支援を受ける人が恐縮してしまって、支援を受けようとしなくなる」ということを体感した、というお声。良かれと思って無償で提供するけれど、それを感謝して受け取れる人もいれば、そうじゃない人もいるのだということを知って。
支援団体さんは、受益者の方々と直接触れ合っているので、日々リアルで具体的な要望を聞くことも多く、一生懸命その声に応えようとする。けれどその一つ一つに応えることにだけ専念してしまうと「本来、どういう姿だといいんだっけ?」という俯瞰した視点が欠けてしまう恐れもあります。

柔らかさと、剛さ。市民活動の“芽生え”を支える
須田:だからこそ、永井さんがいう「しなやかで柔らかい部分」と、「なんでそれをやるのか」という「しっかりとした芯」、その“柔と剛”のバランスが大切なんだなと改めて感じました。
ほくりくみらい基金って、「やさしい団体」と言っていただくことも多いのですが、優しいだけでもだめで。これは経理の道下さんと話していたことなんですが「私たちは、団体さんの“芽生え”を支えるんだ」と。震災を機に立ち上がった、たくさんの団体さんが、今後も活動を継続していくために、他の助成も取れるようになってほしい。自分たちで寄付も集められるようになってほしい。そのために経理や事務もしっかりして、長きに渡って信頼を獲得し活動していってほしい。だからこそ“獅子の子落とし”というか、「育てる」うえで厳しさも必要なんじゃないかと。
守山:先ほどの「非営利だってお金がいる」の裏返しで、「非営利だって、経理はちゃんとしないといけない」ということですよね。そうやって初めて、「お金」が扱える。

未完成の、一緒につくっていく財団だから
須田:だからこそのクールヘッド・ウォームハートというか、冷静と情熱の間で悩みながら、皆さんと一緒に成長している、今まさにその過程にある感じです。
以前寄付者の方にインタビューした際に「ほくみには“パンク”であってほしい。“インディーズ”であれ」とおっしゃっていたんです。ほくりくみらい基金って、いろんな人の気持ちや考えでできているので、つるんと“綺麗に出来上がった”団体ではありません。全然これから変えられるし、作れる。そういう風に思って応援していただきたいですね。

ーーなるほど。だからこそ「推して」ほしいと。それで今財団としての寄付を募集されているわけですね。それでは最後に、次のフェーズは、どのようなことを目指されていますか。
永井:昨年は「災害支援」という、需要が明確なものに対してお金を出してきました。それはもちろんスピードも重視されるし、ある意味次々来る案件に対して反射的に応えるような性質のものでした。でも次の「復興」というフェーズに向かっていく時には、「地域の構造を理解して課題を見つける力」が必ず必要になってきます。そういう「難しいこと」を、私達はやらなければいけない。
支援活動自体もケースマネジメントに向かっていて、それは今後法律にも反映されていくと思います。それくらい個人のニーズが多様化していて、一人一人の「困った」という声に対して対処療法的に対応し続けることが難しくなってくる中で、その根底にある「構造的な問題」を見抜かなくてはいけない。だからこそ、偏りなく多様な人々の意見につぶさに耳を傾けなくてはいけないと思っています。そのためには「時間」も「お金」も必要になってきます。

「未来はつくれる」と誰もが思える地域に
守山:ほくりくみらい基金の設立当初からのビジョンは「“未来はつくれる”と、誰もが思える地域にする」ということです。「何かしたいけれど、自分一人では何もできない」と思っている人が、お金があることで実現できたり、「何もできないから、せめて寄付だけでも」という人が、そのお金が良い使われ方をすることで、自分達で未来は作れると手応えを感じられたりー‥。そういうことが起きている“現場”を皆さんに伝えたいし、私自身も見に行きたい。去年1年は事務所でずっとパソコンと睨めっこで、全くどこにも行けなかったので‥(笑)。
「この人達だって、元々は“何をしたらいいかわからない人”だったんですよ!だからあなたにもできる!」ってことをお伝えしたいし、「石川のソーシャルセクターも頑張ってます!」って声を大にして広めていきたいですね。

須田:私も設立当初から変わらないものとして「頑張ってる人を孤独にしない」という想いがあります。この地域にはソーシャルセクターの人がまだ少ないので、不安や孤独感を感じることもあると思います。せっかく社会を良くしたいと思って頑張っている人たちを、ひとりぼっちにしたくない。

須田:そういう人達が繋がり合える機会があればと思って「ほくみの学校」を企画しているというところがあります。頑張ってる人同士が横連携で繋がって、お互いに支え合える、そういう仲間ができればいいなって思っています。
永井:「未来を自分たちでなんとかしよう」と思う人がちょっとずつ増えれば、もっといい地域になると思うんですよね。次の1年はそこに資源を割いていきたいし、いかなければならないと思っているので、ぜひほくりくみらい基金へのご支援をよろしくお願いいたします。

ーーーーーーーー
(以上インタビュー)
「必要なのは、このチーム」という言葉にあったように、昨年のほくりくみらい基金の活動は、間違いなくこのメンバーでなければ成し遂げられなかったことだったと思います。
めちゃめちゃ“シゴデキ”で知的、そして胆力もガッツもあるー‥(加えて戦隊モノのようにキャラが立っている!)。こんな唯一無二な“チーム・ほくみ”を推す応援寄付は下記リンクから。
(取材:2025年4月)
| 屋号 | 公益財団法人 ほくりくみらい基金 |
|---|---|
| URL | |
| 備考 | ▼「ほくりくみらい基金」への寄付はこちらから |