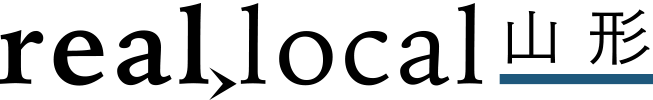中山ダイスケ × 志津野雷【前編】/ぼくらのアートフェス 3
2018年秋開催の山形ビエンナーレ直前。全国のアートフェスのディレクターにフェスへの想いを語っていただきその魅力を紐解くトークシリーズ「ぼくらのアートフェス」第3回のゲストは志津野雷さん、聞き手は東北芸術工科大学中山ダイスケ学長です。

じぶんの目で確かめる旅へ
中山:第3回のゲストは、ぼくの友達でもあり、大好きな写真家でもある志津野雷さん。今日は「逗子海岸映画祭」そして「CINEMA CARAVAN」プロデューサーとしてお呼びしました。
志津野:はじめまして。これまでぼくがやってきたことを紹介するなかで、こんな生き方もあるんだとか、なにかみなさんの役に立つことがあれば嬉しいです。ぼくは基本、旅をしながら写真を撮り、世の中に発表しているのですが、まずはなぜ写真を撮りだし、そして映画祭にたどり着いたかお話しします。
20年以上前、自分の故郷である逗子以外のもっと外の世界を知りたい、という好奇心に駆られ、「後進国と先進国」をテーマに、インドを回り、デリーからパリに渡ってオランダ、スペインといったヨーロッパの先進国を旅し、それからまたインドに戻って、という本当にカメラだけのひとり旅を1年くらいやっていたんです。25歳くらい、2000年ころかな。
中山:大学を出て就職はしなかったんですか?
志津野:就職というものを未だかつて経験したことがなくて。大学出たらサーフィンに没頭しちゃって、その頃は写真で食べていく気もなくて、行き当たりばったりで舞台の裏方とか日雇いの仕事を拾って生きていました。
それで、インドに降り立つとすぐに、4車線くらいある広い高速道路をたくさんの羊が動物優先って感じで歩いてる光景に出会い、なんでこんなところに羊がいて、通り過ぎるのを車のほうが待つんだろうって、いきなりカルチャーショックで。逗子では見たことのない光景に初日から心奪われ、それからどんどんインドの魅力に引き込まれました。ラジャスタンという砂漠のまちを1週間くらい、ラクダとロシア人とアメリカ人と一緒に歩いたりもしていましたね。

そんな写真の旅から自分の田舎である逗子鎌倉の世界に戻って見ると、ちょうど仲間が精力的にSOLAYAという遊び場をつくっていました。写真の旅の熱が冷めないうちにそこでみんなに旅の話をしたりして、それ以来、そこに住み着き、男4人くらいで共同生活をはじめました。ただ、まあ色々あって、それもやがて解散をして、じゃあ独立しようということになったんです。
ぼくは写真家として、自分自身でどうやって食って行くか、インドで撮ってきた作品を実際にどう出して、どうセルフプロデュースし生計を立てて行くかを考えましたし、鎌倉の風景も撮りはじめました。江ノ電という電車から見える鎌倉の日常の風景を、本当に毎朝、同じポジション、同じフレーミングでひたすら撮ったりしていました。

それで、2007年ごろかな、サーファーの仲間と「WAVEMENT」というツアーをしたんです。 青森県の六ヶ所村の核燃料再処理工場を撮ったドキュメンタリー映画があって、それを逗子の公民館を借りて見ました。そのころぼくら原発のこととか全然わからないし「「これって日本の話? 本当にこんなのあんの?」という話になって、「実際に目で見ないとわかんないから直接見に行こう」って、鎌倉でサーファーとかミュージシャン、アーティストとかが集まって旅に出たんです。
廃棄物を海に垂れ流すならそれはぼくらサーファーにとって大きな問題だし、実際どういう影響があるのかわかんないままサーフィンしていいのかとか、じぶんの子どもに「海に入っていいぞ!」って親として言えるのか、と思って。
中山:逗子でそのドキュメンタリー映画を見たサーファーの仲間で「六ヶ所村行ってみようぜ」って、ボードを持ってその場所に向かって行ったということでしょうか?
志津野:映画でインタビューされていた方の話も、実際に自分たちの耳で直接聞きたいと思ったし、そこがどういう風景で、どういう状況になっているのかっていうことをみんなで実際に見ないと、自分たちの言葉では言い表せないだろうということで、事実を知りに行くという感じでしたね。

チームをつくって車4台で千葉から北上し、各県でローカルのサーファーのネットワークを使って地元の人たちを集めて、スクリーンとテントを張ってトークやライブをやったり。その中で、みんなでお互いの意識を確認していくというか、お互いの目を見て話すというような旅を、最終ゴールの青森まで2週間かけてやりました。
これがひとつのターニングポイントになったのは間違いなくて、どうやって自分たちが楽しみながらも社会に適合して生活していけるのかということを、みんなで考えるような出会いと経験をしたんですね。このときのメンバーが、現在の「CINEMA AMIGO」とか「CINEMA CARAVAN」の主力メンバーになっていくんです。
仲間が集まる「CINEMA AMIGO」
そして「逗子海岸映画祭」のはじまり
志津野:10年前に「CINEMA AMIGO」という「映画館」兼「事務所」兼「仲間が集まる基地」みたいなものを立ち上げました。たくさんの旅をしてたくさんの写真を撮ってきましたが、光と陰というか、綺麗な世界というか、外に出そうとするとみんな綺麗ごとになるけど、その反面、やっぱり見せられないものや隠されているものもあります。そういうものを写真として撮っても世の中に出せない様々な事情がある、というのがイヤになって、自分の責任で表現できる場所、自分たちの管理のもとで、さっきのWAVEMENTの仲間と活動できる空間を、ビジネスも含めてシェアしていこうと考えたんです。
海沿いにちっちゃい部屋を事務所としてただ借りるより、写真や映像表現をしているぼくとしては、その方が自分の作品も流せるし、みんなが集まって大衆的に楽しめる場所のひとつになればいいという感じですね。「アミーゴ」という名前の通り、本当にいろんなジャンルの人がボーダレスに集まれるような、隣の畑との垣根を越えるものにしたかったし。映画を切り口にすれば、写真、映像、ダンス、食、ことば、歴史、娯楽とか、いろんなものの可能性が広がると思いました。
中山:逗子の住宅街にある、ちっちゃい住宅を改造したその映画館に、ぼくも何度か行って映画を見ました。20人ぐらいで満席になる小さな映画館なんだけど、毎月のプログラムもカタログもちゃんとあるし、すごく社会性のある映画を選んで上映してましたし、けっこう有名ですよね。
志津野:ここを10年くらい地道にコツコツやってきましたから。 運営はパートナーにやってもらって、ぼくは外で遊んだり、旅に出ながら、写真を撮ったり、インスピレーションをもらって。
で、そこから「逗子海岸映画祭」とか移動式映画館である「CINEMA CARAVAN」っていうものが生み出されていくわけです。 CINEMA AMIGOの目の前が海なので、「この風景を活かして何かできないかな」と思って、逗子の市役所に行って、どうやったら海岸をオフィシャルで借りられるか相談に行ったんですが、まあ、妄想でしかない話なので、ようやく窓口を見いだすまでには、役所でずいぶんたらい回しになりました。
まだCINEMA AMIGOができたばかりで、世間に知られてもいないし運営もうまくいっていないタイミングなのに、映画祭なんていう大きなプロジェクトをこの時期にやるのか?という状況でしたが、やりたい衝動に駆られて一気に突っ走って、海岸にスリクーンを立てて、第1回逗子海岸映画祭をやりました。このスクリーン倒れたらどうするんだろう?っていう不安を抱きながらでしたけど。

中山:海岸の砂浜に立てたスクリーンで映画を上映するわけだけど、その周りにはいつも信じられないぐらい面白い店とか、めちゃくちゃ工夫された美味しい食のあるお店がいっぱい並んでいる、本当に素敵な映画祭ですよね。
志津野:逗子海岸にゼロから材料を集めて、会場も、サインも、チケットブースも、売っているものも全部じぶんたちで手づくりしています。もう、ひとつの村をつくるくらいのイメージですよね。そいうことを10年近くかけてやってきて、ようやく今では海外からも仲間が駆けつけてくれたり、10日間で2万人弱が来てくれるくらいになりましたね。
中山:最初はたらい回しになった映画祭が今では逗子の名物として人を集めているから、市の人も喜んでいるんじゃないですか?
志津野:そうですね、最初は怪訝な顔をされましたけど、今は本当に喜んでもらっています。 まあ、でも、風が強くてスクリーンが切れだしちゃって、裏で20人ぐらいがスクリーンを必死に支えながら修復作業したり、風を軽減させるための突貫工事を始めたりとか、そんなこともありましたけど。
中山:映画祭のときは必ずっていうくらい風が吹いてるんですよね。

志津野:もともと「Play with Earth」って言って、単純に外で遊ぼうっていうことを謳っているので。風が吹いても、雨が降っても、よほどでない限りやります。
中山:その逗子海岸映画祭と同時に、世界中を旅して回ろうぜっていう「CINEMA CARAVAN」も始まったんですか?
志津野:もともとCARAVANとして回るつもりで映画祭をはじめているんです。けど、はじめに骨組みを地元でつくる必要があったので、まずは目のまえの海でかたちにしようぜって言って、逗子海岸映画祭をやりはじめたわけです。だから、逗子海岸映画祭は、CINEMA CARAVANの「逗子編」みたいなものですね。
中山:映画文化のための映画祭ではなくて、映画という「ひとつのスクリーンをみんなで見つめるってところから関わりが始まる」というのが雷くんの狙いなんでしょうか?



志津野:そうです。もちろん映画は大好きなので、見て笑ったり泣いたりっていう日もあるけど、それだけの10日間だと映画を伝えたいだけになってしまう。自分たちはどういう経験をしてきて、どういう動きをして、どういうことを考えているのか。それを共有する場というのが軸にあるんですね。
中山:サーファー、映画オタク、スケートボード、パンを焼いている人、ラッパを吹いている人、サンドイッチ屋さん、本当にいろんな人が集まっているし、雷くんはいつも仲間の話になるんですよね。
志津野:サーファーはサーファー、スケーターはスケーター、ミュージシャンはミュージシャン、パン屋はパン屋という考え方より、表現は違えどやっていることは一緒だって常々感じるんです。別々の業界の垣根なんか壊しちゃえばいいし、出会った仲間たちをひとつに引き合わせるイメージというか。
ぼくの場合は、本当に仲間ありきというか、これがぼくの財産という感じで、全てそこからストーリーがはじまっています。彼らがいなくては、映画祭も、ぼくの存在価値もないだろうというくらい支えられていて、彼らこそ映画のなかのストーリーをつくっている人たちというか、まっすぐで裏もないような彼らにこそ、これからの社会ではどんどん表に出てきてほしいとぼくは思っているんですけどね。
中山:みんな各々ちゃんと手に職を持って生きているんだけど、この場所に本心から望んで集まっているわけですね。
志津野:そうですね、それがこの映画祭のボーダレスな雰囲気をつくり出していると思います。こういういろんな大人たちが集まり、本気でつくってるからこそ会場に滲み出る雰囲気というものが、多分よそとは違っているんです。つくっている側の想いや、これまでつくってきた自負や誇りが会場を支配していって、それをお客さんは自然と察知してしまうんですね。
志津野雷 Rai Shizuno/1975年生まれ鎌倉育ち。東京工芸大学芸術学部写真学科卒業 幼い頃より自然に囲まれ、いつしかその尊く美しい様子にファインダーを向け始める。近年、活動の場を国内外に拡げ、訪れた場所の背景にある文化やそこで暮らす人々に着目し独自の視点で写真を撮り続けている。ANA機内誌「翼の王国」等雑誌、Ron Herman等広告撮影の他、現代美術作家栗林隆氏、騎馬劇団『ZINGARO』ドキュメンテーションの撮影などARTISTとのコラボレーション制作にも力を注ぐ。2016年には初の写真集「ON THE WATER」を発表。移動式野外映画館『CINEMA CARAVAN』を主宰し、国内外で活動するなど、その活動は写真家の域を超えて多岐に渡る。https://www.raishizuno.jp/
中山ダイスケ Daisuke Nakayama/1968年香川県生まれ。現代美術家、アートディレクター、(株)daicon代表取締役。共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002年まで5年間、ニューヨークをベースに活動。ファッションショーの演出や舞台美術、店舗などのアートディレクションなど美術以外の活動も幅広い。山形県産果汁100%のジュース「山形代表」シリーズのデザインや広告、スポーツ団体等との連携プロジェクトなど「地域のデザイン」活動も活発に展開している。2018年4月、東北芸術工科大学学長に就任。