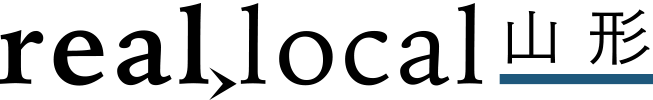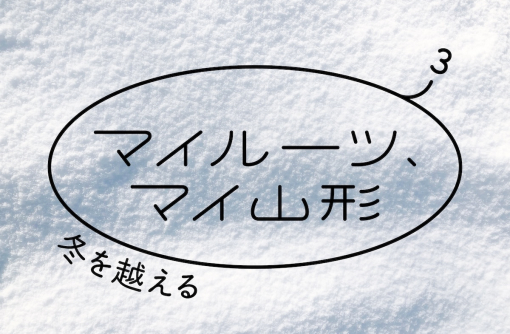中山ダイスケ × 仲西祐介【前編】/ぼくらのアートフェス5
2018年、東北芸術工科大学では全国で展開されているアートフェスのディレクターとともにフェスの魅力と可能性を探る「ぼくらのアートフェス」というトークシリーズを開催。今回はシリーズ第5回の模様(前編)をお伝えします。

中山ダイスケ(D):今回のゲスト、仲西祐介さんです。
仲西祐介(Y):こんにちは、よろしくお願いします。
D:仲西さんは KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭のディレクターをされています。この「ぼくらのアートフェス」という対談シリーズは、小さくて面白いアートイベントのディレクターをお呼びして話を聞こう、という趣旨で開講しているのですが、KYOTOGRAPHIEはもはや全然小さくないですよね… 2018年の来場者数はどのくらいだったのでしょうか?
Y:18万人ちょっとです。
D:18万! 仲西さんは2013年に第1回を立ち上げ、これだけ巨大なイベントにまで育ててこられたわけですが、そもそもなぜ京都で、なぜ写真に特化したフェスなのでしょう?
Y:きっかけは3.11東日本大震災です。そのときまだ東京に住んでいたぼくは揺られながら、これで世の中がひっくり返るんじゃないか、と思いました。でも、震災後いろんなものが変わると思っていたのに、まるで何事もなかったかのようにフタをしようとする人たちの勢いのほうがもっとずっとすごかった。
福島の事故に対しても、メディアはコントロールされ、今の日本で何が起きているのかすらわからない状態でした。だから、自分たちのメディアをつくらなければと思いました。日本で起きていること、世界で起きていることをきちんと伝えるメディアをつくるためにアートフェスティバルをやろう、と。

D:震災をきっかけに、自分が発信するメディアとしてwebメディアを立ち上げた人もいたし、新聞をつくった人もいた。けれど、フェスをつくる人はなかなかいませんよね。自分は一歩引いて、表現者たちを表に出していこうと思ったのには何か動機があったのでしょうか。
Y:例えば腐敗した政治に対してデモをするというようなことを散々やってきたけど、それでは何も変えられなかった。そうじゃなくて、価値観をひっくり返すようなことをやらなければいけない。アートの力でもっとこっちの方がいいよ、という新しい価値観を見せていかなければ、と思いました。
震災以降、大友良英さんみたいなアンダーグラウンドでやっていた人がいきなりメジャーになったり、坂本龍一さんみたいにメジャーな人がアンダーグラウンドを活動の場にしたり、ということが起きていました。今ではもうその辺りのカテゴライズにはあまり意味がないような感じもありますが、ぼくらが若い頃というのはアンダーグラウンドな世界にこそ才能あるアーティストが結構いたわけです。そういうアンダーグラウンドな才能を上に引っ張り上げてくるというようなことを通して、価値観をひっくり返すようなことがしたいと思ったんです。
D:なるほど。

Y:それからもうひとつ。中山さんはよくご存知だと思いますけど、日本のアーティストってなかなか世界に出て行けないんですね。語学の問題もあると思うけど、この島国から海外へ出て行こうと意識しているアーティストがそもそも少ない。それでも今は世界中にフェスティバルがあるから、そこで新しい作家を見つけた海外の人たちが「君ちょっとうちの国でもやってみないか」とか「うちのギャラリーでやらないか」とか「うちの国で出版してみないか」という話になっていくわけです。
D:ええ。
Y:けれども、日本にはそういうプラットフォームがない。日本のアーティストが海外に出られない理由はアーティスト自身のせいだけではなく、環境のせいでもあるんです。ぼくがそのことを強く感じるきっかけになったのは、南フランスのアルルという街で開催されている国際写真フェスティバルに足を運んだときでした。
1970年から続くこのフェスは、まだ文化として認められていなかった写真のフェスとして誕生し、それ以来、長い時間をかけて写真の面白さを伝え、文化を醸成させてきました。そこからやがて写真蒐集のコレクターが生まれ、20年くらい前にパリフォトという「フェア」が誕生するまで至ったわけです。
D:アート作品を売るイベントが「フェア」で、ビエンナーレなどの「フェスティバル」はどちらかというとアーティストの紹介のイベントですね。
Y:そうです。この南フランスの小さな街であるアルルのフェスティバルに、世界中からアート関係者が集まってきて情報交換をしています。「今こういう面白いアーティストがいるよ」とか。でも、そこに日本人はほとんどいない。いないから話題にもされない。みんな知りたいと思っていても、尋ねる相手もいない。そんなところにたまたま足を踏み入れたぼくは「今、日本にはどんなアーティストがいるのか」とか「日本のアーティストはどんな作品をつくっているのか」ってたくさん聞かれたんです。それで、日本にもこういうプラットフォームが必要だと感じました。
それでも自分でやろうとは全く思ってなくて、いろいろな人に「ああいうフェスティバルやってください」ってお願いしたけど、誰もやらない。それもそのはずで、フェスって入場料収入が基本で儲かるものではないので、やりたがる人なんていないんですね。
D:海外では国とか市がお金を出してやるんでしょうし、山形ビエンナーレも大学でやっているからやれているけど、個人ではちょっとムリですよね。
Y:そうなんです。そうなんですけど、ぼくらはどうしても今メディアをつくらなくてはいけないし、日本のアーティストをどんどん海外に出していかなければならない、という想いが強かったんです。
=====

D:KYOTOGRAPHIEの第1回は、どうやってはじめることができたんでしょう。
Y:日本でアートフェスをつくるときには地方自治体と一緒にというのが普通です。ボードメンバーに知事や市長がいて、そこに商工会議所とか地方の大会社の社長さんが並ぶ感じ。でもKYOTOGRAPHIEは、ぼくとルシール・レイボーズというフランス人写真家のふたりだけで始めました。京都に誰も知り合いもいなくて、お金も一銭もないところからのスタートです。
ぼくらは原発の写真も展示するし、戦争反対のメッセージも打ち出すし、社会問題や環境問題や差別の問題などもすべて取り扱います。それでもいいと言ってくださる企業や個人のスポンサーからだけ寄付をもらい、それで運営しています。内容に口出しされないために、そして自由を守るために、行政のお金はほとんどもらわずに今までのところなんとかやっています。
D:そのポリシーをずっと貫いているわけですね。今となってはフェスは有名になって18万人以上動員するまでになったわけですが、実績もなにもない1回目にどうやって展示場所となる京都のお寺や施設の方々を説得できたんでしょう。
Y:例えば、ある作家の写真をどうしてもお寺の襖にして作品展示がしたい、ということになったとします。それでぼくは京都にある世界遺産のような寺院を訪ねていくわけですが、どこの馬の骨かわからない男が突然現れて「貸してください」って言っても、まあ貸してくれないですよね。だから、有力なルートから紹介してもらったり、やらせてくれそうなところをひたすら聞いて回って探し出すわけです。

D:国の文化財とか保護された建築物を使う許可をもらうのだって大変ですよね。しかもお寺に来る人と写真展を見に来る人ではまたタイプが違うわけで、写真展となればリュックを背負った若者がお寺にガンガン入って来るわけで、そうしたところの管理もしっかりやらないといけない。貸す側のお寺だって勇気がいりますよね。
Y:そうなんです。そういう場合は、ちゃんと入口で全部リュックを置いてもらうようなルールにしたり工夫しながらやりました。それに、展示に必要な造作物も日本の建築に合うものにしようと、和紙に写真をプリントして襖に貼り込んだり、写真で掛け軸をつくったり。
「普通の美術館ではやらないような展示を」と思っているので、最初から赤字覚悟で、だいぶブッとばしちゃったんですよね。たった1回で終わってしまうようなイベントにはしたくなかったし、1回目から大きな影響力を持つものにしたかったから、予算はないけど頑張った。PRにかけるお金もないから、デザインの力だけで人の目を引くようなやり方を考えたり。
D:それはどのような?
Y:屋根付きのバス停をつくっている会社に交渉に行って「KYOTOGRAPHIE会期中の京都・大阪・神戸のバス停の広告スペースを全部あけてそこにポスターを貼らせてほしい」とお願いしたり。あとはJRとか地下鉄とか、デパートのショーウィンドウにも。
ぼくの場合は正直に「お金はないけど、これをやるためにはこの場所が一番効果的だからここにポスター貼らせてください」ってお願いするんです。断られても何回も交渉に行く。「このまえ断りましたよね」って言われたら「え、そうでしたっけ?」って言って、向こうが「もうしょうがないや」っていうぐらいまで行くと、だいたいOKをもらえますね。
D:にわかに信じがたい、すごい交渉の仕方…。しかも、相手は京都の人でしょう?
Y:そう。それでも、公共の場所をうまく使わないわけにはいかないから。これは「そもそもなんでこのフェスティバルをやるのか」っていう原点に常に立ち返らざるを得ないところですが、それは「世界に発信していくためには京都しかない」ってことなんです。
D:そうか。世界に向けた国際的なフェスをつくりたかったら、京都でやるのが一番だと。

Y:そう、「東京よりも京都なんです」と。そう言われて京都の人は悪い気はしないですよね。しかも、写真祭ではあるけど、フレームに写真を入れてそれを壁にかけるような一般的な展示はほとんどしません。普段はアート作品を展示しないような場所をあえて使ったり、会場と作品とが融和するような空間をつくったり、古い町家の新しい活用の仕方を提案したり、建築家のデザインとか伝統工芸の職人の技とか、企業の最先端テクノロジーも合わせて、街全体でアートを見せていくということに挑戦していますから。
決して「町おこし」ではないんです。ぼく個人としては、アートフェスで町おこし!という考えはアーティストに失礼だと思うんです。だって、町が経済的に潤ってきたらお役御免ということでしょう?そうじゃなくて、ちゃんと「ぼくらのフェスティバルはこういうことのためにやってます」っていう目標やテーマはちゃんとつくった方がいいと思うんです。
=====
D:世界中からアーティストを呼んで1年スパンでやるのはものすごく大変だと思います。例えば、海外のアーティストにロケハンで来てもらって「あなたの会場はここです」ってあらかじめ見せて、イメトレしてもらうみたいなことをするのでしょうか。
Y:ぼくらは、アートフェスはアーティスト第一であり、アーティスト主体でなければならないと思っています。けれども他方で、ぼくらは行政主体でやっているアートフェスよりも予算のゼロがたぶんひとつ少ないなかで運営しているんですね。派手に見せてはいるけど、実際のところお金はないんです。
「この作家を呼びたい」と思ったアーティストと交渉する際、「あなたの作品をこの会場で展示したい」というのもぼくらの方で決めさせてもらいます。でも、ロケハンに来てもらう予算はありません。だから、スカイプとかで何回も何回も、会場のことや素材のことなどを打ち合わせします。
だけど、西洋のアーティストだったら、写真は決まった高さの壁にフレームに入れて掛けるのが当然と思っているので、そういう人に「あなたの作品を、お寺の床に置きたい」って言ったら「お前ナメてんのか!」ってだいたい怒り出しますね。そこから「いやいや、そうじゃなくて。日本っていうのは靴を脱いで上がる文化だから、ここは全く汚い場所じゃないし、むしろ掃除されててとても綺麗で、ちゃんと座って見るとどれほど素晴らしいか」みたいなことを延々と説明するわけです。
D:日本の文化の説明からするんですか。
Y:ええ、もう何回も、何回も。それで、開催の3日前くらいまでにはある程度大枠の空間をつくっておいて、作家が来てから最終的にその会場を仕上げるというプロセスを踏むようにしています。そうしてちゃんと展示してみると、アーティストはまず100%喜んでくれますね。

D:自費でロケハンに来ちゃう作家さんもいるのでは?
Y:ええ、います。作品も日本でつくっちゃう、という作家もいます。けれど、そういう場合には、少しこちらからも予算を出して長めにステイしてもらって新しい作品を作ってもらうようにしていて。ぼくらはやっぱりアーティストが喜ぶことをやりたいし、町が喜んでもアーティストが疲弊してしまうというのではダメだと思っているので、そこは気をつけています。
中山ダイスケ(Daisuke Nakayama)/1968年香川県生まれ。現代美術家、アートディレクター、(株)daicon代表取締役。共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002年まで5年間、ニューヨークをベースに活動。ファッションショーの演出や舞台美術、店舗などのアートディレクションなど美術以外の活動も幅広い。山形県産果汁100%のジュース「山形代表」シリーズのデザインや広告、スポーツ団体等との連携プロジェクトなど「地域のデザイン」活動も活発に展開している。2018年4月、東北芸術工科大学学長に就任。
仲西祐介(Yusuke Nakanishi)/1968年生まれ、京都在住。照明家。世界中を旅し、記憶に残されたイメージを光と影で表現している。映画、舞台、コンサート、ファッションショー、インテリアなど様々なフィールドで照明演出を手がける。アート作品として「eatable lights」「Tamashii」などのライティング・オブジェを制作。また原美術館(東京)、School Gallery(Paris)、「Nuits Blanche」(京都)でライティング・インスタレーションを発表する。2013年よりルシール・レイボーズと共に「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」を立ち上げ主催する。
https://www.kyotographie.jp/