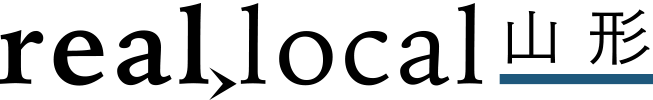地域企業のクリエイティビティとは?(Q1プロジェクト)/フォーラムシネマネットワーク専務取締役 長澤純 × アイハラケンジ(前編)
映画分野でのユネスコ創造都市に認定された山形市が、第一小学校旧校舎をクリエイティブ拠点として再整備することをめざす「Q1プロジェクト」が動き出しています。その連動企画であるこのシリーズは、地域のユニークな企業経営者の方たちにお話を伺い、山形の企業に蓄えられているクリエイティビティとそのポテンシャルを探るというもの。
今回ご登場いただくのは、山形の映画文化を牽引してきたフォーラムシネマネットワークの専務取締役 長澤純さん。聞き手は、Q1プロジェクト・ボードメンバーのひとりであるアイハラケンジ 東北芸術工科大学准教授です。

アイハラ:フォーラムは、市民出資による市民の映画館と呼ばれています。その設立の物語からお聞かせください。
長澤:フォーラム立ち上げは、私の両親の話です。
山形大学工学部の学生だった父と米沢女子短期大学の学生だった母は、父が主宰する映画サークルで知り合いました。大学卒業後の父には映画がやりたいという想いがありました。平日の夜にだけ映画好きな仲間と見る映画館、といったようなイメージだったようです。
大学進学率が高くはない時代に農家の次男が大学に通うことは非常に珍しいことで、工学部を出たら企業のエンジニアに当然なるものと周囲が思っていたところに父が「映画をやりたい」なんて言ったことで祖父に激怒され、二度と帰ってくるな、と勘当されます。
それで、仙台にあった大きなチェーンの劇場に就職し、半年ほど働いた後、福島県にある原町文化劇場という赤字映画館への転勤を命じられます。客席にトイレの臭いが充満したり、椅子からバネが飛び出していたり、プログラムの大半がピンク映画だったりと、いまにも潰れそうなほど悲惨な状況だったその劇場で支配人をやり、映画館経営を実践的に学びながら3年かけて立て直します。

収益が上がるようになると「このままだとウチが潰れる」と危機感を抱いたライバル館からの申し出により、その劇場は買い取られることになりました。それで支配人でなくなった父は山形に帰ることを決意し、当時まだ3歳だったかわいい孫…私ですね、の力を利用して、祖父に勘当を解いてもらいました。映画に対する情熱が並大抵のものではないことも理解してもらえたのでしょう。
地元に戻った父は、山形県映画センターという組織をつくります。あちこちの公民館や市民会館のような場所を借り、そこに映写機とスクリーンを持ち込んで上映するという、移動上映を行う事業者です。
父はそれを仕事としながら、「山形えいあいれん」という自主上映サークルをつくります。みんなで会費を払って、みんなで集まって、みんなで運営を分担し、週に一度の上映会をやるようになります。旅篭町にあるビルの3階フロアの片側を映画センターの事務所に、もう片側をえいあいれんの上映会に使いました。
みんなが集うその場所は「フォーラム」と呼ばれました。いつも誰かが遊びに来ては用事もないのにおしゃべりしたり、次はなにやろう? これやろう! みたいなことを言ってたり、チラシをつくったり、機関紙をつくったり、フィルムをカラカラ回して映画を見たり、終わったら感想を言いながらお茶会をやったり、という場所でした。
アイハラ:映画好きが集まって自分たちの見たい作品を見るそのサークルが、フォーラムの原型だったわけですね。
長澤:そうです。5年ほどすると、自分たちの劇場を持とう、という流れになるのです。当時、35mmのフィルムはいわゆる興行つまり映画館の世界のモノだから一般の人には貸さないという商習慣がありました。映画館の収益を圧迫してしまうから、という理由です。
でもそこをなんとか貸してほしいと配給会社に相談したら「それならあそこの映画館を通してくれ」という話をされたのでそこへ行ってみると「うちの映画館を貸してあげるけど、その代わりチケットこれだけ売って来て」って凄いノルマを課されて、ヒィヒィ言いながら散々苦労して売ってきたというのに、おいしいところは全部その映画館側に持っていかれた、みたいな事件が起きた。えいあいれんの仲間たちは憤慨して「こんなことなら自分たちの劇場をつくろう!」という機運が高まったのです。
「映画館経営に必要なのは仲間とお金とノウハウ」と考えていた父には、えいあいれんの仲間もいたし劇場経営のノウハウもありましたが、お金はありません。そこで苦肉の策として考えついたのが「市民株主」という方法です。「一口30万であなたも株主になりませんか?」と言って市民からお金を集めることにしたのです。
アイハラ:いまでいうクラウドファンディング、ですね。
長澤:そうです。実際、株主として出資してくれたのは20人ほど。やはり20代や30代くらいの若者には30万円というのはハードルが高いですからね。それでも「出資はできないけど会員にはなるよ」って言ってくれた人もたくさんいて、結局1,500万円を集めました。会員というのは10万円の会費を出すと10回分の映画チケットが10年間もらえます、というものです。えいあいれんの活動を一緒にやってきて支えとなってくれたコアなメンバーもいてくれたし、また、若者たちが自分たちの手で映画館をつくろうとしているなんて珍しいことだったから、新聞も面白がって好意的に取り上げて書いてくれたりもしたようです。

実際のところ、建設と設備にかかるお金は1億円近くもかかるものだったので当然それだけでは足りず、父は現在の日本政策金融公庫から借入をしました。そのとき祖父は自分の田んぼを抵当に当ててくれました。祖父の応援があったから、父はこの事業をやることができたのです。ただ、実はこのときの抵当に、実家の田んぼだけではなく妻の、つまり私の母の実家の敷地も家屋も入っていました。
父は次男で、実家には長男がいたので、もしこの事業が失敗したら、自分の家族だけでなく、実家も、田んぼも、実家にいる兄とその家族も、さらには妻の実家まで全員路頭に迷うことになる。ふつうならやめますよね、そんなこと。でも、それをやってしまうのが父の恐ろしいところです。失敗を考えない。絶対うまく行く、としか考えないのです。
アイハラ:なんともすごい話です。そしていよいよフォーラムがオープンするわけですね。
長澤:大手町にできた初代フォーラムは97席と48席という2スクリーンの映画館で、上映作品は『未知との遭遇』と『ひまわり』でした。オープン日の1984年7月25日、お客さんが殺到しました。
この頃の映画館というと映画を見ながら食べるのも飲むのも常識で、空カンがカランコロンとコンクリートの床をどこまでも転げ落ちていくなんていうのがふつうでしたが、フォーラムは劇場内飲食禁止としました。さらに床はすべてカーペット敷きにして足音も響かないようにし、すべての椅子に傾斜をつけてスタジアム形式にするなど、現在のシネコンみたいなことを今から30年以上も前のこのときにすでに採用していました。すべて、映画に集中してほしいから、という理由によるものでした。この斬新さが非常にウケまして「映画好きならフォーラム」というブランドが確立されていきました。「半年で潰れる」なんて言われながらも、お客さんは入ってくれました。

アイハラ:「潰れる」と言われていたなんて、現在のフォーラムからは想像がつきません。
長澤:「すぐ潰れる」とか「絶対にうまくいきっこない」とか、周りからの声にはすごいものがありました。表向きには「市民出資による市民の映画館」の物語として非常に夢のあるいい話として語られることも多いですが、実際は綱渡りの連続で、本当に「運良く乗り切った」という感じでここまで来ているのです。
例えば、同業他社からの圧力で、興行組合からフォーラムが突如除名されるという事件が起きたこともありました。配給会社に「フォーラムを除名したので今後一切フィルムを出さないように」という通達を出され、潰されかけたり。幸いにもこのときは当時一番強い力を持っていたUIPという配給会社が味方について、フォーラムへの協力を表明してくれました。「インディ・ジョーンズ」や「バック・トゥ・ザ・フューチャー」といった人気作品を数多く持っていた会社だったので、私たちはなんとか生き残ることができたのです。
アイハラ:配給会社や映画ファンの会員に支えられ、厳しい状況をくぐり抜けて来られたわけですね。
長澤:そもそもフォーラムをつくるときの最初の目的というのは、ふつうの映画館ではなくて「東京でしか見られないような作品を山形で見られるようにしよう」というものでした。
当時というのは本当に東京でしか見られない映画がたくさんあったのです。どうしても映画が見たいなら東京まで特急で… まだ新幹線がない時代ですからね、出かけて行って、一泊二日かけて見てくる、というようなことをしなければいけなかった。
だから例えば、東京で大学時代を過ごして山形に戻ってきた人のなかには、映画が全然見られなくて非常に困った想いをされていた方がいて、ものすごく映画に飢えているわけですね。そんな状況だったから、アート系作品を上映すると「山形でこれが見られるのか!」とすごく感動してくれるわけです。
とはいえ、父は映画館運営の経験から、アート系映画の上映だけでは十分な収益を上げることは厳しいだろうと考えました。商売としてちゃんと成立するような仕組みにする必要があると考えた結果、アート系とロードショー系の両方をやることにしたのです。それによって集客を確保し、経営を安定させようとした。
アート系とロードショー系をごちゃ混ぜにしたプログラムにするというこのやり方は、現在のフォーラムにまで息づいています。この「ごちゃ混ぜ感」こそが私たちにとって非常に重要なファクターです。アートとエンターテインメントのどちらをも楽しめるようなトータルな空間づくりが大事なのです。
フォーラムシネマネットワーク Webサイト
Q1プロジェクト Webサイト
2020.2.10
text : Minoru Nasu
photo: Haruko Miura