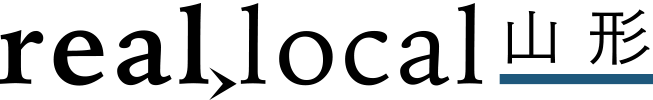此処から映画を作れるか?
映画の街に暮らす(2)
いろんな地域に出かけてその土地の人たちと仲良くなって各地の自主上映に映画を配給・紹介する仕事がめちゃくちゃ面白かった。映画館の仕事に戻らないかと幾度か言われたが、その度に即答で断っていたし、映画祭の専従にならないかとのお誘いも何度かご辞退したことがある。それぐらい、地域上映が面白かった。
この仕事にはルーティンがない。1日の予定は自分が決めるし、会うべき人たちの都合に合わせもするから、出勤時間も退社時間も固定されていない。動きが全てなのだ、人と会うことが全てなのだ。どうしても人と会いたくないときは、出先で空でも眺めている。そんな自己責任しかないような仕事が性に合って、うっかり20年も続けてしまった。(2003年に退職)
でも、一つだけ満ち足りていない感覚があった。
それは、誰かが作った映画を配給しているということ。映画館での商業的興行が難しい作品でも、面白い作品や上映する意義のある映画は世の中に沢山ある。そんな作品を映画館以外の様々な地域に配給し、その作品の生き場所を作り、自分たちも生活し、製作者に映画料を払い、映画の再生産をサポートする活動には大きな意義がある。地域の人たちばかりでなく、映画監督やプロデューサーや配給元とも繋がって映画の流通を新しく手作りするのだ。その仕事の面白さにハマればハマるほど、一方で、なぜ映画は他所から来るんだろう、此処から映画を作ることはできないだろうか、そんな気持ちが底の方に育って行くのが分かった。
じゃ、何をどうすれば良いのかという話になるのだが、そんな気持ちを持ち続けていると、不思議なことに、何故か映画を作りたいという人が時々近づいて来る。自分が山形に住みながらこの20年で幾つかの映画製作に関わって来られたのは、そうした稀人(まれびと)のような人たちとの幸運な出会いのお陰だったと思う。大抵そんな「此処で映画を作りたい」という人は、私たちが住み馴れてしまっているこの山形という土地を、ある意味、異邦人の感覚で視ていて、何かに気づいて見つけ直しているのだった。自分は、そんな熱を持っている人たちに何度か揺さぶられて来たと思う。そうだな、一緒に映画を作ろう、この人と。で、俺には何ができるかな。できることは何でもしよう。カメラを回すことだけが映画を作ることではない。もっと雑多で豊かなことだ。この映画を作る動きの中で、自分の足元に隠れている物語を掘り起こせるかもしれない、何しろ見つけ直しだから。ここから映画を作って此処に還していこう、そして遠くまで送り出してみよう。
そんな感覚を、実は、ずいぶん前に予習していたことを思い出す。
また少し、話が遡る。
確か1982年頃だったと思う。大学を出て山形に戻って来て3年ほど図書館司書をしていた。或る日、職場の先輩に誘われて旧・山形県民会館に「ニッポン国 古屋敷村」を観に行った。大学より映画館に通った回数の方が多かったような学生時代を過ごした割には、意識してドキュメンタリー映画と向き合ったのは、それが初めてだったような気がする。
三里塚で空港建設反対闘争と農民たちの生き様を記録して優れた映画を作り出していた小川プロの面々が、農民詩人木村迪夫の呼びかけに応えて山形県上山市牧野に移り住み製作した3時間半の長編記録映画。
腰が抜けるほど面白かった。急速に過疎化する農村を襲う冷害の仕組みを科学映画のように再現・解析する一方で、村に住み続けてきた人たちの生きた歴史を映してゆく。特に、長らく心に宿していたものを語る村の古老たちの表情や言葉にどんどん引き込まれた。限界集落に住む人たちの人生が、実は日本や世界や時代と繋がっていることを見通す視線。そして、古老達の実存感。
こんな凄い映画があるのか、これまで見てきたどの映画とも違うと感じながら、その作品が撮られたのは、自分が住んでいる土地からほんの数キロしか離れていない場所なのだということに独特なショックも受けた。古屋敷村の古老たちは特別な人たちではない、おそらく日本のどの農村にも居るだろう。いわば普通の農家の年寄りの人生と心の歴史と土着の語りが、こんなに普遍性を持ったものとして自分の身体に響いて来たことに驚愕せざるを得なかった。
俺たちは、こうした言葉や物語を聞き逃しては来なかったか、いや、聞いても耳を傾けずに切り捨てて来たのではなったか。分かった積もりの自分たちの生活、地続きの町や村々の底に、何かとんでもない、いや、ごく普通であるからこそ凄い物語りがあるということ。それに気づき、その現場の人たちと交わりながら掬い取ってくる作家の視点やドキュメンタリー映画というものの面白さを、突きつけられた気がした。
それから数年後、私は、市民運動で作られた映画館で働くことになり、そこで再び、『にっぽん国古屋敷村』と出会うことになった。しかも、それは、上山牧野で農業をしながら映画を作っていた小川紳介監督や小川プロの面々とのお付き合いの始まりでもあった。

つづく