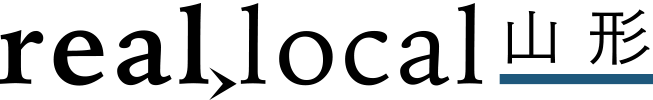「表現は、まず『見る』ことから」阿部宏慈さん/わたしのスタイル6
山形大学の教授や副学長を歴任し、この春に定年退職したばかりの阿部宏慈さん。フランス語とフランス文学の研究者である一方、写真や映画表現をテーマとする映像学も専門とし、さらに2020年3月には詩集も出版しています。
1989年に始まった山形国際ドキュメンタリー映画祭には第1回から観客として参加したり、映画館で学生に頻繁に目撃されたりするうちに、「映画好きがバレた」と笑う阿部さん。今は理事としてかかわる山形国際ドキュメンタリー映画祭のこと、映像や言葉を「見る」ことのおもしろさについてお話しいただきました。

通訳ボランティアを引き受けて
映像作家の視点を知る
阿部さんが山形国際ドキュメンタリー映画祭の運営側にかかわっていくきっかけは、フランス語圏からやってくる監督たちの通訳やアテンド役を依頼されたことでした。それは映画祭が始まったばかりの頃で、阿部さんも山形大学に着任して数年といった時期。頼まれてボランティアで参加するうち、教員である身分も自然と知れて、さらに頻繁に声がかかるようになったそうです。「続けられるのは、楽しい気持ちがあるからですよね。話す機会など滅多にないような作家たちとしゃべることができるのですから、それはやっぱり魅力的」と阿部さんは参加した理由を語ります。
海外からのゲストをアテンドするなかでは、映画をつくる側の視点に触れられることもおもしろさの一つでした。例えば、1999年のインターナショナル・コンペティション部門に出品された『アンダーグラウンド・オーケストラ』★では、撮影監督のエリック・ギシャールさんがゲストとして山形を訪れました。フランス語を話すギシャールさんのアテンド役を頼まれた阿部さんは、お店へ案内して一緒に食事をしたり、会場を案内したりと多くの時間をともにしました。そのなかで、作品をどうやって撮ったのか、どのような狙いがあったのかなど、作品づくりにおけるたくさんの疑問をぶつけたそうです。


あるとき、ギシャールさんと一緒に上映作品を鑑賞することになり、ロシア作家の作品を二人で観に行きました。作中でバスが停車したとき、道路にちょうどワシがいた場面について、鑑賞後に「あの偶然はすごかったね」と阿部さんが話しかけると、ギシャールさんは「あれは偶然とは言えないかもしれない」と答えたそうです。「つまり撮影監督の目から見れば、たとえドキュメンタリー映画であっても、撮影場所をどんなふうに選び、どのように準備していたかという視点で映画が見えてくるんです。山形のお店でお酒を飲みながらそんな議論ができるのだから、それは実に有意義ですよね」。
第1回山形国際ドキュメンタリー映画祭
表彰式における大ブーイングの体験
山形国際ドキュメンタリー映画祭は、そもそもドキュメンタリーをどのようなものと捉え、どんなふうに作品を選んでいるのか。それを知ることができるのが、この映画祭の企画段階からかかわってきた、東京事務局の矢野和之さんの次の言葉です。
長編のフィルム作品で、作者がドキュメンタリーとみなすものをすべて受け付けた。ドキュメンタリーというと、重い、暗い、退屈という固定観念があり、それをぶち壊そうとして、まず「映画」であることを第一に考えた。単なるレポートではなく、テレビ番組でなく、メッセージを伝えるだけのものでなく、啓蒙的なものでもなく……そこで出てきたのが、役者を使ったロードムービー『ルート1/USA』(ロバート・クレイマー)★、実験的な『プレーントーク&コモンセンス』(ジョン・ジョスト)★などで、招待作品には、『風の物語』(ヨリス・イヴェンス)、『僕は怒れる黄色』(キドラット・タヒミック)等々。ドキュメンタリーの映画祭でこのような作品群に接しられることに驚いた人は多い。(矢野和之「山形国際ドキュメンタリー映画祭の歩み」『東北学02 時空を駆ける、フィールドワーク』東北芸術工科大学 東北文化研究センター、2013年)

阿部さんもまさに、その驚いた観客の一人でした。ただそれは、作品そのものについてのみならず、会場での出来事にも圧倒されたと言います。上に挙がっているロバート・クレイマー監督作品の『ルート1』は、第1回のインターナショナル・コンペティション部門で上映されたものでした。作品を会場で観ていた阿部さんは、「これはダントツで大賞だろうと疑わなかった」と言います。ところが表彰式では、大賞ではなく次点の山形市長賞でロバート・クレイマーの名前と作品名が読み上げられました。その途端、会場からは悲嘆の大ブーイング。「大賞となった作品も、それはそれでいい作品だったけれども、私も『ええー!』って叫んだ一人。観客も研究者も、あとからみんなそのことを言っていたし、あそこで味わった共感と、場を共有するムードはすごいものでした。私はまだ山形に来て2年目くらいの頃でしたが、ああこんなことが起こるんだ、いいところに来たなって思ったんですよね」。

こうして見たい作品が連日上映されていたものの、見られない作品も多かったのだそうです。「そりゃあそうでしょう。私だって講義もあるし。今だって、みなさん時間もないし、忙しいし、見に行くのも大変なんですよ。そんななかで、会場の飾り付けをしてくれたり、商店街の人たちもポスターを貼ってくれたり、ずいぶん一生懸命やってくださって」。阿部さんは、映画を見ることと映画祭に参加することとは別のことだと言います。
映像からも言葉からも
作者の思いは「見る」ことができる
ところで、阿部さんは1993年に『プルースト 距離の詩学』という本を上梓しています。20世紀を代表するフランスの作家、プルーストの文学作品を、阿部さんは学生時代から研究してきました。自著のなかでは、長編大作『失われた時を求めて』において、プルーストが比喩によって喚起するイメージや、言及される写真的なイメージを読み解きながら、映像とそれを見る人の記憶や欲望との関係性を考察しています。本書のなかでは、写真について、次のように書いています。
したがって、写真を見ることは、一方では、撮影の瞬間からそれを見る瞬間にいたるまでに経過した時間を「見る」ことであり、ある意味では、過去と現在を隔てる時間的な(しかも不可逆的な)距離を確認することでもあるのだ。こうして、『失われた時』の主人公がバルベックの少女たちの古い写真に見出すのは、子供から少女へと、少女から女へと日々変貌し続ける娘たちの変化であるのだ。
写真という映像のなかには、普段は見えない「時間」を見ることができる。そして過ぎてきた時間を含め、映像に映し出されるものはどのようなものでも、それが現実に「かつてそこにあった」のだと見る人に伝えます。阿部さんは、映像学とは、そこに見えるものによって作品を見ることだと言います。作家の経歴や時代背景といった、作品の外側の見えないものではなく、作品そのものこそが、現実を映し出している。山形国際ドキュメンタリー映画祭で、時には演じられた作品もドキュメンタリーとして上映され続けてきたことなどは、そうした映像の捉え方とも重なっているように感じます。

映像を探求する一方で、詩も書き続けてきた阿部さんに、映像と言葉の関係性についても尋ねました。しばらく考えてから阿部さんは、映像表現と言葉の表現における共通点は「見えるものへの思い」だと答えました。「その思いを提示したいということは、共通していると言えるかもしれませんね。理屈で説明するのではなく、まず『見る』ことから始める。それは言葉もやはり同じです」。

現在の阿部さんは、米沢の大学にて教育に携わっています。大学運営を担う立場である一方、実際に講義も受け持っているそうです。「教員って、学生と接していないと、何かを失ったような気がするんですよ」と阿部さん。高校の図書委員が企画した読書会に、ゲストとして招かれることもあると言います。そんな話をして、「楽しかったですよ」と言う阿部さんの姿は、とてもうれしそうに見えました。


※文中で★印のついている作品は、山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーにて鑑賞することができます。詳しくはこちらを参照ください。https://www.yidff.jp/library/library.html