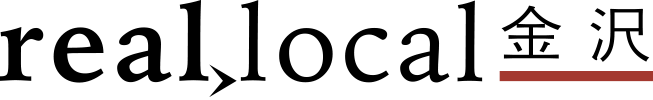金沢のまち・ひとを感じる一皿を。
『tawara』オーナーシェフ 俵徹也さん

飲食店が軒を連ねる片町のはずれ、土塀と石畳の街並みがはじまる長町武家屋敷跡の入口にレストラン「tawara」はある。繁華街の賑やかさからも、歴史ある街の重厚さからも程良い距離を保ち、ふと心が落ち着くそんな場所だ。

オーナーシェフの俵さんは金沢市生まれの39歳。27歳のときに勤めた和食店から料理の世界に入り、3年後には単身渡仏、レストランとホテルでフランス料理を学んだ。ヨーロッパでは地域の生産者が自らその時期に採れた食材を直接厨房まで運んでくる。日本にいたとき以上に、その土地の暮らしと食との密接な関係を感じたという。
帰国後、次の修業先として選んだのは、四季のはっきりしている京都。和食器、洋食器を織り交ぜた懐石風フレンチを提供する先駆け的な店「おくむら」でさらに経験を積んだ。3年ほど経った頃、自分ならこうしたいという思いが強くなり、金沢に戻ってこの店を開くことになる。
「地元だからというのももちろんあったけど、自分が思い描く店に必要なものが全部揃っているのが『金沢』だったから」。
豊かな食材と、器やしつらえで四季を楽しむ文化。そして、それを生む人や土壌が金沢にはあった。直接生産者のもとへ出向くこともあれば、イメージに合う器を求めて地元のギャラリーや骨董店にも足繁く通う。そこでの出会いが「tawara」の料理に表現されているようだ。

ここで食事をしたことのある方ならきっとその個性的な盛付けも強く印象に残っているのではないかと思う。それについて尋ねると、「フランスにいた頃によく美術館で見ていた抽象画の影響かも。彩りのために、味の構成として意味のないものを足すことに違和感があって。同じ色調の中に、味や食感でメリハリを出したり、食材そのもので色を入れるようにしたい」と俵さん。
作家ものの器はシンプルながら素材感があって、それを表現するのに合っているという。陶や漆、ガラス、金工など、食器や店のしつらえで使っている地元の工芸作家の作品は10種類以上。自然と骨董の器や洋食器よりもこちらを使うことが増えていった。


オープンして1年半。食材や器の作り手とより深く付き合う中で、俵さんは最近もっと「ここに暮らす人とその人がつくるもの」に焦点を当てた一皿を、と思うようになったそうだ。
「トマトはどこでも採れるし、いろんな人がつくってるけど、菊理農園の安田さんがつくるトマトはやっぱりほかとは全然違う。小松菜もくせがあって使いにくい野菜という印象だったけど、奥野農園の奥野さんがつくる小松菜はシンプルにスープにするとすごく美味しい。この時期にこの農園で採れるこの野菜で、というメニューをもっと増やしていきたい」。
金沢という土地とそこに暮らす人たちと共鳴しながら、俵さんの食の表現はますます深みを増していく。