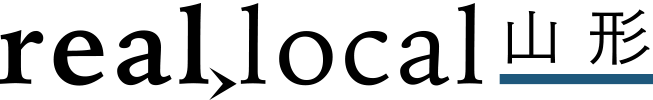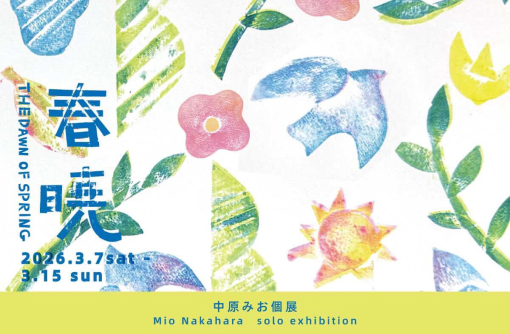はじめての「山形国際ドキュメンタリー映画祭」
※山形へ移住したライター中島による、山形で体験するはじめての出来事を記録するコラムです。アーカイブはこちらから。

正直なところ「山形国際ドキュメンタリー映画祭」と聞いてもピンとこなかった。
ドキュメンタリーだから豪華なドレスを着た俳優たちが登場するわけでもないし、レッドカーペットが敷かれるわけでもなさそうだ。2015年のカタログを開くと玄人向けな印象があり、地元の人に「映画祭ってどんな感じですか?」と聞いてみても、あまり明快な答えはかえってこなかった。
映画といえば、よくNetflixで見ているし、たまに映画館にも行くけど、それはほぼ劇映画だし、そもそも映画を語れるほどの知識はない。そんないち山形市民のわたしがこの映画祭を楽しむ術はあるのだろうか。
そんなある日、この記事から映画祭を楽しむ糸口を見つけた。ボランティアである。さっそくゲストサポーターに応募して、日本全国や海外からくるゲストに対応することになった。

10月5日の開幕日に山形駅でゲストたちを出迎え、ホテルのチェックイン、まち案内などを担当して、監督やプロデューサー、審査員を中心に多くの映画関係者と話す機会がもてた。
初日から深く実感したことがある。ドキュメンタリー映画の監督たちはとても物腰が柔らかく、思慮深く、気持ちがいいコミュニケーションをする方が多い。ドキュメンタリー映画では、一般人の日常や社会にカメラが持ち込まれる。監督たちの人柄に被写体は心を許し、ドキュメンタリー映画はつくれていくのかもしれない。

ボランティア参加の有無によらず、この映画祭は観客とゲストとの距離がとても近い。9つの会場をぐるぐるとめぐり、夜には香味庵で懇親会があるため、映画祭期間中は何度も同じ人たちとすれ違う。その中にはもちろん監督もいる。「あの人はどんな映像を撮るのだろう」と、人に興味がわいて映画を見に行くなんてこともあった。

この1週間でトータル9本のドキュメンタリー映画を見た。中国、アフリカ、インドネシア、アメリカ、ブラジルなど、この短期間で世界中を漂流して各地の景色を覗き見したわけだ。
それはときに、ある家庭の食卓だったり、ときには国を巻き込む社会運動だったり、不穏な空気もあれば、素朴な笑顔もあり、心も頭も振り回されて、正直、疲れた。しかしそれは大切に保管しておきたい感覚でもある。映画を見たあとはおのずと自分が生きる環境や自国について考えたりもした。

この映画祭は映画だけではない。ドキュメンタリー演劇、クラブでのアフリカンミュージックナイト、ドキュメンタリーレコードを聞く集い、シネマ通りの写真展、山寺ツアーなど、関連イベントが昼から夜まで目白押しだった。映画は見なくとも、イベントへの参加を楽しむ市民もいたようだ。

映画祭の盛り上がりを象徴するのが「香味庵クラブ」だった。最終上映時間の夜10時を境に映画ファンとゲストがいっせいに旅籠町の居酒屋〈香味庵 まるはち〉に集まる。三連休の金、土、日は格別に賑わい、店の外まで人が溢れかえっていた。
見ず知らずの人同士でも「今日はなにを見ましたか?」から会話がはじまり、深夜2時まで語らい、翌朝からまた映画を見る。どこまでも映画漬けな映画ファンや関係者たち。この熱気を体験するだけで、映画祭の楽しみがより立体的になる。開幕日から、あれよあれよという間に時間が過ぎていく。

11日には受賞作品が発表された。言葉を交わした監督が受賞して、自分のことのように嬉しくなるから不思議だ。
普段着で表彰台にあがる監督たちの背景には、作品にうつる景色と人々が見えた。
香港での学生デモを記録したチャン・ジーウン監督は受賞について、「嬉しい気持ちと同時に、デモによって逮捕され監獄にいる学生を思うと自分を恥じる気持ちもある」と話し、その率直な言葉でドキュメンタリーの精神に触れた気がした。なぜか泣きそうになった。

表彰式とさよならパーティーを終え、映画祭は無事に幕を閉じた。
表彰式では「山形の地域コミュニティによって実現しているこの映画祭は、ユネスコのお墨付きがなかろうと、創造都市山形の名を世界地図の上にしっかりと刻んでいる」と審査員のイグナシオ・アグエロ氏からの言葉があった。
ゲストたちは帰路につき、七日町大通りからパスをぶらさげた人たちが消え、いつもの日常へ戻っていく。今日からまた「山形国際ドキュメンタリー映画祭2019」への準備がはじまっていく。