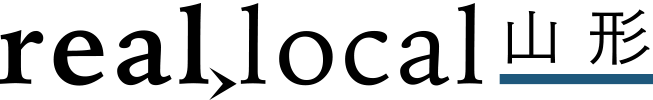中山ダイスケ × 宮本武典 × 三瀬夏之介 【前編】/ ぼくらのアートフェス最終回

左より、東北芸術工科大学 宮本武典教授、中山ダイスケ学長、三瀬夏之介教授
山形ビエンナーレ2018を特徴づけた
大学エリアとまちなかエリアの鮮やかな対比
中山:「ぼくらのアートフェス」最終回は、プログラムディレクターであり特に文翔館を中心としたまちなかエリアを担当された宮本武典先生と、「山のような100ものがたり」でキュレーターとして東北芸術工科大学エリアを担当された三瀬夏之介先生のおふたりと総合プロデューサーであるぼくと3人で、山形ビエンナーレ2018の振り返りをしたいと思います。
宮本:よろしくお願いします。三瀬さんは今回、アーティストとしてだけでなくキュレーターとして参加されました。新しい気づきや発見がありましたか?
三瀬:大学というのは学科があって、さらに細かなコースに分かれてまるで蛸壺みたいなところですが、キュレーションをやることでそれぞれに磨かれた個性がお互い手を握り合って領域共有型でやっているという手応えがありました。実際、文化財保存修復や絵画や映像の先生とディスカッションしてデザインの先生が配置していくのは、まるでひとつのバンドがセッションしているような感じでした。
宮本:ひとりで行う作家活動とはちがいますね。
三瀬:それが意外と自分が作品を作るときと似ているなって気がしました。ぼくが作品を作るときに最初にやるのは「開く」こと。水による滲みやボケ、見渡せないほどの大きさ、全然違うもののパッチワーク…、自分が制御できないノイズをすべて入れ込んでゴチャ混ぜにして、それを整理整頓し、最終的に閉じていくことで作品へと落とし込んでいく。「本当に自分が作ったのかな」って思えるようなものが立ち上がってくるのが理想です。今回もテーマに沿って展示物をあちこちから借りてきて、まずはむちゃくちゃ開いてみて、それらをまるで星座のように並べようとしたとき、作品を作るのと同じような感覚を持ちました。

中山:グラフィックデザイン学科のアイハラケンジ先生もこの「100ものがたり」の展示デザインに参加されましたが、わずかなミリ単位で展示物の高さを調整しつつひたすらモノを並べていました。彼の空間認知能力の高さに改めて驚いたし、その姿を見ていてとても愛おしい気持ちになりました(笑)
三瀬:そのミリ単位の配置が展覧会全体の気配になることを、手伝ってくれた学生も身をもって体験しました。膨大な物量を入れ込んで整理するという大変な作業の連続でしたが、みんなよく頑張ってくれました。
宮本:「100ものがたり」が展示された大学エリアと、山形の七日町付近で展開されたまちなかの展示とを対比的に見た人は多かったみたいです。
山形ビエンナーレについてInstagramで共有されていたイメージは、まちなかの展示の特に小さいものが多かった。確かに小さい玩具的な展示物が多く、瀬戸内国際のような景観を巻き込んだ巨大な作品はなかったですし。

中山:「せっかく山形に来たのに大自然と絡んでいる作品がない」という指摘はありました。大自然にどかーんと彫刻が出現するのを期待していたんでしょうね。
宮本:数千万円というお金をかけて大きな屋外彫刻を作るような他地域の芸術祭と、ぼくたちの芸術祭の個性は違うのかなと思いますけどね。
中山:小さく屈んで見るのが山形的かもしれないし、金銭的問題ではなく文化の違いではないでしょうか。
宮本:芸術祭の運営の側として、こんなことを意識した、ということはありますか?
三瀬:今回の山形ビエンナーレで主会場のひとつとなった「芸工大エリア」には、普段からアートに親しんでいる方だけではなく、地域の方々を含む様々な人々に来てもらいたいと思いました。もうひとりのキュレーターである宮本晶朗先生やアイハラ先生と話したのは、おじいちゃんおばあちゃんも楽しめて、学生も楽しめて、市民も楽しめて、かつアートのプロも楽しめるみたいな、全階層的な仕組みってないだろうか?ということでした。

そのために作ったのが、例えば『100ものがたりガイドブック』というブックレットです。中島彩さんという外部のライターさんやイラストで杉の下意匠室にも制作に入ってもらい、出品作家さんへの質問を通して絵本のようなタイトルとイラストをつけて、まるでものがたりのような作品への入口を作ってもらいました。

実際の展示では、キャプションの文字の大小で階層を作り、興味があるものについてはどんどんクリックしていくと深く掘れるような仕組みを作りました。ビジュアルだけ見ても楽しいし、「面白いな」と思えば掘りたいだけ掘っていける。そんな複層的な仕掛けを施すことで、誰に向けての芸術祭なのかという問いに応えたつもりです。
宮本:あのブックレットは従来の展示図録とはまるで違って「あれ自体が問いになっていてすごく面白かった」という声がありました。
中山:革命的なパンフだよね。
宮本:今回のビエンナーレでは、そうした大学エリアと、まちなかエリアとのふたつのエリアでそれぞれにアートを開いていき、その根っこは同じでも、それぞれ違う視点も提供していました。まちなかではデザイン系のソーシャルなプロジェクトが多かったし、芸工大エリアではもっと近代美術史的な視点から日本美術史を問い直す「研究」のようなことが行われていた。すごいコントラストがありました。
中山:両方があったことが面白いなと感じました。まちなかの方はカルチャー雑誌にどんどん紹介されていたし、大学エリアの方は美術評論で取り上げられていたし。その両方あってこそのビエンナーレだったし、そもそも「デザインとアートの領域を壊そう」っていうのがぼくらの課題でもあったわけですから。
三瀬:実は前回と前々回のビエンナーレのとき、ファインアートを学ぶ学生たちが自分の作る作品とビエンナーレの展示作品との間にあまり連結を感じられていない印象を受けました。その溝を今回のビエンナーレで埋めたいという思いはありましたね。
宮本:ぼくの方は逆に、これまでと同様に、軸をブラさず、芸術監督の荒井良二さんとスタートさせたことを育てていくっていう考え方でした。なので、これまでまちなかで培ってきた雰囲気をベースにしながら、大学エリアへと人の関心を流していくということをすごく意識しました。実際、まちなかから大学へという人の流れが今回はとても多かったような気がしています。
中山:ぼくの印象だと、大学を先に見てからまちなか行く人も多かったみたいです。時間的な流れとしても、お昼に山形に着いてまず大学エリアの展示を見てもらって、そのあとでまちなかに移動して歩きながら展示を見てもらい、夜のイベントに参加してもらって、そのままご飯を食べにいく、みたいな流れです。
ぼくら運営側としては「どのくらいの人がまちなかから大学に行ってくれるだろう?」って心配していたけど、実際の人の流れはけっこう予想とは逆の動きをしていたかもしれせんね。

山形を訪れたゲストたちの
対話と視点から振り返って
宮本:今回のビエンナーレには数多くのゲストも来てくださいました。この「ぼくらのアートフェス」という講義も、他地域のプロデューサーの方たちにゲストとして来ていただき、中山学長はそのゲストの方々と対話をされてきたわけですが、そうした方々の目に、山形ビエンナーレ2018はどのように映ったでしょう?
中山:地域のアートフェスのプロデューサーからお話をお聞きするという初めての試みを全5回シリーズとしてやってきましたが、彼らの多くに共通していたのは、そのまちを自分たちはこんなふうにしたいっていう気持ちを起点としてアートフェスを作っていた、ということです。決して、海外のアートフェスに憧れて真似したくて作ったわけでもないし、商業的な動機からやっているわけでもなかったんです。
その意味ではみんな、そのまちだからやれること、そのまちでしかできないことをアートフェスとして昇華させていました。そんな彼らの話を聞いて「あ、これでいいんだ」って、ぼくらも自信を持てたなって気がしました。
だから逆に彼らからすると、山形ビエンナーレを見て「あ、俺たちがやっていることを山形でやるとこうなるのね」っていう共感を持ってもらえたんじゃないかな。

ただ、ゲストのうちのおひとり、5回目の特別講座で来てくださったKYOTO GRAPHIEのプロデューサー・仲西祐介さんだけはもっと商業的な感覚で、世界中の人たちが集まる京都でカンヌ映画祭くらいの規模のものを作ろうとしています。その仲西さんに山形に来ていただいたのはちょうどビエンナーレ会期中でしたから、大学の展示もまちなかの展示も見てもらいましたけど、山形ビエンナーレをものすごく羨ましがって、嫉妬してくれました。「あの金額の予算規模でどうやってここまでできるの?」「どうやってこれだけさまざまなテーマのものを一括りにして作ることができるの?」ってね。
宮本:ビエンナーレ期間中のトークイベント・ゲストとして来てくださったミナ ペルホネンのファッションデザイナー皆川明さんは、山形ビエンナーレについて「ちゃんと旅をしている感じがした」という感想をくださいました。外国のまちや日本の地方を旅したときにその土地で生まれたものや丁寧に育まれてきたものに触れて「あぁここはこういう土地なのか」ということを理解して、満ち足りた気持ちで帰ってゆくという、本来の意味での旅を体験することができた、と。
地域のアートフェスっていうと、海外の作品を運んできて展示するようなグローバルにやるのが当たり前というものも多いなかで、「こうして山形に来て山形らしいものを見られてよかった」という評価をしていただけたのは嬉しかったです。アートフェスって、とかく複雑なものにしてしまいがちですけど、シンプルに提示するというのも大事だなと改めて思いましたね。
中山:等身大でね。
宮本:そうですね。また同じくトークイベントのゲストだった木工作家の三谷龍二さんは「愛着」というものを山形ビエンナーレに感じてくださったようでした。アーティストや学生やこの祭りに関わったみんながそれぞれのレベルで持っている山形のまちに対する愛、もちろんそれはいろんなカタチがあって、もしかしたら愛憎みたいなものもあるのかもしれないけれど、そうしたものを全部含めての「愛着」というものが、山形ビエンナーレに訪れた人にもちゃんと伝わったような気がしました。

中山:いろんな人たちから、嬉しい褒め言葉をもらえましたね。ぼくたちのビエンナーレが大事にしなきゃいけないところというのはまさにそのあたりだろうし、そこがズレてはいけないのかもしれません。
瀬戸内国際芸術祭も面白いし、越後妻有の大地の芸術祭も面白い。あれらはあれらで、あの規模でやれる最大限の面白いことをやっていて、特に、年々やればやるほどにまちに作品が残って増えて拡大していくところが凄いですよね。
それに対してぼくらは一回やっては片付けて、というのを毎回繰り返していて、まるで幻のような感覚になる。たしかにぼくらのビエンナーレって拡大はできないけれど、そのときそのときの旬のものをまさにそのときしか味わえない、思い出としてしか残らない、そんな切ない感じのするとても愛おしいビエンナーレとも言えるのではないでしょうか。
(2018.10.11)
中山ダイスケ(Daisuke Nakayama)/1968年香川県生まれ。現代美術家、アートディレクター、(株)daicon代表取締役。共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002年まで5年間、ニューヨークをベースに活動。ファッションショーの演出や舞台美術、店舗などのアートディレクションなど美術以外の活動も幅広い。山形県産果汁100%のジュース「山形代表」シリーズのデザインや広告、スポーツ団体等との連携プロジェクトなど「地域のデザイン」活動も活発に展開している。2018年4月、東北芸術工科大学学長に就任。
宮本武典(Takenori Miyamoto)/1974年奈良県奈良市生まれ。東北芸術工科大学美術館大学センター教授・主任学芸員。展覧会やアートフェスのキュレーションの他、地域振興や社会貢献のためのCSRや教育プログラム、出版企画をプロデュースしている。とんがりビル「KUGURU」キュレーター、東根市公益文化施設「まなびあテラス」芸術監督。akaoniとの企画・編集ユニット「kanabou」としても活動中。
三瀬夏之介(Natsunosuke Mise)/1973年奈良県生まれ。東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科長、芸術学部長。京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。修士。既存の日本画の枠にとらわれない、多様なモチーフや素材、時にはコラージュを施した作品の圧倒的な表現力が高い評価を得ている。トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞(2002)、五島記念文化財団 美術新人賞(2006)、第16回VOCA賞(2009)ほか、受賞多数。2013年 個展 N.E.blood 21 三瀬夏之介展 リアス・アーク美術館、日本の絵 三瀬夏之介展 平塚市美術館、2014年 特別展 三瀬夏之介-雨土(あめつち)の記展 浜松市秋野不矩美術館その他、シンポジウムやアーティストインレジデンスに参加するなど、精力的に活動の幅を広げている。