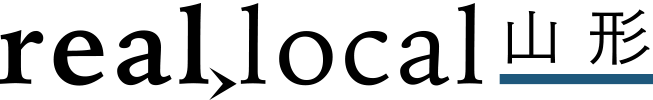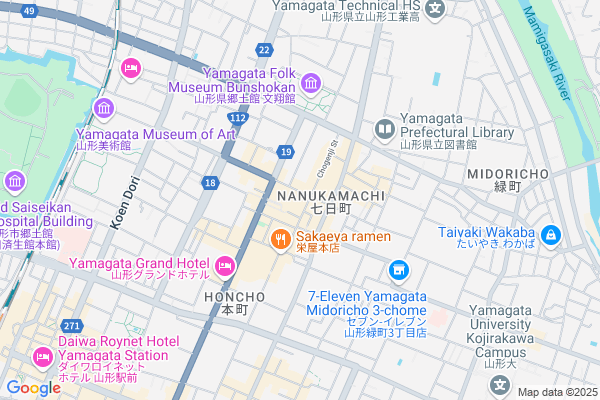「新生・郁文堂書店」に生まれ変わるまで

2016年12月末、クラウドファンディングにてプロジェクトを成立させた〈郁文堂再生プロジェクト〉。2017年の幕開けと同時に、今まで以上に忙しない日々が始まりました。着実に地域へコミットしてきたその文学の拠点を、再びのぞいてきました。
ワークショップ形式で進めた施工
プロジェクトを担う追沼くんと芳賀くんは、クラウドファンディング終了後の安堵感もそこそこに、すぐに業者との打ち合わせ、そして施工の準備を始めます。
1月には業者が入り、電気工事と窓の工事。2月、新しい窓から日の光がたっぷりと落とし込まれ空間がパッと明るくなった中、追沼くんと芳賀くん、そしてまちの人々を巻き込んだ自主施工がスタートしました。
さまざまな作業が行われていく中で、なんだかワークショップ形式の施工が多い印象。なにか意図があるのでしょうか?
(追沼くん)「クラウドファンディングも、郁文堂を地域に根ざした場所にするために、まちのみなさんの支援でつくろうという意図から始めました。だから施工でも実際にみんなでつくり上げていきたいと思って、ワークショップ形式に行き着きました」



緊張と安堵感でいっぱいのプレオープン

郁文堂にこもり、ひたすら作業を進めながら駆け抜けた4カ月間。4月8日に開催されたプレオープンでは、地域の人がぞくぞくと集まってきた光景を前に、緊張と安堵感でいっぱいだったと芳賀くんは言います。

(芳賀くん)「新しくつくったフローリングで子どもたちが踊っていたのが印象的でした。地域の人が実際にこの空間でくつろいだり、談笑している光景を見てこの場所をつくってよかったと感じました」
自分たちの描いていた妄想がついに現実として目の前に現れ、郁文堂書店が“まちの新しい本屋さん”としていよいよ動き出したことを実感した1日だったのでしょう。
一年を振り返って「楽しむことが原動力」
〈郁文堂再生プロジェクト〉が立ち上がってから約1年。なんだか2人とも1年前からずいぶん顔つきが変わってきたように感じます。立ち上げ当時と現在の気持ちの変化を聞いてみました。

(追沼くん)「前より人に素直に頼れるようになりました。実は、プロジェクト立ち上げ当初はすべてセルフDIYで、『自分たちのできる範囲でやろう』と考えていたんです。でも今では『自分たちだけではできないけれど、ここまでやったほうがいいな。周りに助けてもらいながら挑戦しよう』という考えになりました」

(芳賀くん)「“まちを変えたい”というのが一番最初ではなかったんです。ただ、クラウドファンディングを始めて、たくさんの方から支援と協力をもらってちゃんとしたクオリティーにしようと思ったときに、どうしたら地域の人に喜んでもらえるか、ここに足を運んでもらえるかということを考えるようになった。自分たちのできる範囲でやって楽しむ場所ではなく、みんなのための場所という意識に変わりました」

(追沼くん)「意識が変化したきっかけとしてクラウドファンディングで資金を募ったことは大きかったです。最初はプレッシャーでしかなかったけれど(笑)。でも、今は本当にありがたいと思っていて、協力してくれた方にちゃんと恩返しする気持ちで取り組んでいます」
(芳賀くん)「なにかに取り組むときの根本には、全部“楽しむ”という気持ちがあります。郁文堂再生プロジェクトも企画案で留まると思っていたけど、楽しそうだから実際に実現してみようと思った。全部“楽しい”が先行してるんです(笑)。なにか楽しいことがしたくて、問題を探して、実践する」
「最終的に着地する場所が“楽しい”だったら、実現するまでが多少つらくてもいいんです」きっぱりと放たれた言葉に、2人の根底にあるモチベーションを垣間見たような気がしました。

新生・郁文堂書店のこれから
5月末にグランドオープン予定の郁文堂書店。追沼くんと芳賀くんの妄想と構想は止まりません。
(追沼くん)「これから子どもからお年寄りまで気軽に来てもらえるように、ちぎり絵や金継ぎなど、カルチャー系のワークショップを企画しています。あと、6月からドキュメンタリー映画祭とコラボして郁文堂で映画を上映する予定です」
(芳賀くん)「まなび館で行われている一箱古本市を、もっとまちに分散させていきたいですね。イベントでなくても、道端に本棚があって、その近くに椅子と机があって、そこで人が本読んでるという風景が日常にできるといいなと思います」

地域の人々を結びつける主役の本棚たちは、これからぞくぞくと郁文堂に集まってくる予定。どんな本に出会えるだろうか。どんな人に出会えるだろうか。ここでは本と本、本と人、そして人と人とが結びついていく瞬間が、たくさん散らばり広がっていくのでしょう。
20代の若者と、この場所を愛し守り続けるおばあちゃんによって生まれ変わった山形の文学の拠点、〈新生・郁文堂書店〉。彼らのさまざまな妄想や企みに、これからも目が離せません。