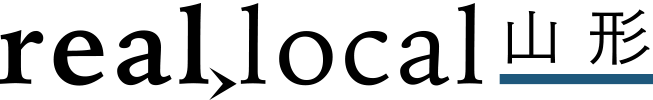中山ダイスケ × 宮本武典【前編】/ぼくらのアートフェス 1
2018年秋に山形ビエンナーレが開催されるのをまえに、トークイベント「ぼくらのアートフェス」が始まった。全5回のこのシリーズは、全国で開催されているアートフェスのディレクターをゲストに迎え、東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長が聞き手となって、それぞれのアートフェスに込められた想いを掘り起こし、その魅力を紐解いていくもの。芸工大の学生にとっては単位修得の講義となっており、学生たちに芸術祭への理解を深めてもらいつつ、会期中はスタッフとしてより楽しくより深くビエンナーレに参加してもらうという狙いもある。
第1回のゲストに登場したのは、山形ビエンナーレのプログラムディレクター宮本武典さんだ。

地域との関係性の
模索から始まった
中山:今日から連続シリーズとして「ぼくらのアートフェス」と題した講義をやります。世界中に様々なフェスがありますが、ここではプロデューサー自らが現場をつくっている小規模のものに焦点を当て、つくった人の想いと地域が繋がったときに起きるシナジーがどんなものなのかお聞きしたいと思います。単なる学びを超えて、学生のみんなに「あの人みたいに自分もやってみたい」と感じてもらいたいです。今回のゲストは宮本武典さん。早速ですが、どういう想いで山形ビエンナーレをつくって来られたのでしょう。
宮本:まずは「Road to ビエンナーレ」からお話ししたいと思います。僕は芸工大に来て13年目になります。ここに来てすぐの頃、国際的にも知られている現代アーティストの展覧会をやりたくて、写真家の宮本隆司さんや彫刻家の舟越桂さんの展覧会を企画しました。でも、反応がとても薄くて。「すごく有名なアーティストです」と言っても、「でもその方と山形にはどういう繋がりが?」ってなっちゃって。

中山:東京だったら連日満員御礼になるラインナップなのにね。
宮本:そこで少し方向性を切り替え、今度は西雅秋さんという彫刻家に山形で滞在制作をしてもらいました。そしたら学生は手伝ってくれるし、地元の新聞社は取材に来てくれるし、非常に盛り上がりまして、その年の某新聞社が選ぶ展覧会ベスト10にも選ばれました。その手応えもあって、出来上がった作品を持ってくるのではなく、作家さんに山形に滞在制作してもらうスタイルを基本とするようになりました。

中山:アーティストが大学で滞在制作すると、大学中がザワザワしますよね。大学の池の周りに突然何かが現れたり、学生が集まって石膏をぶっ壊したり。ああいうシーンが見られて面白かったですね。

宮本:そうですね。そんななかで重要なターニングポイントとなった出来事がありまして、新潟の越後妻有トリエンナーレという芸術祭でのことです。当時僕は芸術祭の記録撮影チームとして運営をサポートしていたのですが、それとはまた別にプライベートで妻と子どもと一緒にこの芸術祭を見て回る機会がありました。そうしたら現代アートはかっこいいし、死や痛みや忘却というテーマはアート好きにはエッジが効いてて面白いけど、子ども連れで行くとあんまり見るものがないんだな、と自分なりに思うところがありました。
中山:キュレーターとしてはエッジの立った現代アートをバチバチやりたいけれど、子どもの反応がアートに対する姿勢の転換点になるっていうのはよく分かる気がしますね。

宮本:また、ある廃校プロジェクトの座談会で、その地区のおじさんたちと美大の学生たちとのディスカッションの場に居合わせたときに、学生たちが「僕ら都会の人間から見るとこういう廃校ってかっこいいんです」みたいなことを言ったら、微妙な雰囲気になりまして…。「廃校になった地域の気持ちを理解できてますか?」ってことですね。受け入れる地域の側の想いと、廃校ってクールでアートよねみたいなこと言ってる側のギャップを目の当たりにしました。
中山:かつてそこに子どもたちがいた木造の古い校舎がアート作品として活用できちゃうというのがネタとして面白いのもわかるし、昔の子どもたちの声の残像が残った校舎というものが、地域の人にとっては悲しいものだってのもよくわかるよね。
宮本:そんなきっかけから、もう一度地域から芸術祭を考えたい、そして弔いや忘却へのあがないではない、希望みたいなものをアートで扱えないかなって思うようになったんです。

アーティストと地域の人と一緒に
小さなお祭りをつくっていく
宮本:そこで、現代アート業界のエッジの効いた展示ではなく、絵本作家と一緒になにかやれたらと思ってオファーしたのが、のちにビエンナーレの芸術監督をやっていただくことになる荒井良二さんです。
2010年の「荒井良二の山形じゃあにぃ」という展覧会では、山形市内にある使われなくなった校舎で、地域の子どもたちやお母さんたちと一緒になって小さなお祭りのような空間をつくりました。それがとても良くて、来場者数も2万人近く集まり、自分の考えは間違ってなかったと思って、荒井さんと定期的にアートイベントをやるようになりました。
2011年に震災が起きるわけですが、この「山形じゃあにぃ」で一緒になった仲間がそのまま復興支援プロジェクトの仲間になりました。被災地を回り、復興を応援するフラッグづくりのワークショップをやったり、ライブしたり。

中山:大きな旗をつくったりもしましたね。
宮本:やりました。そうした復興支援のワークショップキャラバンを通して、アートがアート好きのためのものではなく、そういう状況下でも何かしらの力になることを強く感じました。中山先生と一緒にやったプロジェクトもありましたね。
中山:原発事故で街を出なくちゃいけなくなった南相馬の子どもたちを大学に呼んで、グラフィックデザイン学科の学生たちと一緒に演劇をつくりましたね。あれは面白かったな。
宮本:震災直後は本当にいろんな人が力を出し合い、様々なプロジェクトを立ち上げましたけど、山形ビエンナーレってその時に出会ったアーティストたちとずっと一緒に活動し続けている感じなんです。
東日本大震災を語りつぐ絵本をつくる『東北未来絵本 あのとき あれから それから それから』というプロジェクトは、大きな転換点になりました。「この絵本づくりにみんな参加しませんか?」と新聞広告で呼びかけたら、ものすごくたくさんの人が自分の声を届けてくれました。それを荒井さんとまとめて一冊の絵本にしたのですが、このとき、アーティストではない普通の人たちに参加してもらって想いを入れてもらうことですごい作品ができることを感じました。


アーティストが自身のスペシャルな才能を投じるだけではなく、スペシャルな力を持っているアーティストと普通の人たちが一緒にやることでより面白くなる。普通の人のなかにある創造力や、表現への欲求をアーティストたちが引き出して行くことに可能性があるという発見が、ビエンナーレにつながっていきました。


中山:引き出し方がうまくいくと、その人たちの参加意識がぐっと上がりますしね。やらされたのではなく、自分がやったことがこんなに素敵なものになったと喜んでくれるわけで。
宮本:そうですね。そして山形ビエンナーレが2014年に始まるのですが、大事なのは「市民参加型」ということでした。アーティストが旅人になって作品をつくるのではなく、地域の子どもたちやお母さんたちや様々な立場の人たちがこのプロジェクトに関わることで、芸術祭がみんなのものになっていく。みんなが関わることで、みんなが表現する人になり、表現を躊躇しない人になっていく。
中山:学生のみんなにも、本当にそうなってほしいですね。自分のまちが面白くないならそれは面白くするチャンスなんだと思えるようになってほしいし。たった一軒のカフェからでもイベントはつくれるし、そういう体験をクリエイトできる人になってほしいですね。
宮本:そういう人が多い街は魅力的ですしね。
中山:そう、クリエイティブな人がたくさんいる、変わった大人がたくさんいる街は面白いですよね。そういう街って昔はたくさんあったはずなんだけど、今は均一化されてしまって。イベントだって「ライブ行きたいなー」なんて、参加することばかり考えているけど、「ライブをつくろう!」っていう人はなかなかいない。でも、ライブもつくれるんだよね、意外と簡単に。

〉〉〉後編へつづく
宮本武典(Takenori Miyamoto)/1974年奈良県奈良市生まれ。東北芸術工科大学美術館大学センター教授・主任学芸員。展覧会やアートフェスのキュレーションの他、地域振興や社会貢献のためのCSRや教育プログラム、出版企画をプロデュースしている。とんがりビル「KUGURU」キュレーター、東根市公益文化施設「まなびあテラス」芸術監督。akaoniとの企画・編集ユニット「kanabou」としても活動中。
中山ダイスケ(Daisuke Nakayama)/1968年香川県生まれ。現代美術家、アートディレクター、(株)daicon代表取締役。共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002年まで5年間、ニューヨークをベースに活動。ファッションショーの演出や舞台美術、店舗などのアートディレクションなど美術以外の活動も幅広い。山形県産果汁100%のジュース「山形代表」シリーズのデザインや広告、スポーツ団体等との連携プロジェクトなど「地域のデザイン」活動も活発に展開している。2018年4月、東北芸術工科大学学長に就任。
トークイベント撮影_根岸功
展覧会およびビエンナーレ写真提供_宮本武典