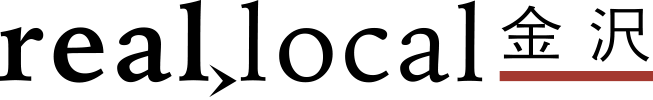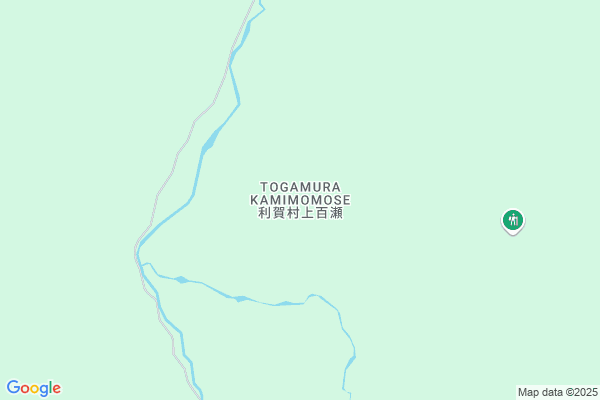伝説の名作『世界の果てからこんにちは』観劇記/人口500人の村にある演劇の聖地・富山県南砺市利賀村”SCOT”
東京から金沢に、家族でUターンしてきた僕が気に入っている、近隣の子連れスポットやイベントをご紹介。初回はお隣富山県ですが、何せ衝撃的だったもので。それに南砺市は金沢から意外と近いんですよ。
金沢から車で約1時間半。富山県南砺市利賀(とが)村にある舞台芸術の聖地、 SCOT (スコット)。
“SCOT”(Suzuki Company of Toga)
利賀村は富山県の深い山間部に位置した緑豊かな農村で、愛を込めてあえてこう表現しますが、「日本の古き良きド田舎」です。時代の変化に流されなかったのか、
日本昔ばなしの風景そのままに、山と田んぼ、クネクネの道、たまにポツポツとある民家。風光明媚。しかし人口は約500人の過疎の村です。


そんな村の一画に、利賀芸術公園という野外劇場、稽古場、
専門的な解説はその道の方にお任せするとして、
「演劇とか、見たことないし」
そういう方でも楽しいやつ、ご紹介します。しかも子どもと一緒に行けます。
それは、『世界の果てからこんにちは』。
この同じ演目を、我が家は毎年、繰り返し観ています。もはやこれを観ないと夏が終わらない、そのくらいの存在になっています。

それほど、この公演を初めて観たとき、度肝を抜かれ、魅了されました。
夕暮れになると、茅葺き屋根の待合所に、何百人という人が続々と集まってきます。全国津々浦々からの日本人だけじゃありません。ここは京都の有名観光地かと見紛うほど、欧米人も沢山います。東京からでは半日以上の移動時間がかかります。それにもかかわらず、舞台を観にこれだけの人が訪れる。本当に国際的な「聖地」なのだと実感します。

待合所から野外舞台に向かうと、これまた素晴らしい光景が広がります。観客席はすり鉢状の半円形で、一番奥の高いところから入ります。観客席は満員。多くの人がひしめき合って、今か今かと開演を待つ。都会のような熱気です。
その視線の先には黒い御影石が敷き詰められた舞台があり、小道具であろう椅子が並び、ただならぬオーラを放っています。背後には大きな池があって、闇を吸い込んだ黒い水が広がり、池の周りの樹々は覆いかぶさるよう枝を伸ばしています。さらに奥に目をやると、利賀の山々がそびえています。
「この村全体が舞台である。」そう感じさせる圧倒的な空間のちから。そこに集まる人の息づかいと、それを吸い込むような自然が対峙する緊張感。どこまでが現世で、どこまでが来世なのか。そんな不思議な気分になってきます。そうかここは「世界の果て」だった。その境界に舞台が位置していますから、劇が始まって登場する演者たちは、まるで黄泉の国からの使者のように見えてくる。


『世界の果てからこんにちは』は1991年に初演があって、戦中から戦後の日本の国家がテーマだそうです。「だそう」というのは、3回も観ているにもかかわらず、まだその意味するところは、よく分からないからです。テレビドラマのように誰もが同じ感情の起伏へと誘導されるような、明快な一筆書きの展開ではなくて、病院や戦場、男女の別れなど、さまざまな場面が断片的に、まるでパッチワークのように継いだ構成なのです。だから人によって、その日の気分によって、受ける印象が異なってくる。
受け手が断片を頭の中で繋げてストーリーにしていく。ある人は悲しいと感じ、ある人は楽しいと感じるでしょう。そんないろんな解釈がありえる、寛容にして多様なもの、そんな舞台。だから、何度でも観たくなる。



でも、静かで難解で眠たくなるというのではありません。演者が昭和の歌謡曲『夜の訪問者』を大声で歌う場面や、目玉の何発も真上で打ち上がる大迫力の花火などがあって、刺激に満ちています。花火は火の粉に手が届きそうなくらい近くて、散った一つ一つが闇に消えていく瞬間まで見えます。その近さだと鼓膜のみならず、空気の振動が頬を震えさせるのも初めて知りました。
花火がクライマックスを迎えたころ、圧巻のフィナーレを迎えます。ついつい意味を問いたくなる自分がいますが、それにひとつのヒントを与えるセリフを、主人公が最後、口にします。それは現地でのお楽しみ。まるでこちらの心が見透かされたような一言で、ぼくは鳥肌がたちました。
そして残るのは、空の焦げたような匂い。



子どもたちが退屈するかというと、そうでもありません。連れてきてみるものです。花火はもちろん楽しみますが、間を置いて放たれる台詞にゲラゲラと笑ったり、不思議な踊りに目を凝らしたり。「よく分からない」と諦めたくなるオトナよりも、より直感的に楽んでいるようにもみえます。断片の間の空白を自らの想像で満たす。子どもたちにはその能力が、元々備わっているんじゃないか。そんな気になって、羨ましくも思えたり。その感覚、大事にしてあげたい。


閉幕後、鈴木さんが登壇し、これまでのいきさつをお話されます。
高度経済成長まっしぐらの時代、世界を舞台に第一線で活躍していた鈴木さんがこの村に移ると決めたとき、メディアは「

『世界の果てからこんにちは』には、「ズシン」と腹にくる何かがあります。
一糸乱れぬ美しい身体の動き、沈黙を破る咆哮、花火が散って震える空気。自然に抱かれた環境に、いろんな人が集まって、それを共に喝采する。その興奮が、生きた記憶となって身体に居座り続けるのです。
日々たくさんの情報が流れ込んで、ほとんどは消尽してしまう。そんな時代に、こんな鉛のような体験ができるエンターテイメントは、世界広しといえども最早あまり残されていないのかもしれません。だからその「ズシン」を求め、世界中から人が集まる。27年前にできたこの舞台は、時代が進むほど、ますます価値を高めている。そう思わせるものがあります。
そして、なぜなんだろう。こういう記憶こそ、また再生したくなる。
帰りの車では子どもたちが、劇中歌『夜の訪問者』の「きっと、きっとまた来てね。素敵な私の夜の訪問者」というサビの部分を何度も復唱していました。そのとおり。また来たいと、不思議と思えるのです。